万年床って何? ダメといわれる3つの理由や対策法を紹介
公開: 更新:

※写真はイメージ

真冬に上着を忘れた警察官 震えながらの説得に違反者が放った一言筆者が交番勤務をしていた頃、同い年で公私ともに仲のよい相棒がいました。警察官を辞めた今でも交流は続いています。 彼をひと言で表すなら『天然』。 早朝の事故対応に向かう車内で、昇る太陽を見ながら「昨日は満月だったんだね…」...
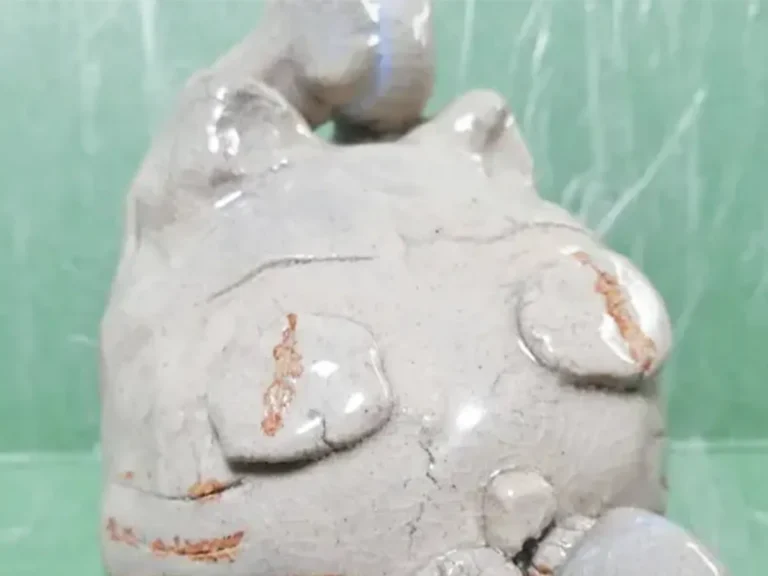
おでこにのせたはずが? 陶芸教室で作った猫の鈴、焼き上がりに吹き出す子供には、小さいうちから、できるだけいろいろな体験をさせてあげたいですよね。 ある日、筆者もそう考えて、息子たちと1日陶芸教室に行ってみました。 オーバーヘッドキックをする猫の陶鈴を作ったはずが? 陶芸教室では「猫の陶鈴...


「布団を敷きっぱなしにするのはよくないのだろうか」
「腰痛持ちで布団を押し入れに収納できない」
こんな風に悩んでいる人もいるでしょう。
布団を出しっぱなしにする「万年床」は、カビやダニの発生原因になるため、避けるのが好ましいです。衛生状態がよくない布団で寝ていると、身体に悪影響を及ぼす可能性があります。
しかし、腰痛持ちや収納する場所がないなどの理由で、どうしても布団を片付けられない人もいるでしょう。
そこで本記事では、万年床のデメリットやカビやダニなどの対策法を紹介します。腰痛持ちの人でも実施できる対策法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
万年床(まんねんどこ)とは布団を床に引きっぱなしにしている状態のこと
※写真はイメージ
万年床とは、布団を収納せずに床へ引きっぱなしにしている状態のことです。万年床にしておけば、好きな時に布団の上で横になれます。毎日布団をたたんだり、上げ下ろしたりするのが面倒で、万年床にしている人も珍しくありません。また収納場所がなくて、床に引きっぱなしにしている人もいるでしょう。
しかし、ケアをせず使い続けている布団には、以下の汚れが溜まります。
万年床を続けていると汚れが蓄積され、湿気が溜まりやすくなり、ダニやカビなどが発生する原因になります。衛生面を考えると、万年床は避けたほうがいいでしょう。
万年床がダメといわれる3つの理由
※写真はイメージ
ここでは、万年床がダメといわれる理由を3つ紹介します。
万年床は衛生的に良くないことに加えて、睡眠の質も落ちてしまいます。
ダニの増殖
万年床は、ダニの増殖を促進します。汗や汚れによって、湿気が溜まりやすくなるためです。人は寝ている間に200㎖の汗をかくといわれており、その汗を布団が吸ってしまいます。特に暑い時期では、500㎖の汗をかくケースも。
また寒い時期に、布団と床の温度差で結露が発生することも、ダニの増殖を促進する理由です。ダニは、湿気や結露が発生している状態を好み、布団に付着した汚れをエサにして繁殖します。布団に生息しているダニの多くは「ヒョウダニ」と呼ばれる種類です。
噛むことはないため、万年床の状態で寝ていても身体が痒くなるケースは少ないです。しかしヒョウダニは、以下のアレルギーを引き起こす原因になります。
アレルギーを引き起こす原因になるのは、ダニの死骸や糞です。ダニを駆除した後に、布団に掃除機を掛けて、死骸や糞も取り除く必要があります。ダニによるアレルギーを防ぐためにも、万年床は避けたほうがいいでしょう。
カビの発生
湿気の溜まりやすい万年床は、カビも発生しやすいです。特に結露が発生しやすい布団の裏側は、カビが好む環境なので要注意。
カビは掃除機や洗剤などで普段から布団をケアすれば、ある程度防げます。しかし布団の中に潜む胞子は落としづらいので、そもそもカビが生えないようにすることが大事です。
胞子を吸い込んでしまうと、人体に悪影響を及ぼす可能性があります。もし人体への被害はなかったとしても、カビの原因で床を傷めるケースも珍しくありません。賃貸や持ち家に限らず、床の修繕費や退去費など、余分な費用がかかってしまいます。
カビの発生を防ぐためには、布団を干したり、除湿したりなどの対策が必要になります。
睡眠の質低下
万年床は、睡眠の質の低下につながります。万年床によって湿気を吸った布団は、弾力性が損なわれてしまうためです。購入した当時と比べてぺったんこになってしまいます。この状態の布団で寝ると、肩甲骨やお尻など、人体の出っ張った部位に余分に圧力がかかってしまい、寝心地が悪くなるでしょう。
睡眠の質が低下すれば疲れが取れにくくなってしまうため、仕事や日常生活などに悪影響を及ぼしかねません。毎日7〜8時間ほどを費やす睡眠は、生きていく中でこだわりたい部分です。弾力のある布団を維持するためにも、万年床は避けたほうがいいでしょう。
万年床のカビ・ダニの対策法8選
※写真はイメージ
万年床がダメなのは分かったけれど「腰痛を抱えており布団を持ち上げられない」「収納する場所がない」と、悩んでいる人もいるでしょう。
そこで、そんな人でも万年床のカビやダニを対策できる方法を8つ紹介します。
万年床を解消したいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
布団をたたむ
布団をたたむことで、床の湿気が逃げるため、カビやダニなどを予防できます。しかし起床直後に布団をたたむのは避けましょう。寝ている間に布団の中に溜まった湿気がこもったまま、収納することになります。
まずは湿気を取り除く必要があるので、布団をでて少し経ってから、具体的には着替えや朝食などを済ませた後にたたみましょう。可能であれば、掛け布団と敷布団を椅子などにかけて、空気にさらしておくのがおすすめです。
布団クリーナーを使う
布団クリーナーを使えば、万年床のダニやカビの対策ができます。布団クリーナーとは、マットレスや敷布団など、布団用に作られた掃除機のこと。ダニを弱らせるUVランプが付いている、布団掃除に特化した家電です。布団クリーナーを使って掃除することで、汚れの少ないきれいな状態を保てます。
ダニやカビの駆除や発生の予防を目的とするなら以下の機能が搭載されている布団クリーナーを選びましょう。
通常の掃除機でも布団の掃除はできますが、床やカーペットのごみが布団に付いてしまうので、おすすめしません。布団専用の掃除機を使って、ダニやカビの対策を行いましょう。忙しくて布団を干すヒマがなかったり、雨が続いたりした時におすすめな方法です。
ダニ・カビに強い素材を使う
腰痛を抱えているなど、身体的な事情で万年床になっている人は、ダニやカビに強い素材の布団を購入することも検討しましょう。例えば、以下の素材の布団が防ダニ対策におすすめです。
万年床の状態にしておいても、普通の製品に比べてダニやカビを防ぎやすいです。しかし薬剤や特殊な繊維が使われているため、価格が高くなる傾向にあります。
身体的事情で布団を片付けたり、干したりできない人には、おすすめな方法です。
布団乾燥機を使う
布団乾燥機も、万年床のダニやカビへの対策に効果的です。布団乾燥機とは、布団内に温風を送ることで湿気を取り除く家電機器。湿気を取り除くことでカビが発生しづらい環境を作れます。
またダニの除去にも効果的です。ダニは50℃以上の熱で死滅するとされています。布団乾燥機から送られる高温が50度以上であれば、ダニを除去できるでしょう。しかしダニの死骸は、以下のようにアレルギーを引き起こす可能性があります。
ダニが繁殖してしまった場合には、ダニを駆除するだけでなく、死骸を除去することが大切です。布団乾燥機を使った後は、ダニの死骸を除去するために、布団の上から掃除機をかけましょう。ダニの死骸が減るので、布団をより清潔にできます。
除湿対策をする
除湿対策も、万年床のダニとカビの発生を防ぐ方法の1つです。除湿対策を行い、布団の湿気を取り除くことで、ダニとカビの増殖する環境を作らないことが大切です。主な対策法は、以下のとおり。
また部屋干しを控えたり、換気をしたりすることで、室内の湿度を抑えられます。寝室や布団を敷いている場所の除湿を行い、ダニやカビの発生を事前に防ぎましょう。
ベッドを使う
万年床のカビとダニの対策として、布団からベッドに切り替える方法があります。布団の上げ下ろしが必要ないため、腰痛持ちの人でも万年床の対策が可能です。ベッドは床と天板の間に空気の逃げ道があるため、敷きっぱなしにしていても、布団と比べてカビやダニが発生しにくい点がメリットです。
それでもカビやダニの発生が不安な人は、厚めのマットレスを購入しましょう。厚めのマットレスは、通気性に優れた製品が多いため、ダニやカビが発生しづらい環境を作りやすいです。またマットレスの上に敷きパッドやシーツなどを重ねれば、外して洗うだけで湿気や汚れを取り除けます。
しかし、1年中同じマットレスを敷きっぱなしにするのは、衛生的によくありません。寝室を換気するなどの、定期的な除湿対策は必要です。
すのこを使う
万年床のダニとカビの対策に効果的な方法は、すのこを使うこと。すのこによって布団と床の間に隙間ができるので、湿気が溜まりづらくなり、カビやダニが増殖する状態の予防につながります。
すのこを購入する際は、湿気に強い素材を購入するのがおすすめです。たとえば、桐で作られたすのこは、湿気に強い傾向があります。一方でパイン材のすのこは、湿気に弱いのでおすすめできません。
注意点は、すのこを使ったからといって、完全に湿気をなくせるわけではないということです。すのこを使っても布団を敷き続けていれば、カビやダニが発生します。
そこで便利なのが、折りたたみ式のすのこです。キャスターつきのすのこなら、折りたたむだけで敷布団を置いたまま部屋干しが可能になるため、腰痛持ちの人でも簡単に万年床を防げるでしょう。
扇風機で送風する
布団に扇風機で風をあてることで、ダニやカビの発生を予防可能です。布団の湿気をとばすために行います。
雨の日で天日干しができない日が続いている場合は、扇風機で風を送り、空気にさらしましょう。少しでも湿気を取り除くことができれば、ダニやカビの発生予防につながります。
また除湿機と併用すれば、よりダニやカビを予防できます。特に梅雨時期は、ただ家の中で干しているだけでは湿気は抜けにくいため、空気を循環させながら除湿してあげるといいでしょう。
イスに布団を掛けてから扇風機をあてると、効率よく湿気をとばせます。
特別な事情がなければ布団はたたんで収納しておこう
※写真はイメージ
布団を床に引きっぱなしにしている状態の万年床は、ダニやカビの発生原因になります。また布団の弾力性が失われて、睡眠の質が下がることも。衛生面を考えると、万年床は避けたほうがいいでしょう。
しかし腰痛持ちや収納スペースがなくて、万年床をせざるをえない状況の人もいらっしゃると思います。そんな人は、布団クリーナーを使ったり、すのこの上に敷布団を置いたりなどの対策を実施しましょう。布団の上げ下ろしをする必要がなくなるので、腰痛持ちでも、安心して布団のケアを行えます。
特別な事情がない限り、布団はたたんで収納しておきましょう。睡眠は1日の約3分の1を費やす行動です。清潔で寝心地のよい布団で睡眠をとりましょう。
[文・構成/grape編集部]