【日本初】琵琶湖の水中に没した江戸時代の遺跡が発見される!
公開: 更新:

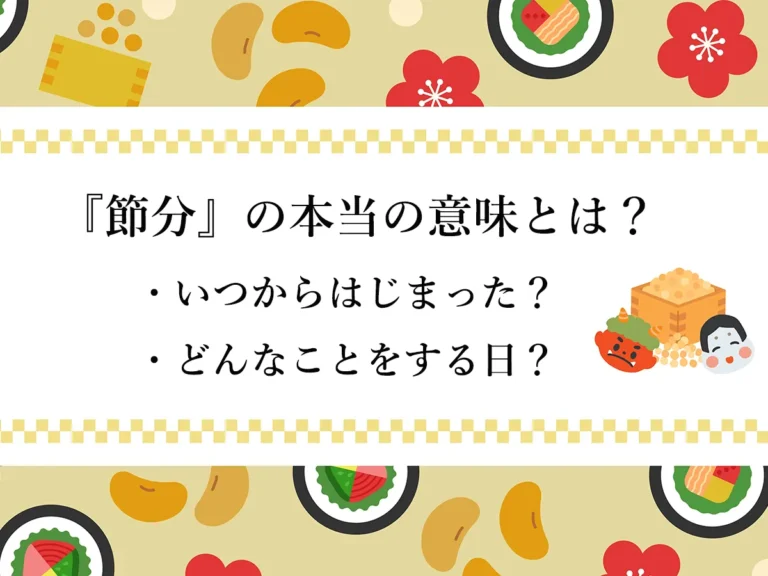
『節分』の本当の意味とは?いつからはじまったのか、何をする日なのかを解説!この記事では、節分とは何か、その意味や由来、節分の日の風習を分かりやすく解説します。行事の起源や節分に関するさまざまな風習を知ることで、毎年の行事がもっと楽しくなるでしょう。
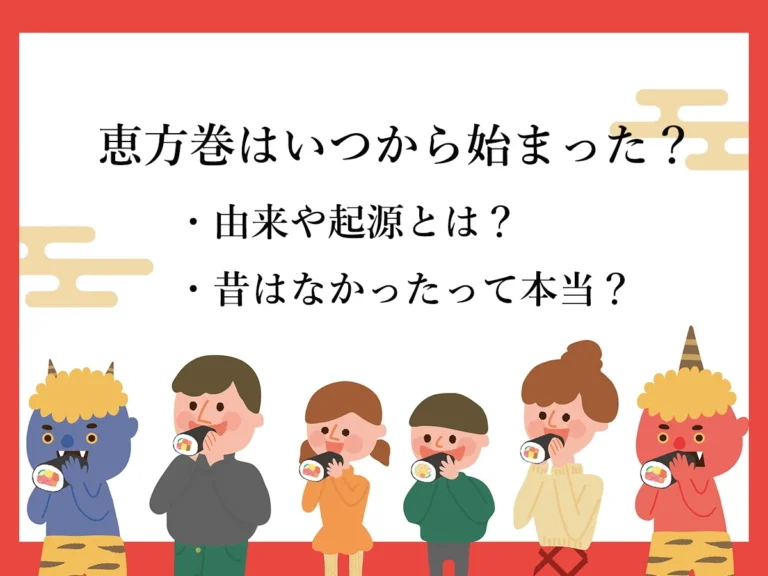
恵方巻はいつから始まった?由来や起源、広まった理由を解説!この記事では「恵方巻がいつから始まったのか知りたい」という人向けに、 恵方巻のルーツや「昔はなかった」と言われる理由を紹介します。一緒に見ていきましょう。


日本最大級の湖「琵琶湖」の湖底で、江戸時代の祠とみられる建物跡が発見され、話題になっています。
建物跡を発見したのは「水没村伝承」などを研究する琵琶湖水中考古学研究会。湖底に立ったままの柱8本や石積みなど、水中遺跡で建物の跡が見つかったのは、国内では今回が初めてのこと!
「水没村伝承」や「湖の底の祠」のキーワードが好奇心をくすぐりますが、ネット上でも驚きに満ちた声が続出しているようです。
地盤沈下が原因?
発見場所は、豊臣秀吉が築城した長浜城の遺跡と呼ばれるあたりから、沖合100メートル、水深1.8メートルの湖底周辺。
放射性炭素で柱の年代測定を行ったところ、江戸時代後期の1801年~1818年の建物ではないかと考えられています。
また、祠は1819年の文政近江地震が原因で、湖底に沈んだ可能性があるとのこと。当時、滋賀を震度6弱とかなり大きな地震が襲ったようです。
まだ発見されたばかりなので、詳しいことは今後の研究で明らかになっていくかもしれません。もしかしたら、面白い伝承や伝説が見つかるのかもしれない…、今からちょっとワクワクしてしまいますね。