縁側の役割やメリット・デメリットは? 濡縁やウッドデッキとの違いも
公開: 更新:

※写真はイメージ

真冬に上着を忘れた警察官 震えながらの説得に違反者が放った一言筆者が交番勤務をしていた頃、同い年で公私ともに仲のよい相棒がいました。警察官を辞めた今でも交流は続いています。 彼をひと言で表すなら『天然』。 早朝の事故対応に向かう車内で、昇る太陽を見ながら「昨日は満月だったんだね…」...
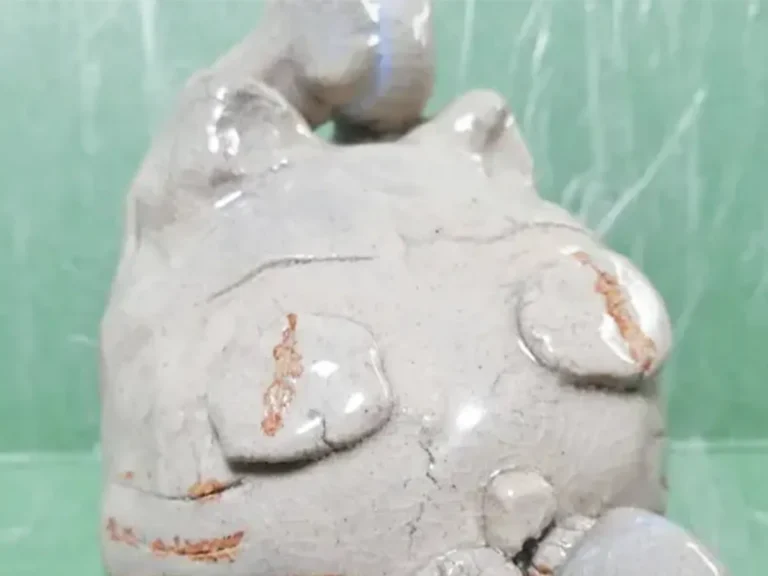
おでこにのせたはずが? 陶芸教室で作った猫の鈴、焼き上がりに吹き出す子供には、小さいうちから、できるだけいろいろな体験をさせてあげたいですよね。 ある日、筆者もそう考えて、息子たちと1日陶芸教室に行ってみました。 オーバーヘッドキックをする猫の陶鈴を作ったはずが? 陶芸教室では「猫の陶鈴...


昔ながらの日本家屋の特徴の1つである縁側。しかし、縁側がなぜ付いているのか知らないという人も多いのではないでしょうか。
こちらの記事では、「縁側を作ろうか迷っている」「ウッドデッキとの違いを知りたい」「縁側を有効活用したい」という人に向けて、縁側の役割や種類、メリット・デメリットを解説します。
縁側の役割とは
※写真はイメージ
縁側には、主に2つの役割があります。
1つ目は機能面。室内と外をつなぐ位置にあるため、暑さや寒さを緩和してくれます。夏は太陽の日差しを防ぎ、冷房の利きを助けてくれることでしょう。
室内にあるタイプの縁側であれば、冬は外の空気との間にワンクッション挟むことができ、部屋の温度を保ちやすくなります。
2つ目は、コミュニケーションの場としての役割。室内にいると、外からの声が届かなかったり、場合によっては話しかけづらかったりする場合があります。
しかし、縁側に居れば、帰ってきた家族にすぐに声をかけたり、地域の人も声がかけやすい雰囲気を作れたりすることでしょう。1人でゆっくりと縁側に腰掛け、四季の移ろいを楽しめるというところも縁側の魅力です。
縁側の種類
縁側には、大きく分けると2種類あります。軒下に設置されている室外タイプのものと、窓の内側に設置され、廊下の役割も担っている室内タイプです。前者の室外タイプのものは『濡縁』、後者の室内タイプは『くれ縁』と呼ばれています。
さらに細かく分けると、濡縁タイプでも雨戸の付いたタイプや、縁側が濡れないように屋根を広くとったタイプも。濡縁とくれ縁を両方設置している家など、さまざまな縁側があります。
縁側を作るメリット
※写真はイメージ
縁側を作る実用面でのメリットは、室内を過ごしやすい気温にしてくれる点です。縁側を作ることで、外と室内までの距離が広がるため、日光が直接室内に入るのを防げます。夏であれば、日差しがかからないぶん、部屋の温度が上がることを防げるでしょう。
また、冬も外気との間に空間ができることで、室内の温かさを保てます。日向ぼっこをしてくつろいだり、近所の人と軽く会話をするためのスペースとして使うこともできるでしょう。
縁側を作るデメリット
※写真はイメージ
生活を豊かにしてくれる縁側ですが、デメリットもあります。日々のメンテナンスの手間がその1つです。
室内タイプであれば、埃がたまるので掃除機や掃き掃除が必要になり、室外タイプであれば雨風にさらされるため壊れやすく、長く使っていると修繕作業が必要になることでしょう。
また、縁側を設置する時には費用もかかります。あまり縁側を活用しないようであれば、不要な出費となってしまうかもしれません。
『濡縁』『くれ縁』『ウッドデッキ』との違い
※写真はイメージ
『濡縁』と『くれ縁』にはそれぞれよさがあるため、使い方によってどちらを設置するのか判断するとよいでしょう。
下記では『濡縁』と『くれ縁』のそれぞれの魅力を解説します。また、『ウッドデッキ』との違いも見てみましょう。
外に設置されている『濡縁』
『濡縁』は、軒下に設置されている室外タイプの縁側。縁側と聞いてこちらを思い浮かべた人も多いのではないでしょうか。『濡縁』という名称は、名前の通り雨が降った時に濡れる縁側であることから、つけられたとされています。
外にいる時にひと休みしたり、ちょっとした荷物を置いたりするスペースとしても使えるでしょう。
室内に設置されている『くれ縁』
『くれ縁』は、室内に設置されている廊下の役割も担っている縁側です。室内と外の間にあるため、室内の気温を一定に保ちやすくする役割があります。
家の内側にあるため、寝転がっても服が汚れる心配がなく、人によっては『濡縁』よりも活用できる場面が多いでしょう。窓が付いているため、雨風で劣化することも少なく、メンテナンスも楽な傾向にあります。
『くれ縁』と廊下の違いは?
『くれ縁』がほかの部屋同士をつなぐ用途も担っていれば、廊下としての役割をはたしているといえるでしょう。ただ、くれ縁は廊下と違い、外に面した場所にあるため、植物を置いて日光浴させたり、洗濯物や野菜を干したりするスペースとしても活用できます。
広々と使える『ウッドデッキ』
縁側と似た設備に『ウッドデッキ』があります。『ウッドデッキ』とは、室内とつながるように作られた、地面から高さのある木製のテラスのこと。屋根が設置されていることの多い縁側とは違い、屋根が付いていないことが多いようです。
縁側は座れる程度の幅で作られることが多い一方で、『ウッドデッキ』はバーベキューをしたり、テーブルを設置したりできるようにスペースを広くとって作られることが多い傾向にあります。
縁側を作る時の注意点
※写真はイメージ
機能面でのメリットがあったり、家族や地域の人とのコミュニケーションの場にもなったりする縁側ですが、作る時に注意しておきたいこともいくつかあります。
縁側を作った後に「もっとしっかりと計画を立てて作ればよかった」といった後悔が残らないよう、次のことを意識しておきましょう。
縁側の寸法を測っておく
自分で縁側を作る時には、どれくらいのサイズのものを作るのかをきちんと決めておきましょう。事業者に設置をお願いする時にはお任せでも問題ありませんが、自分で室外タイプの縁側を作る場合には、事前に窓のサイズや庭の広さとのバランスを考える必要があります。
材料の寸法を間違えて小さくなってしまったり、必要以上に幅をとったりしてしまわないよう、きちんとサイズを測ってから作るようにしましょう。
防犯対策をする
家を建てる時に縁側を一緒に作るのであれば、防犯対策を立てておきましょう。縁側は、幅の広い窓の前に作ることが一般的です。そのため、外から家の中が見えやすくなってしまい、防犯対策をしておかないと空き巣被害にあう可能性が上がります。
外から中が見えないよう、視界を遮るためのすだれを設置したり、室内を見えにくくするミラーカーテンを選んだりするなど、しっかりと防犯対策をしましょう。
屋根や踏み石のサイズ
縁側に合った屋根や踏み石のサイズを調べておくことも大切です。室外に設置するタイプの縁側の場合、雨が降ってくると濡れてしまいます。
雨や風にさらされると壊れやすくなってしまうため、長く使いたい場合には、縁側が濡れないように屋根のサイズを広くとりましょう。
すでに住んでいる家に縁側を増設したいという場合には、サンシェードなどを使って雨を防ぐ方法もあります。縁側と地面までの距離が広い場合は、踏み石を設置すると上り下りが楽になりますよ。
靴を履いたり、立ち上がったりする時に楽な姿勢になるよう、自分の身体に合った高さの踏み石を選びましょう。
縁側のメンテナンスの仕方
※写真はイメージ
しっかりと作られていても、物はいつかは壊れます。定期的にメンテナンスを行えば、より長い間使うことができるでしょう。縁側にはどのようなメンテナンスが必要なのかを紹介します。
日頃のメンテナンスの仕方
室内タイプの縁側と、室外タイプの縁側では、メンテナンスの方法がわずかに違います。室内タイプの縁側であれば、普段の廊下掃除と同じように、掃除機やほうきで埃を取り除き、モップやぞうきんなどで清掃しましょう。
室外タイプの縁側の場合は、埃はあまりたまらないものの、蜘蛛の巣や蜂の巣、木の葉が付くことがあります。蜘蛛の巣などは放置しておくと巣が大きくなっていくので、見つけ次第取り除いてください。
室外タイプの縁側は、雨風で砂が付着するので、定期的にぞうきんなどで拭き掃除をしましょう。
増設・改修する時の注意点
家屋の設備を増設する時には、建築確認申請を国に提出しなければいけない場合があります。自治体や増設する設備の種類、サイズによって申請が必要か不必要なのかが変わるので、縁側を作る前にまず増設が可能なのか調べておきましょう。
改修を事業者にお願いする場合、工事が終了するまで数か月かかることがあります。そのような施工のための期間や、改修費用がどの程度かかるのかを事前に聞いておきましょう。
おしゃれな縁側にするポイント
※写真はイメージ
昔から日本で親しまれてきた縁側ですが、近年では洋風のデザインもあります。壁や室内のデザインに合った材質選んだり、L字型のウッドデッキ風のデザインにしてみると、おしゃれな雰囲気になることでしょう。
縁側を設置する部屋の窓際に、観葉植物やおしゃれなディスプレイを飾ってみてもよいかもしれません。
縁側の魅力を知っておしゃれな縁側にしよう!
室内の温度を保つ役割をはたしたり、人と人をつなぐ憩いのスペースにもなったりする縁側。縁側を設置することで、日常に新たな彩りが加わることでしょう。自分の生活に合っているか吟味して、素敵な縁側を生活に取り入れてみてください。
[文・構成/grape編集部]