干し柿の作り方とは?失敗しないためのポイントや風変わりレシピを紹介
公開: 更新:

※写真はイメージ
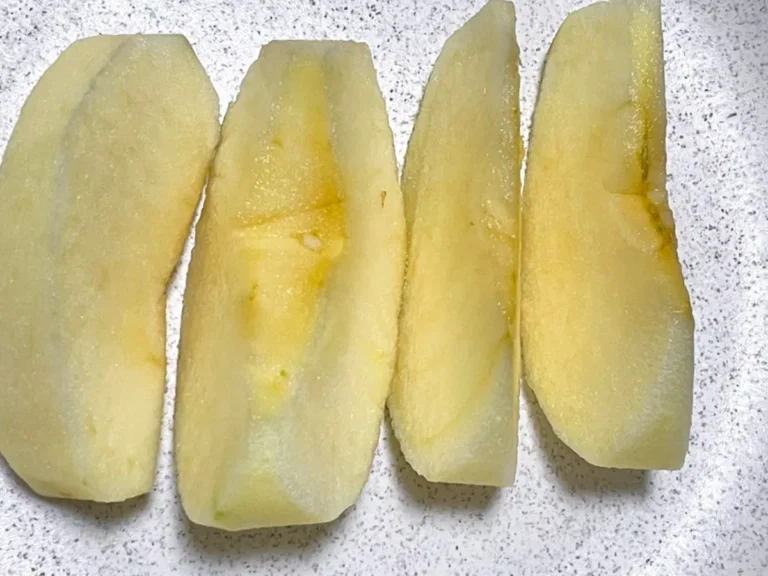
「リンゴが変色してしまった…」 あっという間にきれいな色に『戻す』驚きの裏技とは変色してしまったリンゴを元に戻す方法として、『オレンジジュース』に漬ける方法があるのはご存じでしょうか。 効果が気になった筆者が、実際に試してみました。

冷蔵庫に入れただけで? リンゴの甘さに「マジで?」「今すぐやる」【保存のコツ4選】リンゴや桃、梨など、果物は保存方法によって味わいや甘みが大きく変わります。冷蔵や常温の使い分け、新聞紙やポリ袋での保存など、ちょっとした工夫で鮮度を長く保つことが可能です。季節を問わず役立つ果物の保存のコツをまとめています。






「柿をたくさんもらったので、干し柿を作りたいけど、やり方が分からない」
「何回か作ったことはあるけれど、どうしてもカビが生えてしまう」
このように、干し柿の作り方で悩んでいる人もいるでしょう。
本記事では、基本の干し柿の作り方を解説します。さらに、失敗しないためのポイントや、干し柿を使った風変わりレシピもまとめました。
おいしい干し柿を作りたい人は、ぜひ参考にしてください。
干し柿の基本の作り方
※写真はイメージ
まずは、基本的な干し柿の作り方を紹介します。
干し柿は、糖分が多いとされる『渋柿』を使うことが一般的なようです。
干し柿を吊るす紐は荷造り用の紐で十分ですが、干し柿用の紐や干し柿を固定するクリップなどもあるのだとか。必要であれば活用するとよいでしょう。
1.皮を剥き、紐をつける
干し柿に使用する柿は、紐で縛りやすくするためヘタをT字の状態で残します。皮は、包丁やピーラーを使って剥きましょう。
柿の皮を剥いたら、ヘタに紐をつけます。
ぶら下げる場所によりますが、紐は60cm〜70cm程度の長さにして、両端に柿を縛りつけましょう。先ほど紹介した通り、T字の枝部分に縛りつけてください。
1本の紐に、柿を2個ずつ固定することになります。紐の両端に柿が固定されるため、紐の真ん中を頂点にするとぶら下げやすくなるでしょう。
2.湯で殺菌する
鍋に湯を沸かし、柿を熱湯で殺菌します。湯が沸いたら、柿を5秒ほど湯につけましょう。
柿を熱湯に入れることで殺菌効果が期待でき、カビが生えにくくなるといわれています。
3.柿を干す
柿を干す時は、柿同士がくっつかないように注意してください。
くっついてしまうと、カビの発生リスクが高くなったり、乾燥ムラができたりする可能性があります。
物干し竿や洗濯用ハンガーなど、固定できるものであれば何を使っても問題ありません。
干す場所はできるだけ日当たりがよい場所を選び、雨が降った時は室内に入れましょう。
4.柿を揉む
干してから目安として1週間ほどで、皮が固くなるそうです。
このタイミングで、柿の実が潰れない程度に指で優しく揉みます。柿を揉むことで、果肉の組織が破壊され熟成されやすくなるようです。
さらに、1週間後を目安に揉む作業を行います。できあがりが早くなるだけではなく、甘みが増しておいしい干し柿になるでしょう。
5.完成
干し柿の中身がトロトロになると完成です。
干し始めてから3週間程度が目安とされていますが、柿や気候によって異なるため、1か月程度かかる可能性もあります。
干す期間が長くなるほど食感が柔らかくなるようです。好みの食感に合わせて期間を調整しましょう。
干し柿作りで失敗しないためのポイント
※写真はイメージ
干し柿作りでは『カビが生える』『鳥や虫に食べられる』といった失敗が考えられるため、この2つの対策が重要です。
カビ予防として、熱湯に潜らせることを紹介しましたが、それ以外にも、干す時に焼酎を霧吹きで吹きかけることも効果が期待できるといわれています。
また、鳥や虫に食べられないための対策としては、干し柿用ネットの使用が有効でしょう。外敵から干し柿を守ってくれるため安心です。
このように、考えられる失敗を未然に防げるよう対策しておきましょう。
干し柿の作り方に関するよくある疑問と回答
※写真はイメージ
干し柿の作り方に関する、よくある疑問と回答をまとめました。
誰もが疑問に思う内容に目を通すことで、理解が深まるでしょう。ぜひ参考にしてください。
干し柿を作る時は渋柿か甘柿、どちらが向いている?
干し柿には『渋柿』が向いているようです。
渋柿はタンニンが含まれていることから渋みを感じるようですが、もともと甘柿よりも糖分が多いとされています。
干すことで、タンニンの渋みがなくなり、甘みが増すようです。
干し柿を作る時期はいつ頃がよい?
干し柿を作る時期は、11月頃がおすすめだといわれています。
天気が比較的安定しやすく、気温もそれほど高くありません。気温が15℃を下回る気候が干し柿の作る時期としてちょうどよいでしょう。
干し柿はどれくらい日持ちする?
できあがった干し柿を購入した場合は、常温保存で2日〜3日、冷蔵保存で約1週間、冷凍保存で6か月ほど日持ちするようです。
それぞれの保存するポイントを下記にまとめました。
以上の点に注意して、保存方法を選択しましょう。
柿や干し柿の保存方法や日持ちの期間については、下記記事で詳しく解説しています。
柿を長持ちさせる保存方法は?常温、冷蔵、冷凍、干し柿に分けてポイントを解説
柿を長持ちさせるためには、保存する際の置き方やひと手間に秘訣があります。また、鮮度を保つうえでヘタの処理も欠かせないポイントです。本記事では、柿や干し柿の、常温、冷蔵、冷凍での保存方法や日持ちの目安などを解説します。柿の保存方法が知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
干し柿を使った風変わりレシピ3選
※写真はイメージ
干し柿はそのまま食べても甘くておいしいですが、ひと手間加えると別の楽しみ方があるようです。
ここでは風変わりレシピを紹介するため、ぜひ試してみてください。
1.干し柿バター
まずは、干し柿バターの材料や作り方を紹介します。
【材料(2人分)】
干し柿を4個としていますが、食べたい分を好きなだけ使いましょう。バターも好みの量を使ってください。
【作り方】
バターは、カットした干し柿で挟める大きさにしてください。バターをカットする時は、手や包丁が滑りやすくなるため注意しましょう。
2.干し柿の白和え
干し柿の白和えの材料や作り方は、以下の通りです。
【材料(2人分)】
■調味料
豆腐1丁に対して、干し柿1個が目安です。干し柿の大きさにもよりますが、好みの量を入れましょう。
【作り方】
白和えに干し柿を加えることで、風変わりな白和えができあがります。干し柿の甘みも引き立ち、干し柿をそのまま食べる時とは異なる味わいが楽しめるでしょう。
3.干し柿と大根のなます
最後に、干し柿と大根のなますの材料と作り方を紹介します。
【材料(3〜4人分)】
■調味料
干し柿はアクセントとして使用するため、入れすぎに注意しましょう。
【作り方】
調味料を温める時は、火を入れすぎると酢が飛んでしまうため、温めすぎに注意してください。
干し柿は鳥や虫の被害に注意して日当たりのよいところに干そう
干し柿は、皮をむく、紐をつける、殺菌する、吊るす、揉むの工程を経て、3週間から1か月程度で完成するようです。
カビの発生、鳥や虫の被害に注意して、なるべく日当たりのよいところで干しましょう。
熱湯や焼酎による殺菌方法や、鳥除け虫除けネットなどを活用して、おいしい干し柿を作ってみてください。
[文・構成/grape編集部]