カステラの底に、なんでザラメが? 老舗菓子メーカーの回答に「そうだったのか!」
公開: 更新:

※写真はイメージ

真冬に上着を忘れた警察官 震えながらの説得に違反者が放った一言筆者が交番勤務をしていた頃、同い年で公私ともに仲のよい相棒がいました。警察官を辞めた今でも交流は続いています。 彼をひと言で表すなら『天然』。 早朝の事故対応に向かう車内で、昇る太陽を見ながら「昨日は満月だったんだね…」...
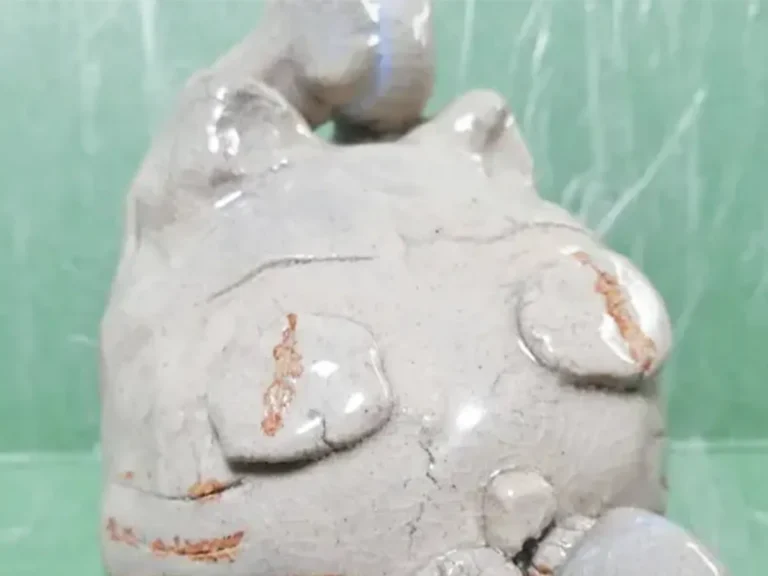
おでこにのせたはずが? 陶芸教室で作った猫の鈴、焼き上がりに吹き出す子供には、小さいうちから、できるだけいろいろな体験をさせてあげたいですよね。 ある日、筆者もそう考えて、息子たちと1日陶芸教室に行ってみました。 オーバーヘッドキックをする猫の陶鈴を作ったはずが? 陶芸教室では「猫の陶鈴...
- 取材協力
- 福砂屋


カステラの底にはたいてい砂糖の粒である、ザラメが付いていますよね。「あのザラメの食感が好き」という人もいるでしょう。
では、なぜカステラの底にはザラメが付いているのでしょうか。あえてなのか、それとも製造工程上、やむなく付くものなのか、不思議ですよね。
疑問を解決すべく、長崎県長崎市に本社のある『福砂屋』に取材しました。『福砂屋』は1624年創業、長崎カステラの伝統を受け継ぐ老舗の菓子メーカーです。
カステラの底に付いたザラメの正体とは?
『福砂屋』に話をうかがったところ、まずザラメが底に付いているのは長崎カステラの大きな特徴だそうです。
なぜザラメが底に付くかについては、「各社で製造方法は違いますので、あくまでも当社の場合はということでお答えします」とのこと。以下がザラメに関する回答です。
弊社では、ザラメ糖を生地に入れ撹拌(かくはん)します。撹拌する際に、ザラメ糖の角を擦り減らし、カステラの底に沈殿させます。
ザラメ糖を木枠に敷き詰め、そこに生地を流し込む製法とは異なり、程よい口当たりのザラメ糖になります。
『福砂屋』提供写真
『福砂屋』の製法では、ザラメ糖は自然に底に沈殿するので、カステラの底にザラメ糖が付くというわけです。
あくまでも『福砂屋』の場合ですが、口当たりのよさを追求することにより、長崎カステラの特徴である『底にザラメ糖があるカステラ』になったといいます。
さらに、『福砂屋』によると「カステラのザラメについて書かれた文献はない」とのこと。超老舗の『福砂屋』にないそうなので、カステラ製造におけるザラメについての資料を探し出すのは難しいでしょう。
詳細な歴史は分からないものの、今度カステラを食べる時には、ザラメが付いているかチェックしてみるのも楽しいかもしれませんね。
[文/高橋モータース@dcp・構成/grape編集部]