理想的な箸の長さとは?選ぶ際に着目したい5つのポイントも紹介
公開: 更新:

※写真はイメージ

真冬に上着を忘れた警察官 震えながらの説得に違反者が放った一言筆者が交番勤務をしていた頃、同い年で公私ともに仲のよい相棒がいました。警察官を辞めた今でも交流は続いています。 彼をひと言で表すなら『天然』。 早朝の事故対応に向かう車内で、昇る太陽を見ながら「昨日は満月だったんだね…」...
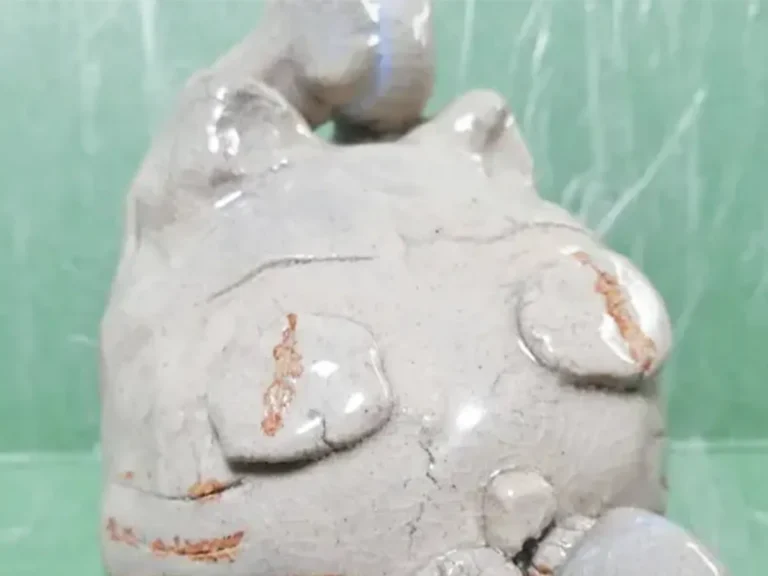
おでこにのせたはずが? 陶芸教室で作った猫の鈴、焼き上がりに吹き出す子供には、小さいうちから、できるだけいろいろな体験をさせてあげたいですよね。 ある日、筆者もそう考えて、息子たちと1日陶芸教室に行ってみました。 オーバーヘッドキックをする猫の陶鈴を作ったはずが? 陶芸教室では「猫の陶鈴...


理想的な箸の長さは、人によって異なります。同じ性別や身長でも、手の大きさによって適した長さは変わるため、実際に測ってから選ぶとよいでしょう。
ただし、使いやすい箸は長さだけでは決まりません。太さや形状など、理想の箸を探すには長さ以外にもチェックするべきポイントがあるのです。
本記事では、箸の長さの測り方と、子供から大人までの長さの目安をご紹介します。
さらに、箸選びの際に着目したい5つのポイントも解説しているため、自分に合った箸が欲しい人はぜひ参考にしてください。
理想の箸の長さと測り方
※写真はイメージ
一般的に、箸の理想的な長さは一咫半(ひとあたはん)といわれています。
一咫は、親指と人差し指の先端同士を結んだ直線の長さです。そこに半分の距離をプラスすれば手の大きさに合う箸の長さになります。
例えば一咫が13cmの場合、19.5cmほどの箸が使いやすいでしょう。12cmの場合は約18cm、14cmの人は約21cmになります。
測る距離は、親指と人差し指の先端どうしを結んだ直線の長さです。
【子供~大人】箸の長さの目安は?
※写真はイメージ
子供と大人では、理想的な箸の長さは異なります。
大人は先ほどの計算で最適な長さが分かりますが、子供の場合は年齢で選ぶのがよいでしょう。
子供も手の大きさによって変わりますが、おおよその長さは次に紹介する内容を参考にしてください。
子供
年齢別の箸の長さの目安は、以下の通りです。
ただし、同じ年齢でも個人差があるほか、販売店やメーカーによっては子供用の箸の長さが異なります。
正確な長さが知りたい場合は、メーカーが指定する方法で測定してから選ぶと失敗のリスクが減るでしょう。
また、年齢に適した箸を選ぶことも重要です。
例えば箸の使い始めは、正しい位置に手が添えられるリング付きや子供の手の大きさに合った握りやすいものが適しています。
握りにくい箸によって苦手意識を持ってしまうと、食事がストレスになり、箸を持つことを嫌がるかもしれません。
子供に食事の時間を楽しんでもらうためにも、子供に合った使いやすい箸を選んでみてください。
大人
大人の標準的な箸の長さは、以下の通りです。
販売店やメーカーによっては、手が小さい人向けに20.5cmもしくは23.0cmの箸も売られています。
標準的な長さの箸が手に馴染まない場合は、小さい人向けの箸も試してみましょう。
また、シンプルなデザインで、男女兼用で使える22.5cmの長さの箸もあります。好みやサイズ感を考慮して、選んでみてください。
長さ以外にも着目したい箸を選ぶ5つのポイント
※写真はイメージ
使いやすい箸は、手の大きさや箸の形状などによって異なります。例えば同じ身長であっても、体形や筋肉の付き方で着やすい服が異なるのと同じです。
理想の箸を見付けるには、次の5つのポイントを押さえておきましょう。
選ぶ時のポイントが分かれば、自然と手にフィットする箸が見付かるはずです。
手に馴染む太さ
手の大きさによって、しっかりと握れる箸の太さは異なります。
手の大きな人が細い箸を使ったり、反対に手の小さな人が太い箸を使ったりすれば、使いづらくストレスを感じるかもしれません。
手が大きい人はしっかりと握れる太い箸、手が小さい人や魚の骨を取るなど細かい箸使いが多い人は、細い箸が向いています。
理想の太さの箸を探すには、実際に店舗で握って確かめるのもおすすめです。
ネットショップにはさまざまな太さの箸が販売されていますが、店舗で実際に触って確かめることで納得して購入できるでしょう。
負担のない重さ
箸は素材によって重さが異なり、手への負担も変わります。軽すぎず重すぎず手に馴染み、長時間使用しても疲れにくい箸を選びましょう。
竹やヒノキは軽く、青黒檀(あおこくたん)や邪紋木(じゃもんぼく)は重い素材として知られています。
ネットショップで購入する際は、素材を確認することである程度の重さが想像できるでしょう。
箸の形状
箸には、丸いものや四角、八角、削りなど、さまざまな形状があります。
八角の箸は末広がりの縁起物として、結婚式の引き出物や土産物などで見たことがあるかもしれません。
箸の形状によっても、手の馴染みやすさは変わります。それぞれ握りやすさや力の伝えやすさが違うため、できれば実際に手に取って確かめるのがおすすめです。
それぞれの箸の形状と特徴は以下の表をご覧ください。
また、これらのほかにも五角、六角、七角の箸などもあります。
箸先の形状
全体の形状だけでなく、食べ物をつまむ先端部分の形も複数の種類と細さがあります。
「箸の形と箸先の形は同じでは」と思う人もいるでしょう。しかし、指で触れる部分と箸の先端の形状が必ずしも一致するわけではありません。
全体の形状が八角でも、箸の先端部分は四角の先角(さきかく)になっているなど、それぞれ別の形状になっている商品もあります。メニューに合わせて箸を変えるのもおすすめです。
例えばうどんを食べる時は先角、納豆ごはんを食べる時は先細、滑りやすいゆで卵があるおでんを食べる時は削りを使うなど、メニューによって箸を使い分けると、より食事を楽しめるでしょう。
それぞれの箸先の形状と特徴は以下の通りです。
仕上げの種類
箸には木目を生かし漆仕上げとした『木箸』や、染料や顔料を混ぜた色漆を何度も重ねて仕上げた『塗り箸』があります。
漆仕上げの木箸は、滑りにくく食材をつまみやすいのが特徴です。一方、漆を重ね塗りした塗り箸は口当たりがよく耐久性が高いものの、木箸と比べると滑りやすいでしょう。
また、塗り箸は漆仕上げの木箸と比べて、華やかな見た目を楽しめる点が大きな魅力です。デザイン性と使いやすさを両立させたい時は、滑り止め付きの塗り箸がよいでしょう。
なお、塗り箸には拭き漆やはけ目塗りなど、さまざまな技術が用いられています。
見た目の美しさや質感にも大きく影響するため、店舗や画像でしっかりと確認して好みの箸を探してください。
理想の長さは手の大きさや使うシーンなどで異なる
箸の長さの理想は、一咫半であることが分かりました。箸選びに悩んでいる人は、一度自身の手を測定してみるとよいでしょう。
使いやすい箸を選ぶためには太さや細さ、重さ、形状、仕上げの種類も確認しておくことが大切です。
年齢や手の大きさはもちろん、使うシーンや食事の内容によって使い分けるのもよいでしょう。自分の手に馴染む箸を選べば、より食事を楽しめるはずです。
[文・構成/grape編集部]