桜餅には道明寺と長命寺がある? 葉は食べる?<桜餅の関東・関西の違いと由来>
公開: 更新:


関東と関西でこんなに違う!卵焼き器、東型と西型の違いとその理由とは?卵焼きは日本人のソウルフードかもしれませんね。銅の卵焼き器には、東(あずま)型と西型があるのをご存じでしたか? その違いを、刃物や料理道具の専門店「日本橋木屋」さんにうかがってみました。 卵焼き器「東型」と「西型」の違い...

「何県民かバレるツイートしろ」に阪急電鉄が反応! 大阪人なら分かるらしい初めて見た人にとっては意味不明。大阪人、あるいは阪急電鉄沿線に住む人には認識できるようでが、あなたは分かりますか?



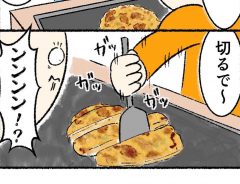


春めいてくると和菓子店に並ぶ「桜餅」。桜餅には実は2種類あるって知っていましたか?またその違いをご存知ですか?桃の節句でもおなじみの桜餅。違いをお子さんに伝えるのも楽しいかもしれません。今回は<桜餅の種類や違い>などについてご紹介します。
桜餅には道明寺と長命寺の2種類がある!?
色と香りで春を感じさせてくれる「桜餅」。桜の葉で餅を包む工夫は江戸時代に発案されたそうです。
桜餅は2種類あることをご存知ですか?
和菓子の桜餅には、「道明寺」と「長命寺」の2種類があります。桜餅と言われて思い浮かべるものは、お住まいの地域によって違うようです。
一般的に、
「道明寺」は、関西風・上方風の桜餅、「長命寺」は、関東風・江戸風の桜餅
という違いがあります。
また、桜餅といえば包んである「桜の葉を食べるか食べないか」、人によって好みが異なり、議論になることも多いもの。それについても最後に取り上げています。
まずは道明寺と長命寺の違いについてご紹介していきます。
<桜餅の道明寺>長命寺との違いとは? 元々武士の携帯食!?
関西風の桜餅が道明寺と呼ばれている理由は「道明寺粉」という材料を使用しているから。
道明寺粉とは、もち米を一度蒸して、乾燥させて粗く砕いた物。これを蒸して色付けしたもので餡を包んで作ります。お米の食感が残るつぶつぶとした皮が特徴です。
道明寺粉の歴史は古く、戦国時代に大阪の道明寺というお寺で作っていた保存食「干飯(ほしい)」が元になっているそう。長期保存できることから武士の携帯食として用いられ、水やお湯でふやかすなどして食べられていたとか。
次第に干飯を挽いて粉にしたものを、「道明寺粉」と呼ぶようになりました。それを使った餅が道明寺と呼ばれるようになったそうです。
<桜餅の長命寺>道明寺と違い小麦粉から作られる
関東風と言われている「長命寺」。皮の材料には小麦粉が使われています。長命寺は、小麦粉に水を混ぜて薄く焼いた皮で餡をくるんだもの。
なぜ「長命寺」と呼ばれているのでしょうか?由来は諸説ありますが、その一つをご紹介します。
江戸時代、東京の隅田川沿いにある長命寺では、川沿いの桜の木から落ちる葉の掃除に日々頭を悩ませていました。そこで桜の葉を塩漬けにし、それにお餅を包んだのが始まりだとか。「長命寺」というお寺で初めて作られたことから、この名前がついたそうです。
気になる道明寺と長命寺のカロリーは?
実際食べるときに気になるのが、カロリーですね。
日本食品標準成分表によると、
道明寺の100gあたりのカロリーは 200Kcal
長命寺の100gあたりのカロリーは 239Kcal
道明寺の方がややカロリーは控えめのようです。
ドーナッツ(375Kcal/100g)、ショートケーキ(327Kcal/100g)などの洋菓子に比べると、カロリー控えめなのは嬉しいですね。
参照:文部科学省「第2章 日本食品標準成分表」
気になる桜餅の「葉」みんな食べている?
道明寺・長命寺に共通しているのが、餅を包んでいる「塩漬けの桜の葉」の存在。桜の葉で包むことで、香り付けやお餅の乾燥を防ぐ目的があるんだとか。
葉は食べる人と食べない人で意見が分かれるようですが、正式な食べ方は決まっておらず、食べる・食べないはお好みによりけりだそう。
中には、香りだけ楽しんで、葉は剥がして中の餅部分だけを食べることを推奨している和菓子店もあるようです。購入先で尋ねてみるのもよいかもしれません。
おわりに
いかがでしたか?桜餅には道明寺と長命寺という2種があり、違いは材料でした。今では地域を問わず、道明寺も長命寺も手に入りやすくなっています。両方を用意して違いを味わってみるのも、いいかもしれませんね。
東京ガス「ウチコト」
東京ガス「ウチコト」は、家事(ウチのコト)で役立つちょっとしたコトをお届けしています。料理、洗濯、掃除、子育て、省エネ等、お家に役立つコト&コツが満載です。 ⇒http://tg-uchi.jp/
関連記事