お盆の迎え火や送り火はいつ、何時頃行えばいい? 意味ややり方は
公開: 更新:


盆踊りとは?行う意味や歴史、参加する時の3つのポイントを解説!盆踊りが何のために行われるのか分からず、参加するかどうかで悩んでいませんか。盆踊りとは、お盆に先祖の霊を迎え入れ、ともに過ごして見送る行事です。本記事では、盆踊りを行う理由や歴史、参加する時のポイントを解説します。

2025年の旧暦のお盆はいつ?旧盆や新盆との違いや特徴を解説旧暦のお盆は、7月盆や8月盆とは時期も内容も異なるようです。地域ならではの特徴が出ているので、内容を知るとお盆への理解を深めやすいでしょう。本記事では、旧暦のお盆の時期や特徴などについてご紹介します。


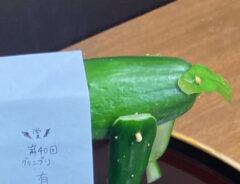



みなさんは、『迎え火』や『送り火』という言葉を聞いたことがありますか。
迎え火と送り火は、お盆の期間に行う伝統的な行事です。
この記事では、迎え火や送り火の意味、いつ・何時に行うのか、やり方についてなど、さまざまな情報をご紹介します。
そもそもお盆って何?
お盆は、正式には『盂蘭盆会(うらぼんえ)』といい、この時期には先祖や故人の霊が家に帰ってくると考えられています。
その霊を迎えて、供養する期間を『お盆』というのだそう。
お盆の時期は、地域によって異なります。詳細はこちらです。
お盆の迎え火・送り火の意味とは? いつ、何時頃に行う?
前述のとおり、お盆の期間に行う伝統的な行事として『迎え火』と『送り火』があります。
迎え火とは、先祖や故人の霊が迷わずに家に帰ってこられるように目印として焚く火のこと。
送り火は、お盆の期間に一緒に過ごした先祖や故人の霊が、あの世へ無事に帰れるようにと願いを込めて焚く火のことです。
この迎え火と送り火は、お盆の期間の何日に行うのでしょうか。
迎え火は『盆の入り』や『迎え盆』といわれる13日に、送り火は『盆の明け』や『送り盆』といわれる16日に行うのが一般的だそう。
また、迎え火と送り火を行う時間は、基本的に両方とも夕方とされています。
お盆の迎え火・送り火のやり方は?
迎え火と送り火のやり方は、基本的に同じだといいます。
用意するものは、おがらと焙烙(ほうろく)。
おがらは皮を剥いだ麻のことで、スーパーや花屋、ホームセンターなどで購入できるそう。
焙烙は素焼きの平皿のことで、仏壇店などで購入できるといいます。
インターネットで検索すると、迎え火・送り火セットも売られているので、そちらを使用するのもいいでしょう。
迎え火と送り火を行う場所は、家の玄関先や門口など。その場所で、焙烙に短く折ったおがらを積み重ねて燃やすのが一般的なやり方だそうです。
中には、マンションやアパートに住んでいて、迎え火と送り火が焚けない人もいるでしょう。
その場合は、盆提灯(ぼんぢょうちん)を飾るのだそう。盆提灯は、迎え火・送り火と同じような役割があるといいます。
盆提灯
お盆に行う迎え火や送り火についてご紹介しました。
一番大切なのは、先祖や故人を大切に思う気持ちです。お盆の期間は、自分たちのできる範囲で供養しましょう。
[文・構成/grape編集部]