『法事』とは? 法要との違いなど詳しく解説!
公開: 更新:

※写真はイメージ

真冬に上着を忘れた警察官 震えながらの説得に違反者が放った一言筆者が交番勤務をしていた頃、同い年で公私ともに仲のよい相棒がいました。警察官を辞めた今でも交流は続いています。 彼をひと言で表すなら『天然』。 早朝の事故対応に向かう車内で、昇る太陽を見ながら「昨日は満月だったんだね…」...
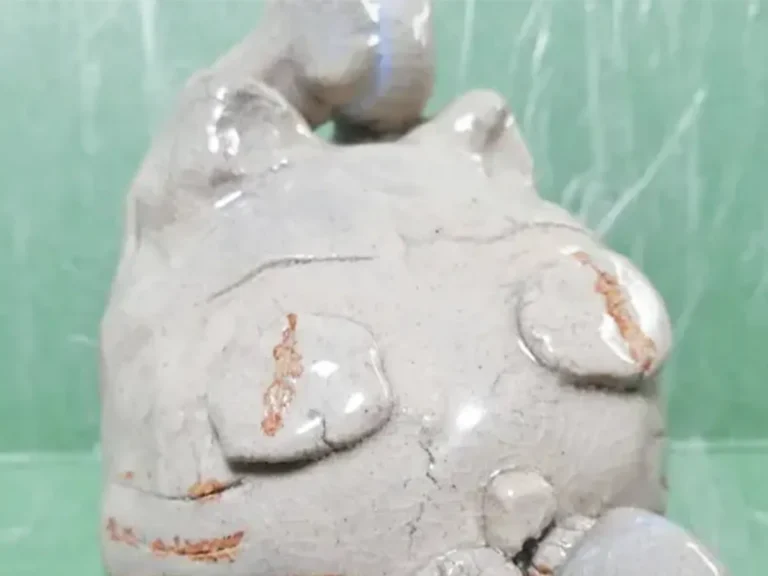
おでこにのせたはずが? 陶芸教室で作った猫の鈴、焼き上がりに吹き出す子供には、小さいうちから、できるだけいろいろな体験をさせてあげたいですよね。 ある日、筆者もそう考えて、息子たちと1日陶芸教室に行ってみました。 オーバーヘッドキックをする猫の陶鈴を作ったはずが? 陶芸教室では「猫の陶鈴...


法事は、亡くなった大切な故人を供養するためにおこなわれるもので、法要と呼ばれることもあります。
しかし『法事』と『法要』は、それぞれ別のものだということをご存じでしょうか。
この記事では、法事と法要の違いについてや、法事の流れやマナーなどを解説していきます。
今後の法事に備えたい人や、法事について詳しく知りたい人はぜひ参考にしてください。
法事とは?
※写真はイメージ
まずは、法事がどのようなものなのかを見てみましょう。
法要との違いや、法要の種類についても細かく解説するので、詳しく知りたい人は参考にしてみてください。
『法事』と『法要』の違い
※写真はイメージ
お通夜や葬儀などを指して『法事』や『法要』など、人によって呼び方はさまざまでしょう。実は、この2つが意味するのはそれぞれ別のものです。
『法要』は亡くなった人の供養をするために、僧侶がお教を読んだり、焼香をしたりする儀式のことをいいます。
一方『法事』は、『法要』やその後の食事などに留まらず、お盆や彼岸供養なども含めた、行事全体を指す言葉です。
よって、『法事』の中に『法要』が含まれるということになります。
法要の種類
※写真はイメージ
亡くなった人を供養するためにおこなう法要には、『忌日法要』と『年忌法要』の2種類があります。
『忌日法要』と『年忌法要』は、亡くなってから1年が経つタイミングでおこなわれる一周忌が分かれ目です。
ここからは『忌日法要』と『年季法要』について一つずつ見ていきましょう。
忌日法要
忌日法要は、故人が亡くなった日から7日ごとにおこなう法要のことで、『四十九日(しじゅうくにち)』と呼ばれる七七日まで継続するのが特徴です。
「定期的に法要をおこなうことによって、故人を極楽まで案内する」と考えられており、信仰を深めつつ、故人に感謝を伝えるという目的があります。
初七日(7日目)
故人が亡くなってから最初におこなうのが、初七日(しょなのか、しょなぬか)の法要です。
基本的には亡くなってから7日後におこなわれますが、近年では『繰り上げ法要』として、葬儀当日におこなう場合も増えています。
二七日(14日目)
故人が亡くなってから14日後におこなわれるのが、二七日(ふたなのか)の法要です。
故人の生前の罪を少しでも軽くするために、現世から故人について祈るのが目的だといわれています。
三七日(21日目)
故人が亡くなってから21日目におこなわれるのが、三七日(みなのか)の法要です。
二七日までは親族を始め、友人なども参列して法要がおこなわれますが、三七日以降は規模が縮小し、親族のみとなります。
四七日(28日目)
故人が亡くなってから28日目におこなわれる法要が四七日(よなぬか、ししちにち)で、内容は三十七日と同様です。
場合によっては、省略されることもあります。
五七日(35日目)
故人が亡くなってから35日目に執りおこなわれるのが五七日(いつなのか)法要で、内容は三七日や四七日とあまり変わりません。
地域によっては、遺族が喪に服する期間を終える忌明けの日とされる場合もあります。
六七日(42日目)
亡くなってから42日後におこなわれる法要が、六七日(むなのか、むなぬか)です。
法要の内容は三七日や五七日と変わらず、親族のみで執りおこなわれます。
七七日(49日目)
故人が亡くなってから49日目におこなわれるのが七七日(しちしちにち、なななぬか)の法要です。仏教用語で『満中陰(まんちゅういん)』と呼ばれます。
『四十九日』とも呼ばれ、法要には親族一同のほか、友人も参列することが可能です。
四十九日を経て忌明けとすることが多く、法要が終わった後は食事会などを開き、悲しい気持ちを切り替えるタイミングとしても知られています。
百箇日(百日目)
故人が亡くなってから百日目におこなわれる法要が百箇日(ひゃっかにち)です。別名として『卒哭忌(そっこくき)』とも呼ばれます。
四十九日が忌明け日とされる場合が多いため一般的には知られていませんが、遺族が大切な人を亡くした悲しみから解放されるために執りおこなう法要です。
年忌法要
年忌法要は数年おきのペースで、故人の命日前後におこなわれるのが特徴です。
長い年月をかけてゆっくりと、故人に冥福を祈り続けるための法要であり、一周忌以降は『◯回忌』と呼び名が変わります。
一周忌
故人が亡くなってから1年後におこなわれるのが、一周忌です。
親族一同に加え、親しかった友人なども参列し、お焼香をおこなった後は、主に食事会などが開かれます。
一周忌は、年忌法要の中でも重要な法要です。参列する際は正しい知識やマナーなどを覚えておきましょう。
三回忌
故人が亡くなってから2年後におこなわれる法要が、三回忌です。
節目の1つとして考えられることが多い一方で、場合によっては三回忌以降の法要をおこなわないことも。
一周忌と同じく、親族一同や友人も参列して法要をおこないます。
七回忌
七回忌は、故人が亡くなってから6年後におこなわれる法要です。
三回忌以降は法要の規模が小さくなり、七回忌以降は基本的に親族のみで法要がおこなわれます。
十三回忌
十三回忌は、故人が亡くなってから12年が経過した頃におこなわれます。
家庭にもよりますが、親族のみで執りおこなわれる場合がほとんどです。
十七回忌
故人が亡くなってから16年が経過した時におこなわれる法要が、十七回忌です。
十三回忌以前の法要と同じく、基本的には親族のみでおこなわれ、場合によっては食事会などが開かれることもあります。
二十三回忌
二十三回忌は、故人が亡くなってから22年が経過した時におこなわれます。
そもそも法要自体をおこなわないケースも多く、親族一同が集まって食事をするだけの場合もあるようです。
二十七回忌
二十七回忌は、故人が亡くなってから26年が経過した時におこなわれます。
二十三回忌と同様に、法要をおこなわないことも多いようです。
三十三回忌
三十三回忌は、故人が亡くなってから32年が経過した時におこなわれます。
僧侶を招き、親族一同で集まって法要をおこないますが、一周忌と比べて小規模におこなうのが主流です。
亡くなってから32年も経つと、故人のことを知らない親族も多くなるため『弔い上げ(とむらいあげ)』とし、法要自体をおこなわないこともあります。
三十七回忌
三十七回忌は、故人を亡くなってから36年が経過した時におこなわれます。
親族を集めて法要をおこなう場合もありますが、三十三回忌を弔い上げとした場合は、法要そのものがおこなわれません。
四十三回忌
四十三回忌は、故人が亡くなってから42年が経過した時におこなわれます。
法要は小規模で、三十三回忌で弔い上げとした場合は、法要自体がおこなわれません。
四十七回忌
故人が亡くなってから46年が経過すると、四十七回忌となります。
四三回忌と同じく法要は小規模で、三十三回忌で弔い上げとした場合は、法要自体がおこなわれません。
五十回忌
故人が亡くなって49年後に迎えるのが、五十回忌です。
三十三回忌を弔い上げとしなかった場合は、五十回忌をもって弔い上げとなります。
百回忌
故人が亡くなって99年が経過すると、百回忌のタイミングとなります。
ただし、ほとんどの宗派では三十三回忌や五十回忌を弔い上げとするため、百回忌をおこなわないことも珍しくありません。
法事の準備の流れは?
※写真はイメージ
身内の人が亡くなって喪主を務めることになったら、法事をおこなうために準備する必要があります。
不慣れなだけでなく、身近な人を亡くした悲しさから慌てて手配してしまうと、トラブルにつながる場合もあるかもしれません。
スムースに法事を執りおこない、故人ときちんとお別れをするために、法事を準備する際の大まかな流れを押さえておきましょう。
この項では、法事の準備や当日の流れについて解説します。参列する際のマナーについても見ていくので、参考にしてみてください。
法事の準備
まずは、法要をおこなう会場と日時を決定します。
基本的には、親族や故人の友人が無理せず来ることができる場所で、土曜日や日曜日におこなうのが一般的でしょう。
会場と日時が決まったら、親族や故人の友人に案内状を送ります。最後に、食事と引き出物の手配を済ませたら準備完了です。
法事当日の流れ
法事当日は親族一同や故人の友人を会場で迎え、参列者がそろったら法要を始めましょう。
僧侶と喪主が挨拶をおこない、その後は僧侶による読経と、親族と故人の友人が焼香をします。
焼香の後は僧侶による法話を聞き、喪主が終わりの挨拶をしたら法要は終わりです。
法要の後は、事前に予約していた店などで会食をおこない、引き出物を渡します。これで法事は終了です。
法事に参列する時のマナー
※写真はイメージ
法事にはマナーがあります。法事に参列する際は、マナーを確認しましょう。
亡くなった故人はもちろん、身内や故人の友人に対して失礼にならないように注意が必要です。
ここからは、法事のマナーについて一つひとつ解説します。法事に参列する際の参考にしてみてください。
お布施の書き方と渡し方
法事をおこなう際、僧侶に感謝の気持ちを伝えるためとして、お布施(ふせ)を渡す必要があります。お布施は奉書紙(ほうしょし)という和紙に包すのがマナーです。
奉書紙には、黒の毛筆で文を書きましょう。最初に奉書紙の上側中央当たりに『御布施』と書き、その下に故人のフルネームを書きます。
故人のフルネームを各箇所は、場合によっては『◯◯家』といった形で書いてもよいでしょう。奉書紙にお金を包んだら、読経が終わった後に渡してください。
お布施の相場は、法要の種類によって異なります。葬儀や告別式の場合は宗派や内容に応じてさまざまですが、四十九日や一周忌などの法要は1~5万円ほどと考えるとよいでしょう。
法事に参列する時の服装マナー
※写真はイメージ
法事にそぐわない服装で参加すると、故人に対する供養の気持ちが伝わらなくなってしまうこともあります。
参列する際は、マナーに合わせた服装を心がけましょう。
男性の服装
男性の場合は、準喪服または略喪服を着用するのが一般的です。
上下黒のスーツに白い無地のワイシャツを用意し、光沢のない黒ネクタイを着用しましょう。
靴下や靴のほか、ベルトなども黒いものを着用し、髪型も清潔感を意識して整えるようにしてください。
女性の服装
女性の場合は、黒いフォーマルスーツやワンピースなどを用意してください。
スカートの丈はヒザが隠れるほどのものを選び、薄手の黒いストッキングを着用しましょう。
男性と同じく、コーディネートは基本的に黒色でそろえ、ナチュラルメイクにしたり、ネイルを落としたりするなど、派手なものは避けてください。
清潔感のある髪型に整え、髪が長い場合はヘアゴムなどでまとめるとよいでしょう。
法事に参列する時はマナーを守って気持ちを伝えよう
法事は、亡くなった人を供養するためにおこなう大切な儀式です。参列する際はマナーを守りましょう。
人によっては、身内が亡くなったショックから、法要や法事の準備が満足にできないこともあるかもしれません。
しかし、故人を供養するために心を切り替え、滞りなく法事を済ませることも大切です。家族や親族と協力しながら、法事を執りおこなうようにしましょう。
[文・構成/grape編集部]