平安時代の平均寿命は何歳?貴族と庶民の一生や寿命が短い理由を解説
公開: 更新:

※写真はイメージ

真冬に上着を忘れた警察官 震えながらの説得に違反者が放った一言筆者が交番勤務をしていた頃、同い年で公私ともに仲のよい相棒がいました。警察官を辞めた今でも交流は続いています。 彼をひと言で表すなら『天然』。 早朝の事故対応に向かう車内で、昇る太陽を見ながら「昨日は満月だったんだね…」...
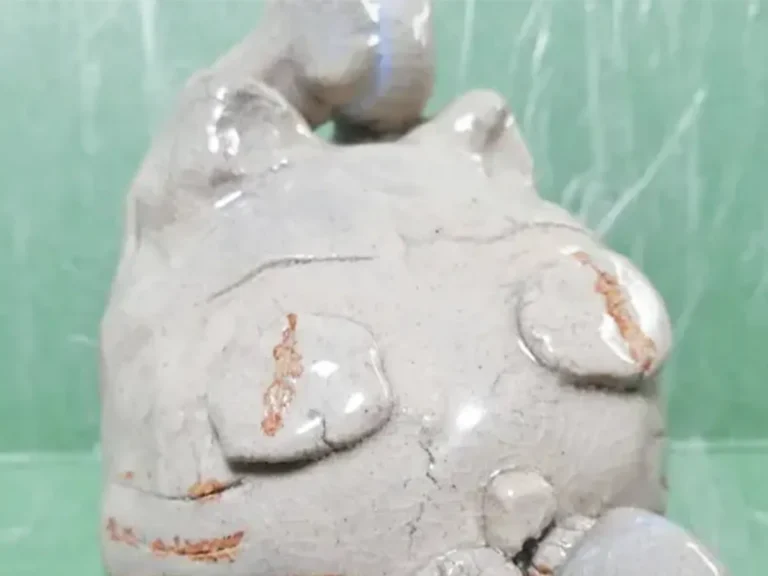
おでこにのせたはずが? 陶芸教室で作った猫の鈴、焼き上がりに吹き出す子供には、小さいうちから、できるだけいろいろな体験をさせてあげたいですよね。 ある日、筆者もそう考えて、息子たちと1日陶芸教室に行ってみました。 オーバーヘッドキックをする猫の陶鈴を作ったはずが? 陶芸教室では「猫の陶鈴...


大河ドラマなどを観ていて、「平安時代の平均寿命は何歳だったのだろう」と気になった経験がある人は少なからずいるでしょう。
『平安時代の貴族の平均寿命は30歳前後』という説がありますが、庶民の場合はさらに短かったようです。平安時代の平均寿命が短い理由は、医療が未発達で栄養が偏っていたためだと考えられています。
本記事では、平安時代の平均寿命についてまとめました。平安時代の平均寿命が短い理由や、平安貴族の一生、人生の節目で行う儀式についても解説します。
歴史に関心がある人は、ぜひ参考にしてください。
平安時代の平均寿命
※写真はイメージ
平安時代の平均寿命は、貴族と庶民では異なります。それぞれの平均寿命について、以下にまとめました。
平安時代の貴族の平均寿命
平安時代の貴族の平均寿命は、30歳前後だったと考えられています。平均寿命については諸説あるものの、男性が33歳、女性が27歳くらいといわれているようです。
平安時代には、40歳になると『四十賀(しじゅうのが)』の儀式で長寿を祝いました。その後も10年ごとの節目のたびに長寿を祝いますが、これらの総称を『算賀(さんが)』といいます。
ただし、当時書かれたと思われる日記などからは、60歳を祝う『還暦』の記録がほとんど確認できないのだそうです。これは、当時60歳まで生きた人が少なかったためかもしれません。
また、現代では女性のほうが長生きする傾向にありますが、平安時代には男性のほうが長生きだったようです。
平安時代の庶民の平均寿命
平安時代の庶民は、貴族に比べて平均寿命が短かったと考えられます。
『平安時代の平均寿命』に関する資料は、身分の高い貴族について研究したものがほとんどのため、実際のところ庶民の寿命については不明です。
専門家の中には「平安時代の庶民の平均寿命は、現代人の半分以下の年齢だった」という人もいます。
平安時代の平均寿命が短い理由
※写真はイメージ
平安時代は、庶民、貴族ともに、あまり長生きができなかったようです。
平安時代の平均寿命が短かった理由について解説します。
栄養が偏っていたため
平安時代の平均寿命が短いのは『栄養の偏り』が原因だといわれています。
当時権力を持っていた貴族は、豪華な食事をしながら、室内中心の生活を送っていたようです。
豪華ながらも栄養が偏った食事であったことに加え、運動不足による不摂生のため、貴族でも長生きできなかったと考えられています。
また、貴族の女性は、食べるという行為を『下品』だと考えていました。そのため、身分の高い女性ほど、極力食事を控えなければならなかったようです。
その一方で、庶民は素朴な生活を強いられ、生きるだけで精一杯でした。そのうえ、飢饉(ききん)に苦しめられることも少なくなかったようです。
また、結核や脚気(かっけ)などの病気を患い、そのまま短い生涯となるケースも多かったと考えられています。
平安時代の庶民が長生きできなかった理由は、主に病気によるものですが、そもそもの原因は栄養不足でしょう。平安時代には、栄養失調で命を落とすことが少なくなかったようです。
医療が未発達だったため
平安時代の医療が未発達だったことも、短命の理由だと考えられます。
当時は、悪霊が病気をもたらすと考えられていました。そのため、貴族が病気になった場合は、生霊や死霊を祓うために陰陽師の祈祷や僧侶の読経に頼っていたようです。
平安時代には、感染症が流行するたびに、老若男女問わず多くの人が命を落としたという記録が残っています。特に、乳幼児の死亡率は高かったようです。
また、出産をきっかけに亡くなってしまう女性も多かったため、女性が短命だったのも納得できるでしょう。
さらに当時は、庶民が利用できる医療機関が少なく、薬の入手も困難でした。
貴族、庶民ともに平安時代の平均寿命が短い理由は、医療が未発達だったためでしょう。
平安貴族は『人生の節目』で儀式を実施していた
※写真はイメージ
平安時代の平均寿命は、現代人の半分以下の年齢のため『何歳くらいで結婚していたのか』や『どのような一生を送っていたのか』が気になるところです。
当時の人々の一生については、人生の節目に行っていた儀式を知ることで把握できます。
当時は貴族が政権を握っており、さまざまな儀式によって国家の安泰を願いました。そのため、私生活でも人生の節目ごとに『健康を祝い災いを避けるための儀式』を行っていたようです。
平安時代の貴族の一生
※写真はイメージ
寿命が短かったとされる平安時代ですが、貴族は一生のうちにさまざまな儀式を行いました。
ここからは、節目に行う儀式とともに平安貴族の一生について解説します。
平安貴族の誕生から幼児期まで
平安時代の貴族は血や死を恐れていたため、お産を嫌っており『産屋(うぶや)』に移動して行いました。
誕生後の儀式は、下記の通りです。
誕生後は、吉日に産湯の儀式『御湯殿(おゆどの)』を行い、9日目までの奇数の日に一度、祝宴の『産養(うぶやしない)』を開催しました。
その後は、お食い初めの由来になった『五十日祝(いかのいわい)』と『百日祝(ももかのいわい)』を行ったようです。
男女ともに幼児期は髪を剃り落としますが、3歳になると髪を伸ばし始めるために『髪置の儀(かみおきのぎ)』を行います。
5~7歳頃には『袴着の儀(はかまぎのぎ)』を行いました。袴着の儀は『着袴の儀(ちゃっこのぎ)』とも呼ばれていたようです。
『髪置の儀』や『袴着の儀』は、七五三の由来となっています。
平安貴族の成人期から結婚まで
平安時代の貴族は、成人すると結婚できる年齢として認められ、以下の儀式を行いました。
儀式をきっかけに、男子は冠をかぶり始め、女子は巻きスカートのような裳を着用し始めたようです。女性の中には、お歯黒や引き眉などの化粧を始める人もいます。
平安時代は、婚姻が認められる年齢も早かったようです。
男女の出会いは、男性側が『魅力的な異性がいる』という噂を聞き、女性の姿や生活を覗き見て手紙を送るのが主流でした。
文面や内容が女性の好みに合っていれば文通を開始し、何度かやりとりを経て男性が訪問することになります。
平安時代の貴族は、上手に和歌が作れたり楽器を演奏できたりすることで、異性を惹きつけていました。
男性が女性宅に3日通い続けて夜をともにすると、婚姻が成立します。その後『所露(ところあらわし)』という披露宴が行われ、正式な結婚に至りました。
貴族の結婚生活ですが、平安時代の前期は夫婦が別居し、夫が妻の家を訪ねる『妻問婚(つまどいこん)』が主流でした。
平安時代中期になると、男性が女性の家に婿に入る『婿入婚(むこいりこん)』が増えていきます。
さらに平安時代後期からは、妻が夫の家に入る『嫁入婚(よめいりこん)』が多く見られるようになりました。
平安貴族の高齢期から終活期まで
平安時代は、40歳以降になると高齢期に該当します。紫式部が老眼を気にし始めたのも、40歳頃といわれているようです。
平安時代に50歳まで生きられた人は、わずか10%しかいなかったのだとか。
平安時代中期になると、貴族が、出世への道や就いたポストを捨てて、出家するケースが増えました。
一見華やかな貴族の暮らしですが、出世や恋愛に対する『欲望』や『嫉妬』に苦しむことが多かったようです。苦しみから逃れて、余生を静かに暮らしたいという気持ちが、出家につながったのでしょう。
一方で『出世したい』『高いポストが欲しい』などの欲望を持つ貴族もいたようです。平安時代に出世するためには、年齢を重ねる必要がありました。
歌人の藤原俊成は、91歳で亡くなるまで創作を続けたといわれています。91歳といえば現代でも長寿とされる年齢ですが、創作にかける気持ちが、長生きにつながったのかもしれません。
なお、出家については、極楽浄土を願うための終活として行うこともあったようです。
死後は、貴族の場合は火葬、庶民は土葬が一般的だったとされています。ただし、一条天皇の最初の后である藤原定子は、庶民と同じように土葬されています。
平安時代の貴族の平均寿命は約30歳!庶民よりも長寿な傾向にあった
平安時代の平均寿命は、貴族の場合は30歳前後ですが、庶民はさらに短かったようです。平均寿命が短い理由は『栄養の偏り』と『医療が未発達だったため』だといわれています。
平安時代には、現在の『思春期』に該当する時期は『結婚適齢期』に達していました。現代と比較すると、成人する年齢も早く、短い一生だったようです。
一方で、平安時代の貴族の中には、90代まで生きた人物も存在します。
平安時代には、身分によって差があったようですが、平均すると早世な傾向にありました。
平安時代の平均寿命と貴族の一生を知り、歴史への理解をさらに深めましょう。
[文・構成/grape編集部]