歩幅の平均はどれくらい?身長、性別、年齢ごとの平均や改善方法も紹介
公開: 更新:

※写真はイメージ

真冬に上着を忘れた警察官 震えながらの説得に違反者が放った一言筆者が交番勤務をしていた頃、同い年で公私ともに仲のよい相棒がいました。警察官を辞めた今でも交流は続いています。 彼をひと言で表すなら『天然』。 早朝の事故対応に向かう車内で、昇る太陽を見ながら「昨日は満月だったんだね…」...
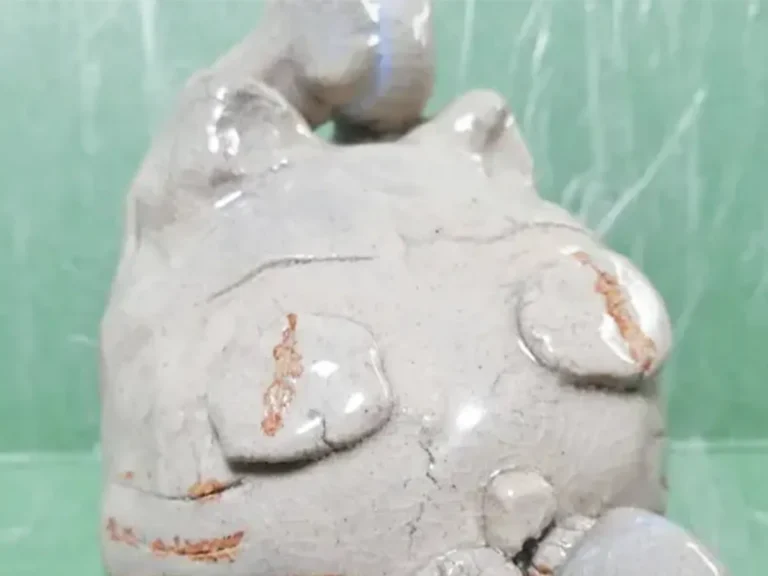
おでこにのせたはずが? 陶芸教室で作った猫の鈴、焼き上がりに吹き出す子供には、小さいうちから、できるだけいろいろな体験をさせてあげたいですよね。 ある日、筆者もそう考えて、息子たちと1日陶芸教室に行ってみました。 オーバーヘッドキックをする猫の陶鈴を作ったはずが? 陶芸教室では「猫の陶鈴...


歩幅の平均は、年齢や身長、性別によって異なります。
歩幅は、健康状態の目安にもなることをご存じでしょうか。歩幅が平均よりも狭い場合は、運動不足なだけではなく、老化のサインかもしれません。
本記事では、歩幅の平均値や測り方、歩幅と健康との深い関係、歩幅を広げる方法を紹介します。効果的なウォーキングの方法も解説しますので、健康が気になる人は、ぜひ参考にしてください。
歩幅の平均を年齢、身長、性別ごとに紹介
※写真はイメージ
歩幅は、年齢や体格、性別によって差があります。ここでは平均的な歩幅を確認しながら、身長、年齢、性別による違いを見ていきましょう。
歩幅の平均
歩幅とは、一般的に『片足のつま先から、反対側のつま先までの距離』を指します。
歩幅は個人差が大きいため、明確な平均値を出すのは難しいものの、いくつかの調査データから目安を知ることは可能です。歩幅の平均値は、成人男性で65〜78cm、成人女性で60〜70cmとされています。
また、歩幅は、高齢になるにつれて徐々に狭くなるようです。70代になると、男性は65cm前後、女性は55〜60cm程になるといわれています。
ただし、年齢や身長、性別によって差が出るため、あくまでも参考値としてとらえましょう。
身長ごとの平均歩幅
歩幅は、身長とも深く関係しており、一般的に『身長が高いほど歩幅も広くなる』といわれているようです。
理想的な歩幅の目安は『身長×0.37〜0.45』の式で計算できます。普通の歩幅の場合は『身長×0.37』、大きめの歩幅で歩く場合は『身長×0.45』が目安です。
上記の式で計算した『大きい歩幅』の目安は、身長150cmで67.5cm、160cmで72cm、170cmで76.5cm、180cmで81cmとなります。ウォーキング時の目安にしてください。
年齢ごとの平均歩幅
年齢が上がるにつれて、歩幅は徐々に狭くなるといわれています。
これは、加齢によって筋力や関節の柔軟性、バランス感覚が低下するためです。歩く速度がゆるやかになるにつれ、歩幅も狭まる傾向にあります。
また、加齢に伴う歩幅の変化と、健康状態の関連性を指摘する報告もあるようです。歩幅の狭さが、体力や身体機能に影響を与えるとされています。
この説は、すべての人に当てはまるわけではありません。生活習慣や運動習慣による個人差も大きいようです。
性別ごとの平均歩幅
歩幅は性別によっても違いがあり、男性のほうが、女性よりも広い傾向にあります。
その理由は、身長差によるものです。女性は男性よりも平均身長が低いため、歩幅が狭くなると考えられています。
筋肉量の差も多少は影響するかもしれませんが、身長差のほうがより深く関係しているようです。男女で歩幅の平均に差があるのは、体格差によるものと考えてもよいでしょう。
自分の歩幅を測ってみよう
※写真はイメージ
自分の歩幅がどれくらいなのかが気になる人も、いらっしゃるかもしれません。ここからは、簡単にできる歩幅の測り方と、正確に測るためのポイントを紹介します。
歩幅の簡単な測り方
歩幅とは『片足のつま先から、反対側の足のつま先までの距離』のことです。歩幅を調べる際には、10歩歩いて距離を測り、それを10で割ると1歩分の歩幅が分かります。特別な道具も必要なく、試しやすい方法です。
屋外で測る場合は、横断歩道や点字ブロックの幅を目安にするとよいでしょう。横断歩道の白線は約45cm、点字ブロックは1枚あたり約30cmの幅があるため、これらを使うと、おおよその歩幅を計測可能です。
横断歩道を基準にする場合は、白線の前に片足を置き、もう片足で完全にまたげれば『45cm+自分の足のサイズ=歩幅』になります。
なお、点字ブロックや横断歩道を基準にする際には、近くに人や車がいないこと、本来の利用者の妨げにならないことを確認してから行いましょう。
歩幅を正確に測るためのポイント
歩幅を正しく計測するうえで大切なのは、無理のない自然な状態で歩くことです。大股歩きは避け、普段通りの歩き方を心がけましょう。
自治体の公共施設などで、歩幅を測る専用のシートを利用できる場合もあるようです。また、スマートフォンの機能やアプリでも計測できます。
歩幅の狭さは老化の始まり?
※写真はイメージ
歩幅が狭くなる原因の1つとして、加齢や身体の衰えが影響しており、時には見過ごせないサインになることもあるようです。歩幅の狭さが脳や身体におよぼす影響について、見ていきましょう。
歩幅が狭いことによる身体への影響
歩幅が狭くなる原因の1つに、歩く力の衰えがあります。足の筋力やバランス感覚の低下により、しっかりと前に踏み出すことが難しくなり、結果として一歩の距離が短くなる傾向にあるようです。
こうした状態が続くと、つまずきやすくなり、転倒の危険性が高くなるでしょう。日常の動作がゆっくりしたものになり、活動量の低下にもつながります。
歩幅の変化は、身体の健康や認知機能との関わりがあると考えられてもおり、見逃せない指標の1つです。
『歩幅の狭さは老化のサイン』といわれる理由
歩幅が狭くなる理由として、平衡感覚の低下や筋力の衰え、心肺機能の変化などが関わっているとされています。
関節の柔軟性が低下することや、視力と脳の働きが変化することも、歩行に影響を与える要因です。これらの要因により、小さな歩幅で歩く『ちょこちょこ歩き』が目立つようになります。
歩幅の変化は、加齢による身体のサインとして気付きやすいポイントの1つといえるでしょう。
『認知機能、筋力、代謝』と歩幅との関係
歩幅が狭くなると、足をしっかり上げて歩くことが難しくなり『すり足』に近い歩き方になるといわれています。
また、歩幅の狭さと、認知機能が関連しているという調査もあるようです。歩幅が大きい人と小さい人を比較すると、小さい人のほうが『認知機能の低下率や、認知症を発症する可能性が2〜3倍以上高くなる』傾向にあるのだとか。
そのほか、代謝や全身の筋力と歩幅にも関係があるといわれています。自分や家族の歩幅の変化に気付いたら、身体の状態を見直してみましょう。
健康のために歩幅を意識しよう
※写真はイメージ
歩幅は年齢や体力によって変化しますが『少し広め』を意識することで、身体によい影響を与えるようです。歩幅を広げることで期待できる点と、無理なく改善する方法について紹介します。
歩幅を広げることで期待できる、健康面のメリット
普段より少し広めの歩幅で歩くと、下半身の筋力アップや、身体を引き締める効果が期待できます。歩幅が広くなることで歩く速度も上がるため、同じ時間歩いたとしても運動量が増えるでしょう。
『歩行速度と健康状態には関連性がある』という調査結果もあります。『歩くスピードが速い人は、認知症の発症リスクが低く健康寿命も長くなる』という報告もあるようです。
歩幅を気にかけることで、将来の健康によい影響を与えるかもしれません。
ウォーキングで歩幅を改善する方法
歩幅を無理なく広げるには、次の3つのポイントに気を付けましょう。
こうしたポイントを押さえて歩くことで、自然と歩幅が広がり、運動の負荷も高くなります。急に変えるのではなく、日常の中で少しずつ取り入れるのがポイントです。
歩き方を変えることで、健康維持が期待できるでしょう。
歩幅の平均と健康の関係を知り、歩き方を見直そう
歩幅には個人差があり、加齢とともに徐々に狭くなる傾向にあります。歩幅が小さくなることで、転倒しやすくなったり、歩行スピードが遅くなったりすることが分かっており、体力や認知機能の低下とも関連しているようです。
歩幅を少し広げて歩くことで、筋力維持や、代謝の向上が期待できます。自分の歩き方や歩幅を把握して、無理のない範囲で改善しながら健康を維持しましょう。
[文・構成/grape編集部]