エスニックとは何のこと? 意味や料理、服装やインテリアまで解説!
公開: 更新:

※写真はイメージ

真冬に上着を忘れた警察官 震えながらの説得に違反者が放った一言筆者が交番勤務をしていた頃、同い年で公私ともに仲のよい相棒がいました。警察官を辞めた今でも交流は続いています。 彼をひと言で表すなら『天然』。 早朝の事故対応に向かう車内で、昇る太陽を見ながら「昨日は満月だったんだね…」...
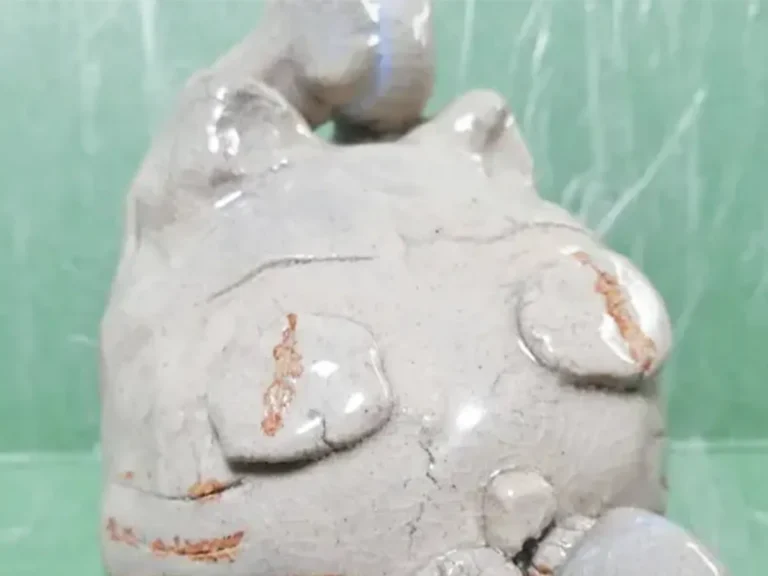
おでこにのせたはずが? 陶芸教室で作った猫の鈴、焼き上がりに吹き出す子供には、小さいうちから、できるだけいろいろな体験をさせてあげたいですよね。 ある日、筆者もそう考えて、息子たちと1日陶芸教室に行ってみました。 オーバーヘッドキックをする猫の陶鈴を作ったはずが? 陶芸教室では「猫の陶鈴...


『エスニック料理』や『エスニックインテリア』など、時々見聞きする『エスニック』という言葉。なんとなくの雰囲気で使っているものの、定義を説明できる人は少ないのではないでしょうか。
この記事ではそんな『エスニック』について、意味や特徴を詳しくご紹介していきます。この記事を最後まで読めば、『エスニック』を説明できるようになりますよ。
『エスニック』とは?
※写真はイメージ
まずは『エスニック』の意味を説明していきます。『アジアン』との違いや英語での表現もご紹介しますよ。
『エスニック』の意味
『エスニック』とは、『民族の』という意味を持つ言葉です。山岳に住む少数民族などを想像してもらうと分かりやすいかもしれません。
具体的には、アメリカの先住民族であるインディアンや、日本のアイヌ民族などすべての民族が含まれます。欧米では、アジア、アフリカ、中南米などの民族の、伝統的なスタイルを指すことが多いようです。
『エスニック』とアジアンの違い
では、『エスニック』とともによく聞く『アジアン』は、どういうスタイルを指すのでしょうか。アジアンとは『アジア風』を意味し、言葉通りアジア地域のみに対して使用されます。
『エスニック』という大枠の中にアジアンが存在している、と理解すると分かりやすいですね。
しかし、日本や中国の文化や慣習を『アジアン』と表現することはあまりありません。欧米ではイランやトルコ、北アフリカといった中東地域をアジアとみなすことが多く、日本では東南アジアあたりの文化を『アジアン』と呼ぶことが多いです。
『エスニック』の英語表現
『エスニック』は英語で『ethnic』と書き、『民族の』『民族的な』『民族に関する』といった、固有の文化や風習を持つ集団を指します。
『エスニック料理』の特徴
※写真はイメージ
続いて、『エスニック料理』といえば具体的にどのような料理なのか説明します。
『エスニック料理』はどこの国のもの?
日本で『エスニック料理』といえば、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシアといった東南アジアの料理を指すことが多いでしょう。
場合によってはインドやネパールといった南アジアや中東に加え、モロッコやブラジルなどの北アフリカ、中南米の料理まで含まれます。
日本料理では使われることのない香辛料や調味料を使った、イタリアンやフレンチなどの欧米料理を除くもの、と認識しておくとよいかもしれません。
『エスニック料理』の代表一覧
日本で一般的に知られている『エスニック料理』の代表例を挙げていきます。東南アジアの料理が中心です。
タイ料理
『エスニック料理』ブームの火付け役となった、タイ料理。
辛みと酸味の独特な味付けがくせになるスープ『トムヤムクン』や、タイ風のチキンライスである『カオマンガイ』、バジルとひき肉を炒めて目玉焼きとともにご飯にのせた『ガパオライス』など、想像するだけで食べたくなってきますね。
ベトナム料理
ベトナム料理は、米粉を使った料理が多いのが特徴です。ライスペーパーを使った『生春巻き(ゴイ・クォン)』や、米粉の平麺をスープに入れる『フォー』、ベトナム風お好み焼きといわれる米粉を使った『バインセオ』などがあります。
また、昔はフランスの植民地だったことから、フランスパンを使ったサンドイッチ『バインミー』や、カフェ文化を背景とした『ベトナムコーヒー』など、フランスとベトナムが融合した食文化も見受けられるのが面白いところです。
インドネシア料理
旅行先として人気のバリ島があるインドネシア。イスラム教徒の多い国民性のため、豚肉を使った料理は少ないです。
インドネシア風チャーハンといわれる『ナシゴレン』や、インドネシア風焼きそばの『ミーゴレン』は、甘みとスパイシーな辛さが独特のおいしさでやみつきになります。
マレーシア・シンガポール料理
マレー系、中国系、インド系など多様な食文化が入り混じっています。『海南鶏飯』というチキンライスや、ココナッツミルクを使ったカレー麺『ラクサ』、スペアリブを香辛料や香草とともに煮込む『肉骨茶』とも表記される『バクテー』などが代表的です。
料理以外の『エスニック』
※写真はイメージ
料理以外では何に対して『エスニック』という言葉が使われるのでしょうか。日本で浸透している『エスニック』文化についてご紹介します。
『エスニックファッション』
ゆったりしたシルエットやカラフルな原色使い、幾何学模様の柄が特徴的です。日本では夏の暑い季節に着る人が多いですね。人の目を引きやすいデザインなので、うまく着こなせれば周りからおしゃれだといってもらえることでしょう。
着こなしのポイントは、上下の柄や色のバランスを考えることです。上下どちらも原色や、どちらも柄にしてしまうと、派手でごちゃごちゃした印象を与えてしまいます。
服で取り入れるのが難しく感じる場合は、アクセサリーやサンダルといった小物から試してみるのもよいでしょう。1つ『エスニック』要素が加わるだけで、与える印象が変わるものです。
『エスニックインテリア』
異国情緒あふれる雰囲気が魅力的な『エスニックインテリア』。地域によって特徴が大きく異なります。
白やベージュをベースに植物を多用した、自然あふれるリゾートホテルのようなアジアンテイストや、はっきりとした色合いに繊細に刺繡された中近東のデザインが、想像しやすいのではと思います。
部屋の雰囲気を大きく変えずに取り入れたい時は、雑貨などの小物や、竹素材の製品を置いてみましょう。竹製品は日本の家屋にもなじみやすいので、和と『エスニック』を掛け合わせた素敵なスタイルになります。
一気に雰囲気を変えたい場合は、ラグやカーテンを変えるのがおすすめ。ファブリックの色味や柄が異なると、部屋の雰囲気がガラリと変わります。
『エスニック柄』
『エスニックファッション』やインテリアについて紹介しましたが、具体的に説明するのは難しいところですよね。ここでは代表的な『エスニック』の柄について、ご紹介していきます。
ネイティブ柄
ネイティブとは、『先住の』といった意味を持つ言葉です。『エスニック』と同様さまざまな地域が含まれますが、ファッション業界でネイティブ柄というと、『ネイティブアメリカンの部族の間で伝えられてきたインディアン柄』を意味し、複数の柄をまとめて指します。
ペイズリー柄
羽のような、または勾玉のような形の植物模様が特徴。バンダナやスカーフに使われていることが多いので、見たことがあるのではないでしょうか。生命力や霊魂がイメージされたネイティブ柄の1つです。
タイダイ柄
英語でタイ(Tie)は『縛る』、ダイ(Dye)は『染める』という意味です。縛って染める、『絞り染め』の手法を使って染色されるので、同じ仕上がりとなるものは1つとしてありません。カラフルな虹色がぐるりと円を描いているようなデザインが有名です。
オルテガ柄
こちらもネイティブ柄の1つ。スペイン系開拓移民のオルテガ一族が、ネイティブアメリカンのナバホ族の影響を受けて生み出されたデザインといわれています。
ひし形を組み合わせた幾何学模様が特徴で、ニットなど冬のものによく使われているでしょう。
ノルディック柄
アジアや北アフリカ地域ではありませんが、ノルウェーといった北欧の伝統的な柄も『エスニック』の一種に入れられることが多いです。トナカイやもみの木、雪の結晶がモチーフに使用されており、日本でも人気が高く、今では冬の定番デザインの1つですよね。
異国の『エスニック』文化に触れてみよう
『エスニック』について、意味から料理やインテリアなど、身近にある文化をご紹介しました。『エスニック』といっても、地域によって特徴がさまざまでしたね。
『エスニック』文化に触れる時は、どのあたりの地域なのか考えながらエスニック料理に舌鼓を打ったり、ファッションを楽しんだりしてみてはいかがですか。
[文・構成/grape編集部]