O157を甘く見ないで! 厚労省の注意喚起に「ゲゲッ」「絶対気を付けます」
公開: 更新:

※写真はイメージ
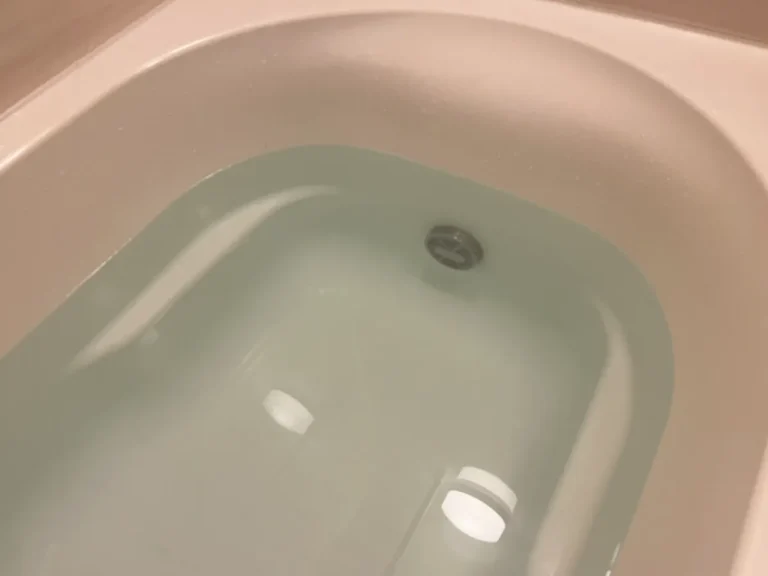
お風呂で家族が倒れていたらどうする? 政府が教える5つの手順【冬場の入浴事故】冬の入浴時、特に気をつけたいのがヒートショック。入浴中の事故を防ぐため、そして事故が起こった場合にするべきこととは?政府が教える手順を紹介しています。

「中毒症状を引き起こすことが…」 農林水産省が『貝毒』について注意を呼びかけアサリなどの漁業権の対象となっている貝は、指定されている場所以外で採取すると、漁業権違反となります。 一方で『漁業権の対象ではないけれど食用可能な二枚貝』もあり、その場合は採取して持ち帰ることが可能です。 しかし、管理さ...
- 出典
- 厚生労働省






ニュースでたびたび報道される食中毒の中でも、『O157』は広く知られています。
重症化すると命に関わることもあり、大切な家族を守るためには日頃からの予防が欠かせません。
本記事では、O157を防ぐための具体的な方法について解説します。
O157による食中毒を防ぐ方法
※写真はイメージ
O157は、『腸管出血性大腸菌』の一種で、ほんの少量でも体内に入ると激しい食中毒症状を引き起こすことがあります。
特に抵抗力の弱い子供や高齢者は重症化しやすく、命に関わる場合もあるため注意が必要です。
厚生労働省のウェブサイトでは、O157の予防策として、次のように呼びかけています。
O157は、湿度と温度が高い環境で急速に繁殖するため、特に夏場は注意が必要です。肉を調理する際は、最低でも75℃で1分以上加熱してください。
ステーキやハンバーグなども中心部までしっかり火を通し、「表面だけ焼けて中は生」という状態を避けましょう。
また、同省は食中毒を防ぐためのポイントとして『菌を付けない』『増やさない』の2つを提示しています。
調理前には必ず手を洗い、菌を食品に付けないこと。さらに買い物から帰ったら、生鮮食品はすぐに冷蔵庫へ入れて繁殖を防ぐことが大切です。
肉を小分け冷凍する際のポイント
※写真はイメージ
生肉は日持ちしないため、小分けにして冷凍保存する人も多いですが、冷凍すれば安全というわけではありません。
O157のような食中毒菌は、冷凍しても死なずに生き残るものが多く、解凍後の取り扱いに注意が必要です。
常温での自然解凍は菌が増える原因になるため、冷蔵庫でゆっくり解凍するか、電子レンジを使いましょう。
また、一度解凍した肉の再冷凍は避けるべきです。
冷凍する際は空気をしっかり抜いて密封し、早めに凍らせることもポイント。解凍後は中心までしっかり加熱し、安心して食べられる状態にしてから調理しましょう。
O157の感染を防ぐためには、日々のちょっとした心がけが欠かせません。
安全な温度でしっかり加熱し、清潔な環境で保存、調理することで、食卓の安心は守られます。
[文・構成/grape編集部]