家庭での鶏肉料理、食中毒に注意して 厚労省の投稿に「大事な情報」「気を付ける」
公開: 更新:

※写真はイメージ

梅干しのNG行為知ってる? 行政が教える『正解』に「盲点だった」「もうやらない」アルミ製品に入れたら、穴が空く。使う際に、注意すべき食品とは?
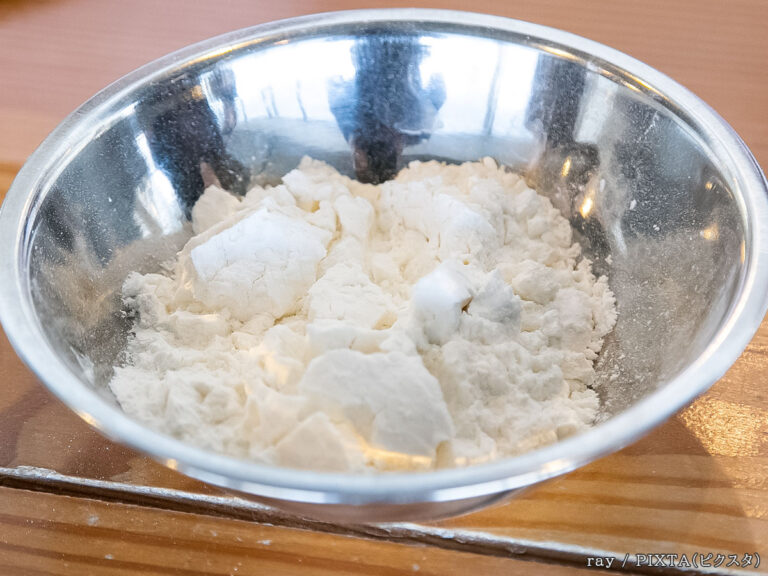
「生のまま食べないで」 製粉協会が注意を呼びかけ小麦粉は揚げ物の衣に使用したり、パンやお菓子の材料にしたりなど、料理に欠かせない材料です。 熱を通して食すことが基本で、生で食べるのは避けるべきといわれています。これはなぜなのでしょうか。 小麦・小麦粉の企業団体である製...
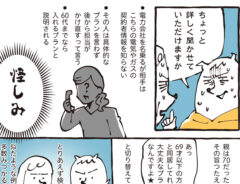





家族の健康を守るため、気を付けたいのが日々の食事です。食品の取り扱い方や調理方法を誤ると、食中毒を起こしてしまう恐れもあるでしょう。
食中毒にもさまざまな種類がありますが、比較的多いといわれているのがカンピロバクター食中毒です。
厚生労働省食品安全情報(@Shokuhin_ANZEN)の公式Xアカウントの注意喚起情報より、食中毒の原因や予防策について解説します。
カンピロバクター食中毒とは
カンピロバクターとは、ニワトリやウシの腸管内にいる細菌のこと。この細菌そのものは、決して珍しいものではありません。スーパーなどで販売されている鶏肉からも、高い割合で発見されているそうです。
熱に弱い特性を持つため、しっかり火が通った状態で食べれば、特に問題はないでしょう。一方で、生や半生、加熱不足の状態で食べると食中毒を起こす恐れがあります。摂取した菌が少量でも食中毒になりやすいため、十分に注意してください。
厚生労働省食品安全情報はX投稿で、カンピロバクター食中毒を予防するためのポイントとして、以下の3点を紹介中です。
・鶏肉は十分に加熱する
・サラダや魚の刺身など生食のものとは別で調理する
・鶏肉調理に使った器具は熱湯消毒する
鶏肉が十分に加熱されているかは、中心部の色から判断できます。しっかり白くなるまで火を通すようにしてください。中心までしっかりと加熱されているかどうか不安な時には、カットして確かめてから食卓に並べるのもおすすめです。
ほかの食材に菌が移ってしまう可能性もあり
鶏肉の調理そのものに気を付けていても、カンピロバクター食中毒になってしまうケースもあります。これは、調理前の生肉から、別の食材へと菌が移ったことが原因と考えられるでしょう。
生の鶏肉をカットした後のまな板と包丁を使い、生食用の野菜をカットすれば、当然汚染されてしまいます。器具を熱湯消毒してから使う、もしくはサラダの準備をした後に肉の調理をする、といった工夫が必須です。
厚生労働省食品安全情報の公式X投稿では、カンピロバクター食中毒は、「肉類が新鮮だから安全というわけではない」と伝えています。例え購入したばかりの鶏肉であっても、食中毒菌に汚染されている可能性は十分にあります。
そのリスクを理解したうえで、安心・安全な調理を心掛けてください。
カンピロバクター食中毒になると、1~7日程度の潜伏期間を経て、下痢や腹痛、発熱といった症状が現れます。「もしかして…」と思ったら、専門医に相談しましょう。
食中毒は決して特別なものではなく、誰にとっても身近なトラブルです。鶏肉の取り扱い方には、特に注意してくださいね。
[文・構成/grape編集部]