「考えられへん!」 ミス30ヶ所以上の『誤植本』が出版された理由
公開: 更新:
1 2

【2026年】2月の満月『スノームーン』とは?意味や願い事、スピリチュアルな面まで解説!この記事ではスノームーンとはどんな満月か、意味や由来、いつ見られるかをまとめます。観測に最適な時間を確認して、夜空に浮かぶ美しい月をゆっくり眺めてみてくださいね。

1月の満月『ウルフムーン』とは?名前の由来やスピリチュアルな意味、願い事についても紹介!1月の満月をなぜ『ウルフムーン』と呼ぶのか知っていますか?この記事では、ウルフムーンについての基本的な情報から、スピリチュアルな部分まで広く紹介します。

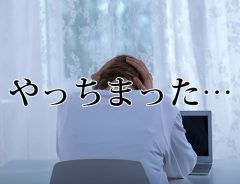



編集者がデータを修正する現状
今回、話を聞いた編集者は『岐阜信長歴史読本』の編集作業には「直接関わってはいない」とのこと。
しかし、編集部内にデスクを借り、内部で数十年編集作業を行っているというベテランのフリーランスで、「KADOKAWAでの編集作業の流れ」をある程度把握していると言います。
考えられるミスの原因について、話を伺いました。
――なぜ今回のような「ミスだらけの本」が出版されたのか?
今回の報道を聞いて、最初に思い浮かんだのは「データの先祖返りではないか」ということ。
KADOKAWAでは、現在ほとんどの編集部が文字修正などをInDesignというソフトを使い、編集者が行います。
校了データを印刷所に渡す際に、データが先祖返りしてしまった可能性が高いのではないでしょうか。
――詳しく言うと?
InDesignというのは、ページレイアウトソフトのことです。
ほんの十数年前までは、「ゲラ」と呼ばれる校正紙を印刷所が出校し、編集者はそれに「赤字」と呼ばれる修正を書き込んで印刷所に戻していました。
赤字を見た印刷所内のオペレーターがデータを修正し、再度校正紙を出校するという流れです。
――つまり、編集者がデータを触ることはなかった?
その通りです。
デザイン変更がある場合は、デザイナーがデータを修正しますが、基本的には編集者がデータをイジることはありませんでした。
例外はありましたが、「通常作業としてはない」と言い切っていいレベルです。
――それが現在では、編集者がデータを修正する?
InDesignの普及で、簡単にデータの修正ができるようになったので、編集者がデータを修正するようになりました。
作業量が増えるという意味ではデメリットですが、印刷所に赤字を戻す従来のやり方よりも、早く修正ができるため、スケジュールの調整が楽になります。
導入当時は印刷所に赤字を戻すというやり方をしていた人も、スケジュール上の問題から現在では、ほとんどの編集者がInDesignを使って自ら修正をしています。
――具体的にはどのような流れで作業を?
編集者がInDesignを使って原稿を流し込み、写真などを入れた最初のデータを初校と言います。
初校時は、地図データや写真はもちろん、原稿に関してもダミーが入っている場合がほとんど。スケジュールがタイトなため「すべてのデータを揃えて初校を出す」というのは、なかなか難しいのが現状です。
通常は、再校ですべてのデータをそろえ、修正を終えて校了するというのが一般的な流れです。あまりにも修正点が多い場合などは、念校を出す場合もありますね。
――「データが先祖返りする」とはどういうこと?
例えば、再校データをイジっているつもりで、初校データを開き、作業をしてしまうことなどを「データの先祖返り」と言います。
つまり、今回の場合で言うと「校了データだと思って印刷所に納品したものが、実は初校などの古いデータだったのではないか」というのが私の予測です。
――そんな初歩的なミスが起こり得るのか?
もちろん、滅多に起こることではありません。
しかし、今回ほどの規模ではありませんが、過去に「データの先祖返り」が原因で、本文に「あああああああ」というダミーが入ったまま出版された雑誌もあります。
スケジュールにもよりますが、校了前は精神的にも肉体的にも追い込まれている場合がほとんど。
睡眠時間が極端に短い中で「うっかり」ということを考えれば、「明日は我が身」です。本気で、今回の件を笑い飛ばしている同業者はいないのではないでしょうか。
また、「KADOKAWAなどの大手出版社で、校閲なしで本を出版するという話は聞いたことがない」とのこと。
そう考えると、今回のミスは「手を抜いたこと」で起こったのではなく、「編集の過程で起こってしまったアクシデント」とも言えそうです。
もちろん、担当した編集者にも過失はありますが、過酷な環境下で起こってしまったミスだとすれば、担当編集者だけのミスとすることには違和感もあります。
KADOKAWAは、「今回の事態がなぜ起こってしまったのか」の原因解明をWebサイトで約束しています。
今後、このようなミスを再発させないためにも、出版業界全体に労働環境や作業手順の改善が求められているのかもしれません。
※InDesignに関する記述に、誤解を招く表現がありました。訂正してお詫び申し上げます。
[文・構成/grape編集部]