『クレヨン』と『クレパス』の4つの違い!向いている素材や手入れ方法もご紹介
公開: 更新:

※写真はイメージ

ホワイトボードを綺麗にする4つの方法!汚れの原因や注意点もご紹介本記事では、ホワイトボードを綺麗にする方法や汚れる原因、掃除の際の注意点を解説。汚れの原因を理解し正しい方法で掃除すれば、綺麗な状態を簡単に保てるといわれています。清潔な状態で長く使いたい人はぜひ参考にしてください。

リングノートの正しい捨て方とは?金具の外し方や注意点も解説本記事では、リングノートの正しい捨て方を詳しく解説します。さらに、割り箸やリムーバーを使った簡単な金具の取り外し手順もご紹介。リングノートを処分する際の注意点も記載しているので、正しい捨て方を知りたい人はぜひ参考にしてください。


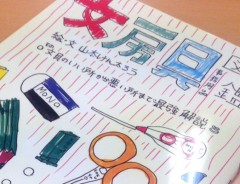



「小学校で『クレパス』がいるって聞いたけれど、『クレヨン』じゃダメなのかな」
「絵を描きたいけれど、『クレヨン』と『クレパス』どちらがよいのだろう」
『クレヨン』と『クレパス』は似ている文房具のため、違いを知らない人も少なくないでしょう。
実は、成分や特徴など大きく4つの違いがあり、色を塗った後の仕上がりも変わります。しかし、具体的にどのように違うかを知らなければ、選ぶ際に迷うかもしれません。
そこで本記事では、それぞれの違いや向いている素材、年齢についてご紹介します。手入れ方法や似た製品との違いも紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
『クレヨン』と『クレパス』の4つの違い
※写真はイメージ
『クレヨン』と『クレパス』の違いは4つ。大きな違いを感じにくい文房具ですが、実は色の発色や成分にさまざまな違いがあります。
どちらを使えばよいか迷っている人や、描きたい絵に合うほうを選びたい人は、違いを理解しておきましょう。
成分
『クレヨン』と『クレパス』は含まれる成分に違いがあります。『クレヨン』は着色顔料と固形ワックスのみで作られた、比較的シンプルな作りが特徴です。
一方で『クレパス』は、着色顔料と固形ワックスに加えて、液体油や体質顔料などを使用しています。体質顔料とは、硬さや滑りを調整する役割を持つ顔料のことです。
『クレヨン』にも液体油や体質顔料が使用されている場合もありますが、入っている量が違います。
使用している成分によって、それぞれのよさを引き出しているのでしょう。
硬さや滑りやすさ
『クレヨン』と『クレパス』では、『クレパス』のほうが軟らかく、滑りやすい性質を持ちます。そのため、広い範囲を塗りつぶしたい場合は『クレパス』のほうがきれいに仕上がるでしょう。
一方で『クレヨン』は少し硬めで滑りにくい性質が特徴です。広い範囲を塗りつぶそうとすると、隙間やムラができる場合も。
しかし、線画は『クレパス』よりも得意であり、細かい表現もしたい際は『クレヨン』がおすすめです。
どちらも塗りつぶしや線画ができないというわけではないため、好みにあわせて選びましょう。
色の混ぜやすさと重ねやすさ
『クレヨン』と『クレパス』の明確な違いとして、色の重ねやすさや混ぜやすさがあります。
『クレヨン』は色を混ぜたり重ねたりしにくいですが、『クレパス』は色が混ざりやすいのだとか。
そのため、描画の際に色を混ぜてグラデーションにしたい時やきれいになじませたい場合は『クレパス』を使用したほうがよいでしょう。
混ぜやすさや重ねやすさに違いが出る理由は、成分です。『クレパス』のほうが、体質顔料や液体油によって軟らかく伸びやすいため、色も混ざりやすくなります。
色をなるべく混ぜたくない場合や、色ごとの区別をはっきりさせたい場合は『クレヨン』がおすすめです。
塗った後の質感
『クレヨン』と『クレパス』は、全体を塗った後の質感も違います。『クレヨン』は、ベタつきにくく、触ってもサラッとしている点が特徴です。
一方で『クレパス』は液体油を含むため、『クレヨン』よりも手が張りつくように感じるかもしれません。
全体的には『クレパス』のほうがしっかりと色を塗っているように感じますが、もし触り心地が気になる場合は、『クレヨン』のほうが塗りやすいでしょう。
それぞれどの素材で使うのが向いている?
※写真はイメージ
『クレヨン』と『クレパス』は、成分のほか、硬さや塗った後の質感などが異なるため、使うのに向いている素材も分かれます。
それぞれどのような素材に適しているかを確認してから使用すれば、描きやすさを感じたり、クオリティの向上につながったりするかもしれません。以下で詳しく解説します。
『クレヨン』は厚手で凹凸のある素材
『クレヨン』は、多くの素材に使用できる文房具です。なかでも、特におすすめの素材は、画用紙などの厚手のタイプ。
表面がツルツルしている用紙より、厚手で凹凸のあるほうが、色の定着がよい傾向にあります。
また、コピー用紙などの薄い素材は、『クレヨン』で色をのせるとシワシワになるケースもあり、描きにくさを感じるかもしれません。
そのため『クレヨン』は画用紙などの厚手のタイプがおすすめです。さらに『クレヨン』であれば、ビニール袋などにも色をつけられる可能性があります。
『クレパス』は幅広い素材に使用できる
※写真はイメージ
『クレパス』に向いている素材も、基本的には『クレヨン』と変わりません。
『クレヨン』に比べると油絵のようなタッチもできるため、キャンバスなどに描くと特別感も出るでしょう。
また、木材にも適しているといわれており、幅広い素材で使用できます。さらに『パステル紙』という、パステル画に使用される紙もおすすめです。
パステル紙は、表面の凹凸や強度に特徴があり『クレヨン』にも適しています。色をきれいにのせたい場合は、厚手の紙や凹凸のあるタイプを探すとよいでしょう。
『クレパス』と『クレヨン』でおすすめの年齢は違う?
『クレヨン』と『クレパス』は素材の違いから、おすすめの年齢が異なります。
保育園や幼稚園児には、『クレヨン』の使用がおすすめです。『クレヨン』のほうが硬く、強い力で握っても折れにくい性質があります。
軟らかさのある『クレパス』は、小学生以降におすすめです。小学生になると色を塗る機会も多くあるため、『クレパス』のほうが表現しやすくなります。
ただし、必ずしも年齢に合わせる必要はありません。どちらが向いているのかを考えながら、より描きやすいほうを選ぶとよいでしょう。
『クレヨン』と『クレパス』の手入れ方法は?
※写真はイメージ
『クレヨン』や『クレパス』は箱も含めて汚れがつきやすく、使う時に手が汚れてしまうのが気になる人もいるかもしれません。その場合には、下記の方法で手入れをしてみましょう。
まず『クレヨン』と『クレパス』をきれいにする際は、柔らかい布を準備し、きれいに拭き取ります。布がない場合はティッシュでも代用可能です。
汚れがひどい場合などは、ベビーオイルなどを布に含んで落とすと、汚れを簡単に拭き取れるでしょう。
『クレヨン』や『クレパス』のケースも同様の方法できれいにでき、コットンや綿棒を使うと細かい部分まで拭き取りやすくなるため、ぜひ試してみてください。
また、巻紙の汚れがひどい場合は、剥がして新しくつけ替える方法がおすすめです。例えば、マスキングテープや折り紙を使うと、デコレーションしながらきれいにできます。
自宅にあるもので簡単にきれいにできるため、汚れを拭き取って長く楽しみましょう。
『クーピー』と『ぺんてる』は違う製品?
※写真はイメージ
『クーピー』と『ぺんてる』は、『クレヨン』や『クレパス』と似ているようで違う製品です。
『クーピー』は、株式会社サクラクレパスが1973年に発売した文房具で、正式名称は『クーピーペンシル』。『クレヨン』のような発色で色鉛筆のように使うことができ、消しゴムで落とすことができます。
『ぺんてる』は、大日本文具株式会社(現:ぺんてる株式会社)が1951年に発売した文房具です。
ぺんてる株式会社のウェブサイトによると、『ぺんてる』は固形描画材『パステル』の定着力が弱いという欠点をカバーし、発色がよく変色しにくいといった長所を生かした商品なのだとか。
品質のよさから反響を呼び、会社自体も「ぺんてるさん」と呼ばれていたことを受け、社名を変更した経緯があるそうです。
『クレヨン』と『クレパス』は仕上がりにも差が出る
『クレヨン』と『クレパス』は、一見すると同じ文房具ですが、入っている成分量に違いがあり、仕上がりや塗り心地にも影響します。
特に、色の混ぜやすさや重ねやすさは非常に違いが分かりやすく、色をきれいにのせたい場合は『クレパス』、線画をメインにしたい際は『クレヨン』がおすすめです。
ただし、質感などの好みによって、どちらが向いているのかは異なります。
画用紙などであれば子供でも描きやすいため、ぜひ『クレヨン』や『クレパス』を使って、さまざまな絵を描いてみてくださいね。
※この記事は、一部ぺんてる株式会社のウェブサイトを参照しています。
[文・構成/grape編集部]