手作りおでんで食中毒! 医師が教える『要注意な具材』に「こんなにたくさんあるなんて…」
公開: 更新:

※写真はイメージ
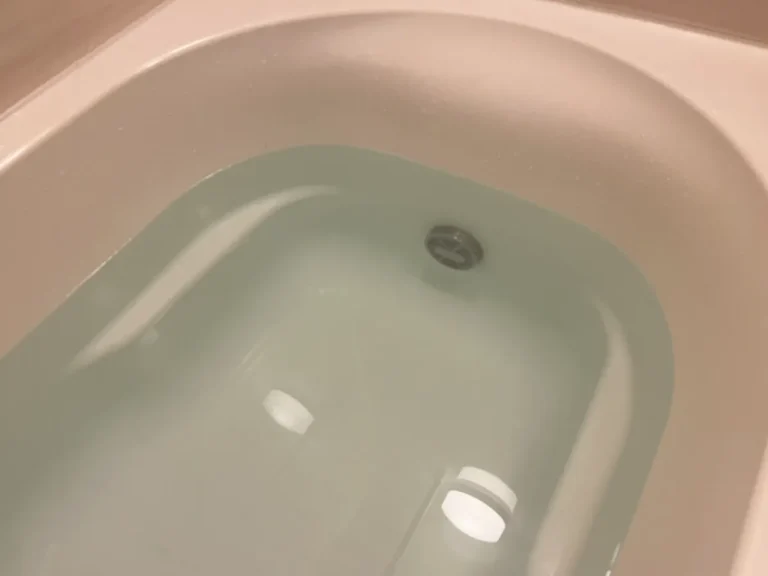
お風呂で家族が倒れていたらどうする? 政府が教える5つの手順【冬場の入浴事故】冬の入浴時、特に気をつけたいのがヒートショック。入浴中の事故を防ぐため、そして事故が起こった場合にするべきこととは?政府が教える手順を紹介しています。

「中毒症状を引き起こすことが…」 農林水産省が『貝毒』について注意を呼びかけアサリなどの漁業権の対象となっている貝は、指定されている場所以外で採取すると、漁業権違反となります。 一方で『漁業権の対象ではないけれど食用可能な二枚貝』もあり、その場合は採取して持ち帰ることが可能です。 しかし、管理さ...






寒い時期になると、無性におでんを食べたくなりますよね。
スーパーマーケットやコンビニエンスストアで売られている既製品もいいですが、好きな具材だけを入れられる、手作りおでんも魅力的。
具材を切って煮込むだけなので、冬のお手軽料理としても大人気です。
そんなおでんには、食中毒のリスクが潜んでいることをご存じですか。
なぜ温めて作るおでんで食中毒になる可能性があるのか、その理由を医師に詳しく取材しました。
『要注意な食材』『万が一食中毒になった時の対応法』も解説するので、おでんを作る予定の人はチェックしてみてください。
おでんで食中毒になるのはどんなパターン?
※写真はイメージ
まずは、おでんで食中毒になる原因を、大阪府大阪市にある、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニックで院長を務める、安江千尋医師にうかがいました。
おでんで起こる食中毒の多くは、ウェルシュ菌という細菌によるものです。
ウェルシュ菌は、土壌や人の腸にも存在する身近な菌。加熱調理中の高温の中でも、芽胞(がほう)という殻のような形で生き残ることがあります。
高温の料理の中でも生き残る細菌が原因なら、おでんで食中毒になる理由も納得できますね。
では、どんなパターンで食中毒が発生しやすいのでしょうか。
一番多いのが、鍋に入れたまま長時間常温で保存してしまうケースです。
煮込んだ後の鍋をコンロの上に放置したり、冷めてから冷蔵庫に入れようと思って忘れてしまったりなどのパターンですね。
ウェルシュ菌は、40~50℃前後に繁殖しやすい菌。調理から冷めるまでの間に繁殖した菌が作った毒素は壊れにくいので、再加熱しても安全とは言い切れません。
おでんなどの煮込み料理は「一晩寝かせると味がしみておいしい」と言われています。
しかし、安江医師によると「家庭では安全に『寝かせる』ことが難しく、実はもっとも危険な状態になります」とのこと。
鍋の中心部がぬるい温度が長時間続く状態は、NGのようです。
要注意な食材はある?
※写真はイメージ
おでんにはいろいろな具材を入れられますが、特に食中毒のリスクが高くなる具材はあるのでしょうか。
特に注意が必要なのは、タンパク質が豊富な練り物・肉類です。ちくわ・はんぺん・さつま揚げ・牛すじ・ゴボウ天などはウェルシュ菌の栄養源。
そして、大きくて内部の熱が冷めにくい大根やジャガイモは、冷めるまでに時間がかかるので、ウェルシュ菌が繁殖しやすくなります。
つまり『栄養が豊富+内部が冷めにくい』の組み合わせで、食中毒リスクも高まります。
まさか、そんなにたくさんあるなんて…!
食中毒と言えば、生の状態から調理する肉や魚などを思い浮かべる人が多いことでしょう。加工された練り物も要注意とは、驚きですね。
安江医師が挙げた具は、どれもおでんでよく見かける人気の具材。
いろいろな食材を入れるのが醍醐味とも言えるおでんで、食中毒のリスクが高まる具を避けるのは難しいでしょう。
そこで、安江医師に食中毒の対処法と予防法をうかがいました。
食中毒になった時の適した対応はある?
※写真はイメージ
食中毒になった場合は、主な症状として腹痛・下痢が現れます。多くは2~3日でよくなりますが、脱水症状には注意が必要。
特に子供や高齢者は脱水が進行しやすいので、水分と、ミネラルなどの『電解質(イオン)』をしっかり摂ってください。
症状が強い場合は、医療機関の受診を検討することが大切です。
下痢を繰り返すと脱水症状が現れる可能性があるので、水分と電解質を積極的に摂取したいですね。
特に、子供や高齢者が家族にいる場合は注意しておきましょう。
食中毒のリスクを考えたら、「おでんは一晩寝かせないほうがいいの?」と気になるもの。
家庭で安全に手作りおでんを食べるための予防策も、安江医師にうかがいました。
でき上がったおでんを常温で放置しないことが、一番の予防策です。完成後に粗熱を取って、浅い容器に小分けにしたら、冷蔵庫で保存してください。
翌日に食べる場合は、沸騰状態で数分間、再加熱することが大切。
1つの容器のおでんを一度に食べきり、再加熱を繰り返さないことで感染リスクを抑えられます。
大鍋料理は翌日も食べられるメリットがある一方で、保存方法によっては食中毒のリスクを高めます。
しかし、こちらの予防策をしっかりと実践すれば、家庭でも安全に料理を楽しめますよ。
大鍋料理を作る際は、早めに冷やす・小分け保存・しっかり再加熱。
おでんを作る時のために、ぜひ覚えておいてくださいね。
監修・取材協力 安江千尋医師
天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニックの院長。
消化器内科・内視鏡検査・肛門内科に特化した専門クリニックで、胃がん・大腸がんの早期発見と早期治療に取り組む。
また、消化管感染症や食中毒に関する診療・啓発活動にも携わる。
⇒Instagram、ウェブサイト
[文・構成・取材/grape編集部]