ワインの保存方法とは?おいしさの要因や開封後に保存する時のポイントを解説
公開: 更新:

※写真はイメージ

白菜の旬はいつ?おいしい白菜の見分け方や保存法をご紹介本記事では、白菜の旬の時期や新鮮な白菜の見分け方、保存方法についてご紹介。白菜は、スープなど冬に欠かせない野菜ですが、1年を通して目にします。旬の時期や1年中販売されている理由を知ることで、よりおいしく白菜を食べられるようになるでしょう。

里芋の芽は食べられる?芽がでた時の対処法や保存方法を解説ジャガイモと同じように、里芋の芽にも毒性があるのか気になりませんか。食べられるとしたら、どのように調理すべきか、知りたい人もいるでしょう。本記事では、里芋の芽は食べられるのかをテーマに、芽が出た時の対処法や保存方法を解説します。



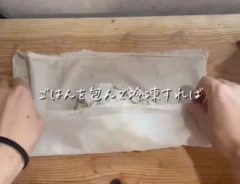


「ワインの正しい保存方法を知りたい」
「適切な保存方法で、ワインをおいしく飲みたい」
ワインを購入した時や飲み残した時に、保存方法で悩んだ経験はありませんか。未開封でも開封後でも、ワインをできるだけおいしく飲みたいと考える人もいるでしょう。
本記事では、ワインの保存方法やおいしさを左右する4つの要因、さらには開封後の保存方法のポイントについても解説します。ぜひワインをおいしく飲むための参考にしてください。
ワインのおいしさを左右する4つの要因
ワインのおいしさを左右する4つの要因を紹介します。
ワインは保存方法を間違えると味わいや香りが変化する可能性があるため、おいしく飲むにはできるだけ適切な保存状態を維持しなければなりません。
おいしさを左右する要因をおさえて、保存する時に役立ててください。
温度変化
※写真はイメージ
ワインの温度変化に注意しましょう。温度が高くなると熟成スピードが速くなり、逆に低くなるとワイン内の酸が減るとされています。
熟成スピードは品質に影響する可能性があるため、温度を変化させず一定の状態を保つことが重要です。
目安温度は、10〜15℃といわれています。保存する温度が高すぎたり低すぎたりするとワインの状態が悪くなるため、注意しましょう。
光
※写真はイメージ
ワインは光によって状態が変わる可能性があり、不快なニオイが発生するおそれがあります。
光は、直射日光だけではなく蛍光灯の光も含むようです。
そのため、ワインは光を避けた暗い場所で保存するのがよいでしょう。
振動
※写真はイメージ
ワインに振動を与えないことも、ポイントの1つです。
振動は、ワインの熟成を早めたり、味わいや香りが変化したりするおそれがあるとされています。
そのため保存場所には、一度置いたら栓を開けるまで動かさなくてよい場所を選択しましょう。
酸素
※写真はイメージ
酸素はワインの酸化をうながすため、酸素に触れさせないことがポイントです。
また、湿度は65〜80%が目安だといわれています。
乾燥した場所に保存するとコルクが縮んでしまい、ボトルの口との間に隙間が生じ、その隙間から空気が侵入して酸化をうながしてしまう可能性があるようです。
このような事態を防ぐためにも、ワインボトルはコルクがワインに浸る角度に寝かせて保存しましょう。
コルクをワインで湿らせることで、コルク自体の乾燥防止が可能になります。隙間が生じにくくなるため、空気の侵入を低減してワインの酸化防止につなげられるでしょう。
未開封ワインの保存方法
※写真はイメージ
未開封のワインは、気温10〜15℃、湿度65〜80%、そして光が遮られた場所で保管することがおすすめです。
コルクの乾燥を防ぐために、ボトルは横に寝かし、コルクがワインに浸かるようにする点も意識しましょう。
そのほか、ニオイの強いものはワインに移る可能性もあるため、ニオイ移りの原因となるものを近くに置かないようにしてください。
前述の通り、振動を与えることもワインの劣化につながる可能性があるため、できるだけ飲む瞬間まで動かさないように注意しましょう。
開封後のワインを保存する時のポイント
※写真はイメージ
ボトルに入ったワインを飲みきれず、そのまま保存したいと考える人もいるかもしれません。
しかし、一度開封したワインは未開封のものと異なり、空気に触れやすく味が落ちるリスクがあります。
開封後のワインを保存する時のポイントは2つです。ここでは、各ポイントについて解説します。
冷蔵庫でボトルを立てて保存し、早めに飲み切る
開封後のワインは、酸化を防ぐために冷蔵庫で保存しましょう。低温のほうが酸化スピードが遅くなるとされています。
また、できるだけ空気に触れる場所を減らすため、ボトルは立てて保存することがおすすめです。
開封後はある程度ワインが減っているため、寝かすより立てるほうが空気に触れる面積を小さくできる可能性があります。
なお、ワインの保存期間は1週間以内が目安とされており、冷蔵庫に保存した後はできるだけ早く飲み切ってください。
できるだけ空気に触れさせない
飲み残しのワインは、酸化抑制のためできるだけ空気に触れさせないことがポイントです。
ここでは、主な方法を3つ紹介します。
コルクで栓をする
※写真はイメージ
1つ目は、もともと栓として使われていたコルクを、再び『コルク栓』として使用する方法です。
コルク栓はワインオープナーによって穴が空いているため、コルクをラップで包んでから使用することで、隙間からの空気の侵入を防げるでしょう。
専用ストッパーを使用する
※写真はイメージ
ワインボトル用の専用ストッパーの使用もおすすめです。
ボトルの空気を抜くポンプ付きのアイテムを使えば、ボトル内の空気を減らして酸化を抑制できるといわれています。
ストッパーは使い回しができるため、ワインを楽しむなら用意しておくとよいでしょう。
小さな瓶に移し替える
※写真はイメージ
ワインの残量が少ないケースでは、ワインボトルよりも小さい瓶に移し替える方法があります。
容器を小さくすることで、空気との接地面積を小さくできるため、酸化を防ぐ効果が期待できるでしょう。
移し替えた後は、冷蔵庫に立てた状態で保存することで、より酸化を遅らせられるようです。
ワインの保存方法に関する疑問と回答
ここでは、ワインの保存方法に関するよくある疑問と回答をまとめました。
多くの人が疑問に思う内容に目を通すことで、失敗が減る可能性があります。ぜひ参考にしてください。
ワインセラーがない場合のおすすめの保存場所は?
※写真はイメージ
ワインセラーがないケースでは、季節によっておすすめの保管場所が異なります。
夏場は、外気温が30℃を超える日が多いため、ワインの常温保存は適していません。そのため、夏場は冷蔵庫の野菜室に入れておくのがよいでしょう。
この時、乾燥を防止するため、新聞紙などでボトルごと包むとよいといわれています。
冬場は、光が遮られた場所であれば常温保存が可能なようです。しかし、気温が低くなりすぎたり湿度が下がりすぎたりする可能性があるため、それらの管理も重要となります。
例えば、冷蔵庫の野菜室の温度が10〜15℃ほどであれば、季節に関係なく野菜室に入れてもよいでしょう。
開封後のワインはどれくらい日持ちする?
※写真はイメージ
開封後のワインの日持ち期間は、ワインの種類によって若干異なります。目安期間を下記にまとめました。
上記はあくまで目安であり、開封したワインはなるべく早く飲み切ることがおすすめです。
特に、スパークリングワインは炭酸が抜けてしまうおそれがあるため、開栓当日に飲み切りましょう。
味が落ちたワインを活用する方法はある?
※写真はイメージ
味が落ちたワインは、料理に使用することがおすすめです。
例えば肉を煮込む際に赤ワインを使うと、コクが深まるとされています。デミグラスソースに少し加えるだけでも、味に深みを加えられるでしょう。
一方で白ワインは魚介系との相性がよいとされ、火を入れる際に振りかけるとフルーティな香りでアクセントをつけられるようです。
煮込み料理や炒め物など、幅広い用途で使用できるため、ぜひ活用してみてください。
未開封のワインは温度、湿度、置き方に注意して保存する
未開封のワインは、温度10〜15℃、湿度65〜80%の光が当たらない場所で、ボトルを寝かせて保存しましょう。
また、保存場所のニオイや振動も品質の劣化につながる可能性があるため管理方法に注意が必要です。
飲むその時まで、静かな場所でそっと寝かせてあげること。そして、一度栓を開けたら冷蔵庫でしっかり休ませてあげることが大切です。
これらのポイントを押さえることで、ワインの繊細な香りや味わいを守れるでしょう。最後の一滴まで、ワインのおいしさをじっくりと堪能してください。
[文・構成/grape編集部]