「電車で泣いた」「本当にありがとう」 羽生結弦の『言葉』に感謝の声
公開: 更新:


「メダリストはやっぱ違う」「SNSの才能がある」 Switch2落選の宇野昌磨の『言葉』に大反響宇野昌磨さんが、Switch2当落でメダリストのメンタルを見せつける!?「SNSの才能がある」「秀逸」と、称賛の声が相次いでいます。
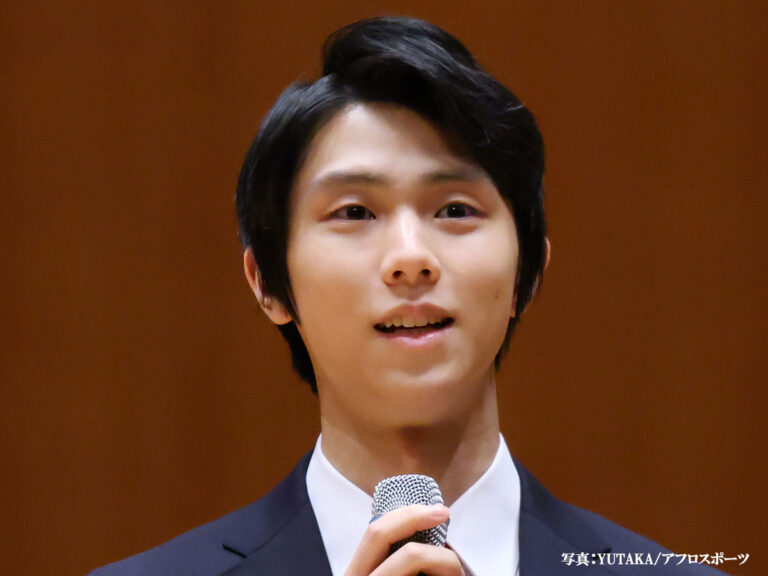
羽生結弦、2025年3月11日の深夜にSNSを更新 東日本大震災から14年が経ち…東日本大震災から14年が経ちました。羽生結弦さんがSNSに思いをつづっています。
- 出典
- サンケイスポーツ

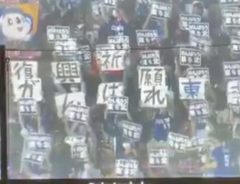




2021年3月11日で、東日本大震災発生から10年が経ちます。
この地震に見舞われ被災をした一人、フィギュアスケーターの羽生結弦選手。
同日サンケイスポーツは、羽生選手が被災した人々へ向けてつづった『メッセージ』を公開しました。
羽生結弦「でも、やっぱりいわせてください」
震災から10年を経てもなお、故郷へ戻ることができない人や行方が分からない人も多くいます。
仙台市の自宅が全壊し、自身も避難生活を経験したという羽生選手。
さまざまな心の傷を負いながら、日々生きる人たちへこのようなメッセージを贈っています。
羽生選手は、復興に向けて懸命に生きてきた人々へ、簡単にはいえないことを理解しつつも、「頑張ってください。僕も、頑張ります」という言葉を改めて贈ったのです。
震災だけではなく、世界という舞台でさまざまなプレッシャーや厳しい練習に耐えてきた羽生選手。
誰よりも「頑張れ」の持つ力を知っている、羽生選手だからこそいえる言葉に、ネット上ではさまざまな声が上がっています。
・電車の中で読んでいて、涙が出そうになりました。まだまだ復興の途中。一歩ずつですね。
・あの時から「頑張れ」って言葉が嫌いでした。でも、羽生くんの「頑張れ」は何か違うものを感じますね。ありがとう。
・羽生さんの頑張る姿に、どれだけの人が励まされたことか…。失ったものは元には戻らないけど、少しずつ前へ進んでいきたいと思えました。
10年が経過してもなお、被災した人々は、あの時の傷跡と向き合いながら生きています。
私たちがやるべきことは、震災の経験を風化させることなく、次の世代へ正しくつなげていくことだといえるでしょう。