マムシとほかのヘビとの見分け方は?遭遇した時の対処法も解説
公開: 更新:

※写真はイメージ
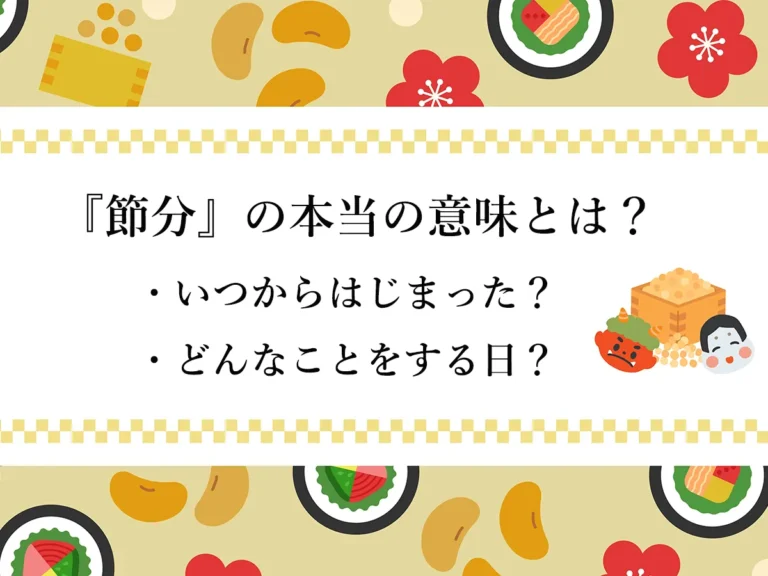
『節分』の本当の意味とは?いつからはじまったのか、何をする日なのかを解説!この記事では、節分とは何か、その意味や由来、節分の日の風習を分かりやすく解説します。行事の起源や節分に関するさまざまな風習を知ることで、毎年の行事がもっと楽しくなるでしょう。
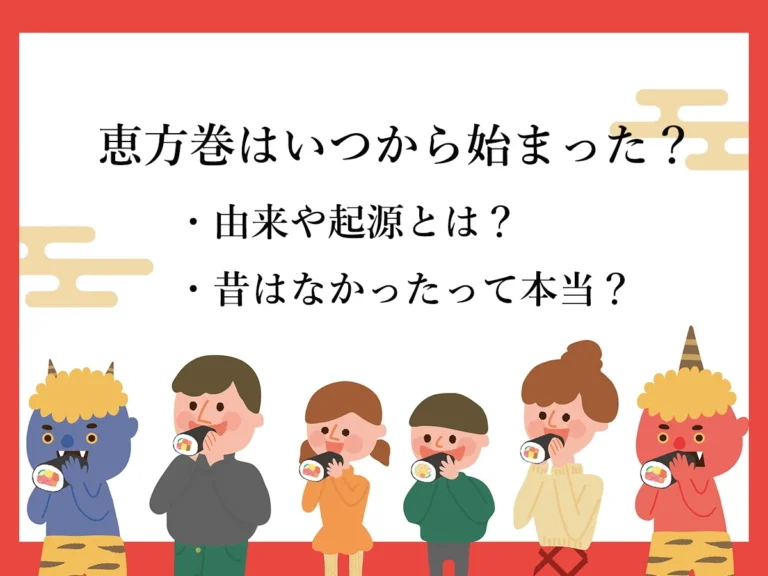
恵方巻はいつから始まった?由来や起源、広まった理由を解説!この記事では「恵方巻がいつから始まったのか知りたい」という人向けに、 恵方巻のルーツや「昔はなかった」と言われる理由を紹介します。一緒に見ていきましょう。






マムシは日本国内に広く生息する毒ヘビで、見つけたら一刻も早く距離をとるべき危険な生物です。
しかし、その見た目は地味で、ほかのヘビと似ているため、姿や形だけでマムシかどうかを見分けるのは難しいといわれています。もし誤って近付いてしまえば、命に関わる事故につながりかねません。
そこで本記事では、マムシの特徴やほかのヘビとの違い、実際に遭遇した場合の対処法などを詳しく解説します。
いざという時に冷静に判断できるよう、知識を備えておきましょう。
マムシの3つの特徴
※写真はイメージ
マムシについて正しい知識を身につけることは、野外活動を安全に楽しむために重要です。
ここでは、マムシの体の特徴や生態、行動パターンなど、基本的な情報を分かりやすく紹介します。
外見
マムシの体長は一般的に40〜60cm程度で、メスはオスよりもやや大きくなる傾向があり、大きな個体では、80cmに達することもあるようです。
体型は太くずんぐりとしていて、体には暗褐色や黒褐色の銭形模様があり、背中側で左右の模様がつながる特徴を持っています。
ただし、この模様は個体差があり、成体になるにつれて経年劣化や汚れなどにより模様が見えにくくなることがあるでしょう。そのため、模様だけでマムシかどうかを判断しないように注意してください。
マムシの体の地色は季節や生息環境によって変化し、茶褐色、灰褐色、赤褐色、あるいは黄土色など多様な色調を見せます。若い個体は成体よりも鮮やかな色をしていることが多く、尾の先端が黄色くなっているのも1つの特徴です。
マムシの頭の形は三角に近く、首との境界がはっきりしています。頭部の上面には小さな鱗が不規則に並んでおり、これは無毒のヘビとの重要な識別点になるでしょう。
また、マムシの瞳孔は明るい場所では縦に細長いスリット状になりますが、暗い場所では丸く開くため、観察する環境によって見え方が変わるのが特徴です。
生態
マムシは主に山間部や丘陵地、水田、河川敷などの湿った環境を好んで生息し、日中は岩の下や草むらに身を潜め、夕方から夜間にかけて活発に活動します。特に、梅雨の時期や夏場の雨上がりには出没頻度が高まるため、注意が必要です。
捕食の際は、ネズミやカエルなどの小動物を毒で仕留め、丸呑みにします。獲物を追いかけることは少なく、待ち伏せ型の狩りをする傾向があるようです。
マムシの繁殖期は秋で、卵ではなく直接子ヘビを産むという特徴があります。一度に2〜10匹程度の子ヘビを産みますが、生まれたばかりの子ヘビでも毒を持っているとされるため、注意が必要です。
行動パターン
マムシは動きが比較的ゆっくりで、刺激を受けるとトグロを巻いて身構え、「シャーシャー」と音を立てて威嚇することがあります。この音は、空気を強く吐き出して出すもので、警戒しているサインです。
多くのヘビが人を見つけるとすぐに逃げようとするのに対し、マムシはその場にとどまるか、ゆっくりと移動することが多いとされています。
また、冬眠から目覚めた春や繁殖期の秋には特に活動が活発になり、通常より目撃する機会が増えるでしょう。温かい日差しの中でのんびりと日光浴をしていても、刺激を与えると反応することがあるため、注意が必要です。
マムシとほかのヘビとの見分け方
※写真はイメージ
マムシは、日本国内で遭遇する可能性がある代表的な毒ヘビの一種です。野外でヘビに遭遇した際、それがマムシかどうかを見分けるためには、国内に生息するほかのヘビとの違いを知っておかなければなりません。
ここでは、マムシとほかのヘビとの見分け方を解説します。
ヤマカガシとの見分け方
ヤマカガシも毒を持つヘビですが、マムシとは見た目や行動に明確な違いがあるため、比較的見分けは付きやすいかもしれません。
成体のヤマカガシの体長は60〜120cm程度で、マムシはおおよそ40~60cmと、ヤマカガシよりやや小柄です。体型にも違いがあります。ヤマカガシが比較的細長いのに対し、マムシは太くずんぐりとした印象を受けるでしょう。
ヤマカガシの頭は丸みを帯びており、首との境界はマムシほどはっきりしていません。また、瞳孔は常に丸い形をしています。
ヤマカガシの模様の特徴は、頸部(首の後ろ)に赤色または橙色の斑紋があり、体の背面には黒と赤のリング状の縞模様です。ただし、これらの模様は個体や生息地域などによって差が大きい点に注意しましょう。
行動面では、ヤマカガシのほうが動きが素早く、水辺を好む傾向があります。また、ヤマカガシが威嚇する時に首を平たく広げる行動は、マムシには見られないものです。
ヤマカガシの性格はおとなしく、普段は人に襲いかかるようなことはほとんどありませんが、近付くと攻撃的になる場合があるため、マムシ同様、不用意に近付かないようにしましょう。
無毒ヘビとの見分け方
日本に生息する多くの無毒ヘビは卵形や楕円形の頭を持ち、首との境界があまり明確ではありません。対してマムシは三角に近い頭をしており、首との境界が明瞭です。
体の模様や色も異なる場合があります。例えば、無毒ヘビの一種であるシマヘビには、体に縦方向に走る4本の黒い縞模様があるのが特徴です。アオダイショウは成長すると、体の色がオリーブ色や青みがかった色に変化するといわれています。
ただし、模様や体の色については成長や個体差によって変化することがあるため、見分ける際の目安の1つとしてとらえてください。
また、多くの無毒ヘビの瞳孔はマムシと異なり日中でも丸い形をしていますが、近くでじっくり観察しなければ見分けがつきにくいです。
さらに、夜間はマムシも瞳孔が丸くなり、無毒のヘビと区別がつかなくなる可能性が高くなります。瞳孔での確認は難しいため、どの時間帯でも確認のために接近するのは避けたほうがよいでしょう。
行動面では、無毒ヘビは一般的に動きが素早く、人を見かけるとすぐに逃げる傾向があります。それに対して、マムシは本来おとなしい性質で、動きが少ないでしょう。
なお、無毒のヘビに咬まれても毒の心配はありませんが、防御行動として咬み付くことがあります。ケガをしないためにも、むやみに触れないようにするのが得策です。
マムシに遭遇した場合の対処法
※写真はイメージ
マムシを見つけた際、正しい対応を知っておくことで、危険を回避できるでしょう。
マムシを発見したら、まずは落ち着いて状況を把握することが大切です。慌てて走り出したり、大声を出したりすると、マムシを刺激して攻撃的になるおそれがあります。まずは立ち止まり、マムシとの距離を確認しましょう。
基本的には、少なくとも1m以上の安全な距離を保ちながら、ゆっくりと後退することが重要です。決して近付いたり、棒などでつついたりしないでください。
マムシは自分の体長の半分程度の距離まで、頭を素早く伸ばして攻撃できるため、写真を撮るために接近することも危険な行為といえます。
野山や田畑を歩く際は、リスクを減らすための予防策も大切です。長袖、長ズボン、トレッキングシューズなど、肌の露出を抑える服装を心がけ、草むらに不用意に手を入れないようにしましょう。
また、藪や石の陰などを確認しながら、足元に注意して歩くようにしてください。万が一、進路上にマムシがいて通れない場合は、迂回路を探すか、十分な距離を保ったままマムシが移動するのを待ちましょう。
マムシに咬まれた場合の応急処置
※写真はイメージ
マムシに咬まれた場合は、適切な応急処置と迅速な医療機関への受診が非常に重要です。
ここでは、各自治体のウェブサイトで紹介されている応急処置の内容をまとめました。
応急処置を行った後はすぐに119番通報をして救急車を呼ぶか、速やかに医療機関を受診してください。
また、可能であれば、咬んだヘビの種類や特徴を医師に伝えられるようにしておきましょう。
マムシの見分け方を知って、安全に自然を楽しもう
マムシの特徴には、三角形に近い頭部と首との明確な境界、銭形の斑紋、猫のような縦長の瞳孔などがあります。毒を持つヤマカガシをはじめ、ほかのヘビとの違いも把握しておくことで、万が一見かけた場合でも冷静に対処できるでしょう。
マムシに遭遇した場合は、慌てず、静かに安全な距離を保ちながら立ち去ることが基本です。決して刺激したり近付いたりせず、落ち着いて行動しましょう。
万が一咬まれてしまった場合には、適切な応急処置を行い、速やかに救急車を呼ぶか、医療機関を受診してください。
また、野外活動の際には、マムシに咬まれないよう予防することも大切です。長袖、長ズボンの着用や、草むらに不用意に手を入れないといった基本的な注意点を守り、安全に自然を楽しみましょう。
※この記事は、一部各自治体のウェブサイトを参照しています。
[文・構成/grape編集部]