家計簿が続かなかった理由は○○だった!? 楽しく続けられる方法とは
公開: 更新:
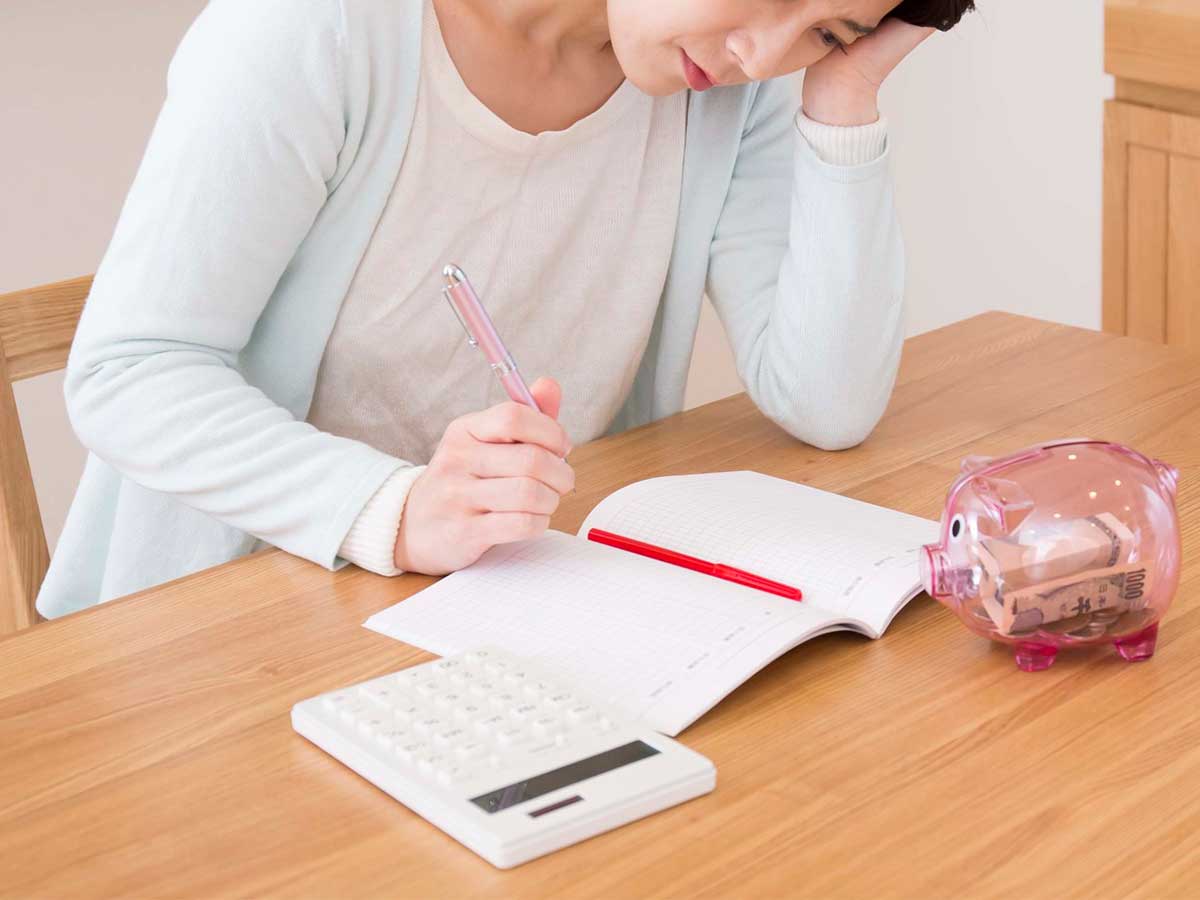
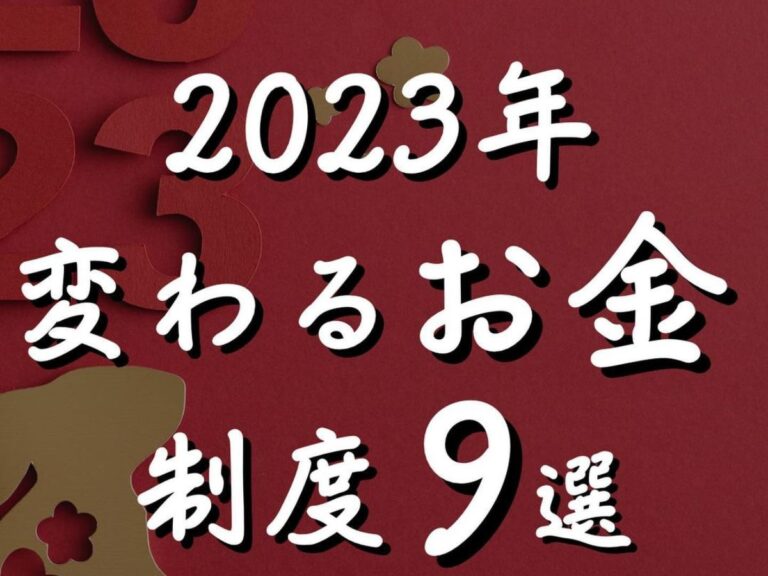
「参考になる」「知らなかった」 2023年に変わる「お金の制度」2023年はお金に関する制度にいくつか変更されるため、将来のために損をしないよう学ぶ必要があります。意外と身近な制度もあるのでいくつかご紹介します。

普通の50円玉に見えるけど…? 『超レア硬貨』の値段に驚愕!お財布の中に眠っているかも? 50円玉が、5~10万円に!?
grape [グレイプ] lifehack
公開: 更新:
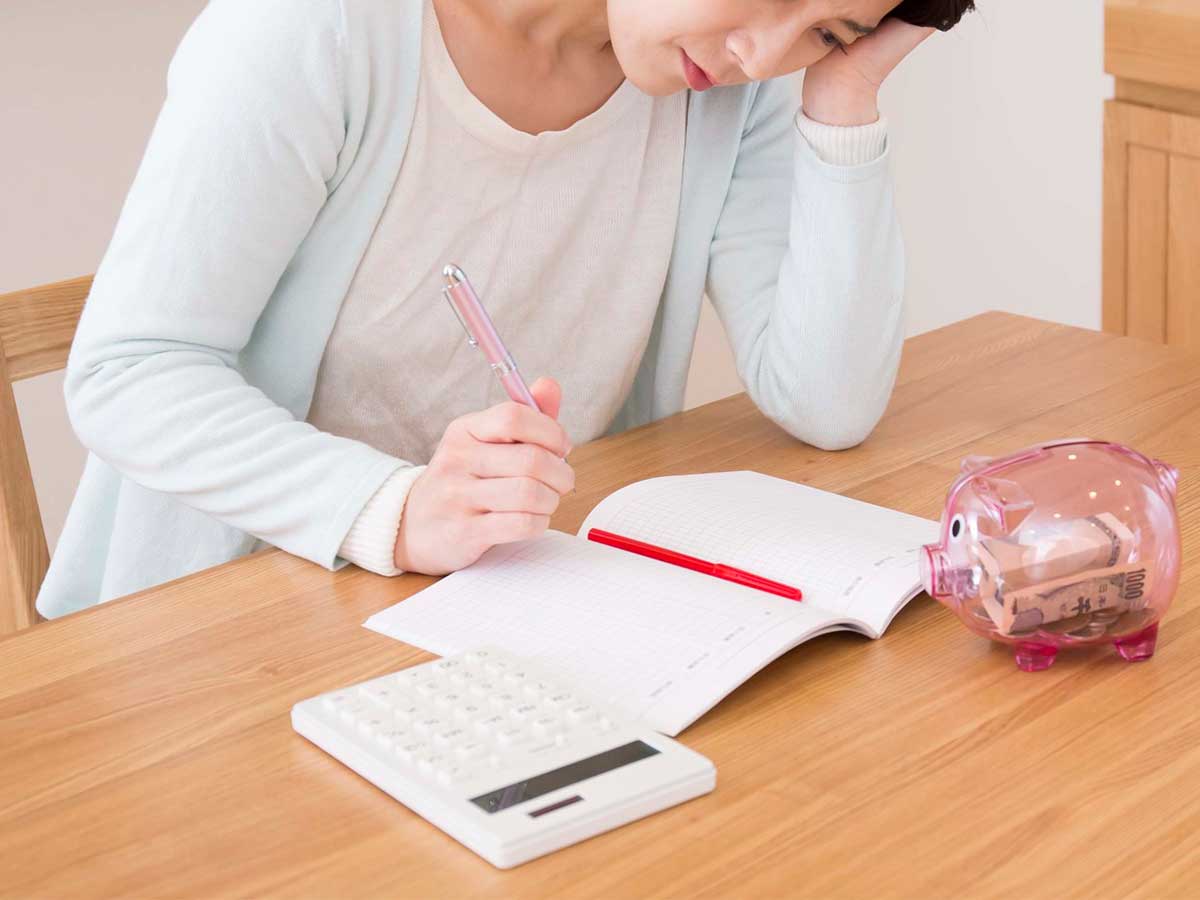
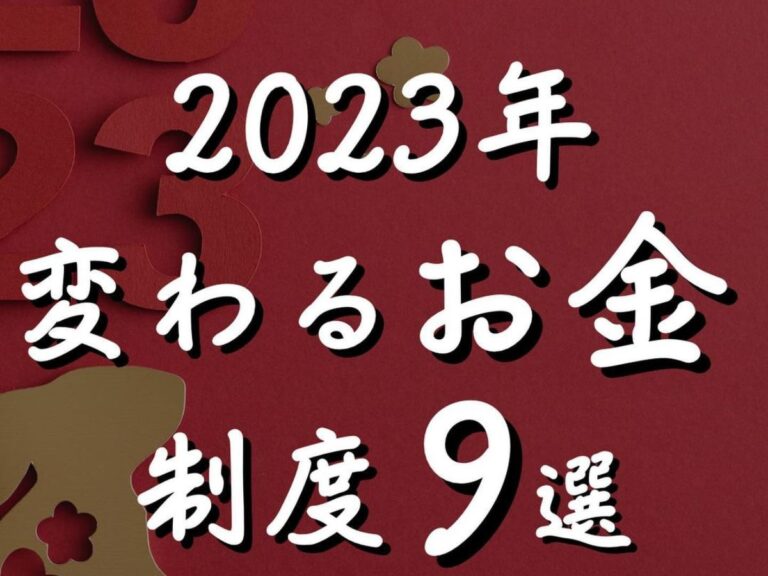
「参考になる」「知らなかった」 2023年に変わる「お金の制度」2023年はお金に関する制度にいくつか変更されるため、将来のために損をしないよう学ぶ必要があります。意外と身近な制度もあるのでいくつかご紹介します。

普通の50円玉に見えるけど…? 『超レア硬貨』の値段に驚愕!お財布の中に眠っているかも? 50円玉が、5~10万円に!?
「家計管理をしっかりしよう!」と思っても、家計簿を記入し続けるのは難しいですよね。
なかなか家計簿が続けられなかったAさんは、使いやすそうな家計簿ノートを購入しても、ただ書くだけで満足し、節約も貯金もできませんでした。
「どうしたら家計簿が続けられるのだろう…」と悩んでいた時のこと。Instagramで貯金ができている人をチェックするうちに、自身が犯していた家計簿の使い方の間違いに気付いたといいます。
Aさんのように家計簿が続かない人の共通点は、一体なんなのでしょうか。
家計簿をつける『目的』を見失っている
そもそもなぜ家計簿を記入し続けなければいけないのでしょうか。
家計簿とは「何にいくら使った」ということを細かく記入する必要はなく、次のポイントが分かればいいのです。
・今月はあと何円使えるのか。
・目標のために何円残せたか。
Aさんは、購入頻度が高い食費や日用品などについては、『商品ごとの値段』を忘れずに記入することを続けていました。
しかし、一つひとつ記入したり、支出の合計金額を出したりするのが面倒になり、だんだんと適当になったそうです。
結局頑張って記入しても残高が合わないことがあり、さらに面倒になる負のループ。
そこで、家計簿を続ける目的が品物の金額を記入し続けて、残高を合わせることになっているのに気付きました。
Aさんは商品ごとの値段を記入するのを辞め、使った金額のみざっくりと記入するように変更。
そして、食費や日用品などは月ごとに予算を立て、予算内でやりくりをするように変えました。
家計簿は残高を合わせるのではなく「何にお金を使いすぎているか」「決めた予算は適切か」をチェックするようにしたことで、貯金ができるようになったそうです!
1円単位で残高を合わせようとしていた
ちゃんと記入したのに、残高が合わないことが続くと嫌になりますよね。
Aさんも1円単位で残高を合わせようとしてはうまくいかず、家計簿を記入することを何度も挫折しました。
レシートをもらい忘れていたり、自販機などを利用した時にメモし忘れたり…。使ったらすぐ家計簿につけられたらいいのですが、なかなか難しいものです。
そこで、Aさんは使ったお金と残高を合わせる作業を辞め、次のような使い方に切り替えました。
1:毎月かかる家賃や、電気代などの光熱費、保険代や通信費(以後、固定費)を書き出す。
2:収入から固定費を引いて残った金額を確認。そこから、貯金したい金額分を先に抜いておく。
3:最後に残った残高内で、食費や日用品など、月によってばらつきのあるものに使う予算を決定。
予算内でやりくりを頑張れば、仮に残高が合っていなくても貯金できています。そのため、家計簿をつけるのはもちろん、家計管理が楽になったそうです!
家計簿をつけた後の『振り返り時間』がなかった!
その後、家計簿を3か月ほどつけ続ける中で、お金は貯まらず節約もできていないことに気付いたAさん。
家計簿を続ける意味が分からなくなり、結局挫折してしまいました。
Aさんは、家計簿を書き続けることが目的になっていて、「毎月何にいくら使っているのか」「無駄な支出があるかどうか」「いくら貯められているか」を把握していなかったのです。
そこで、家計簿をつけた後に、しっかり見直す時間を設けることで、次のようなことを把握できるようになったといいます。
・食費や日用品は毎月いくら予算があればいいか。
・毎月の固定費をいくら削減できるか。
・使っていないのに加入しているサービスなど、無駄な支出はないか。
この見直す時間を確保したことによって、貯金できるようになったそうです!
さらに「いくら貯金できたか」を確認することで、家計簿を楽しみながら記入できるようになりました。
家計簿の記入が続かない人は、ついつい『書き続けること』や『残高を合わせること』が目的になりがちです。
固定費やいつものお買物を見直すことで、無駄な支出がないかどうかを確認してみてください。
「いくら残せたか」が分かる家計簿を作れたら、きっと家計管理も楽しくなるはずです!
AIPONさんの記事はこちら
※記事中の写真はすべてイメージ
[文/AIPON 構成/grape編集部]