客の『迷惑動画』に一蘭が声明を発表 コメントに「応援します」「心から同情」
公開: 更新:

※写真はイメージ

マクドナルド「購入はお断り」 マナー違反者への対策に「いいと思う」「もっと厳しく」2025年8月月14日、『マクドナルド』は今回の混乱について謝罪するとともに、同月15日に開始する『ハッピーセット』では第2弾に先駆けて、購入制限を設けることを発表。

STARTO社『リーガル公式アカウント』開設 今後の活動に「心強い」「厳しくやってほしい」2025年8月13日、STARTO ENTERTAINMENTは、Xに法律に関する専用アカウントである『STARTO ENTERTAINMENT(Legal)』を開設。同日の投稿では、アカウントを開設した経緯や活動方針を発表しました。



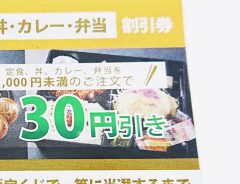


2023年1月末、寿司チェーン店『スシロー』で撮影された非常識的な動画を皮切りに、ネット上ではさまざまな迷惑行為が話題になるようになりました。
『炎上』した動画に映っているのは、店内の備品を舐めたり、ホームレスをからかったり、会計前の食品にいたずらをしたりする若者の姿。
どれも、SNSのフォロワー数や『いいね』数が目当ての、承認欲求の暴走による非常識的な行為といえるでしょう。
『スシロー』の騒動をきっかけに、ネットでは非常識的な動画を公開しているアカウントが取り上げられるようになり、相次いで迷惑行為が明らかになっています。
SNSでの迷惑行為に『一蘭』が声明を発表
同年3月、動画SNS『TikTok』で公開された1本の動画がネット上で拡散。
そこには、ラーメン店『一蘭』で、『ライダーキック』のコメントとともに店内のディスプレイに飛び蹴りをしたり、備品を床に投げ捨てたりしながら笑う男性が映っていました。
備品を投げ捨てる際には「はよ来てくださいボケ」という一文も。店員がなかなか席に来ず、男性は腹を立てていたのでしょうか。
動画がネット上で拡散されると、男性の迷惑行為に対し「何が面白いのかが分からない」「どうしてこんなことができるのか」といった声が上がりました。
一蘭「二次被害が発生した場合、法的措置を」
騒動を受け、同月15日に『一蘭』はウェブサイトで『SNSで拡散された一蘭店舗での迷惑行為に関するお知らせ』を公開。
撮影された店舗を特定した上で、騒動が一定の解決まで進んでいることを報告しました。
「今後、迷惑動画によって二次被害が起こった際は、法的措置などの厳正な対応をとる」と意向を示した『一蘭』。
一方で、前述した『スシロー』の件を含むこれまでの『炎上』は、ネット上での行きすぎた誹謗中傷行為も問題視されています。
撮影者の個人情報を特定してネットに公開したり、通っている学校に電話をしたりといった、『私刑』のような行動にも疑問の声が上がっていました。
『一蘭』が今回、詳細の公表を控える判断を下し、今後の対応について明らかにしたのは、騒動の外野による一方的な白熱化を防ぐためでもあるのかもしれません。
「店と利用客を守りたい」という想いが伝わる『一蘭』の真摯な対応に、ネットから応援する声が上がっています。
・大好きな『一蘭』でそんなことが…。今後も変わらず応援します。
・ちゃんと解決に向かっているようで安心した!撮影者がちゃんと反省するといいな。
・企業側も大ごとにしたくないんだろう。こうして声明を出すことで、迷惑行為が減るといいね。
インターネットの発達によって、今や若者を中心に、現実世界と同じようなコミュニケーションの場になりつつあるSNS。
気軽にいろいろな人と触れ合うことができる一方で、時には思いもよらない速度で自身の情報が拡散され、取り返しのつかないことになってしまう危険もあります。
過剰なまでの承認欲求を満たそうとした結果の暴走行為と、ネット上での『私刑』ともいえる行きすぎた批判…これらは、どちらもネット社会ならではの問題なのでしょう。
数々の『炎上』騒動を経て、幼い子供を持つ人からは「どうやって、我が子にインターネットとの向き合い方を教えればいいのか」という不安の声も上がっています。
どんな道具も、使い方によっては人に害を与えてしまうもの。インターネットの便利な一面だけでなく、恐ろしい一面も子供たちにしっかりと伝えなくてはなりません。
[文・構成/grape編集部]