夏場のお弁当には注意して! 農水省の注意喚起に「知っておくべき」
公開: 更新:

※写真はイメージ

食中毒を防ぐには? 内閣府の呼びかけに「意外」「知らなかった」【食中毒の予防4選】暖かくなる季節、油断大敵なのが食中毒です。注意喚起の記事を4つ集めました。
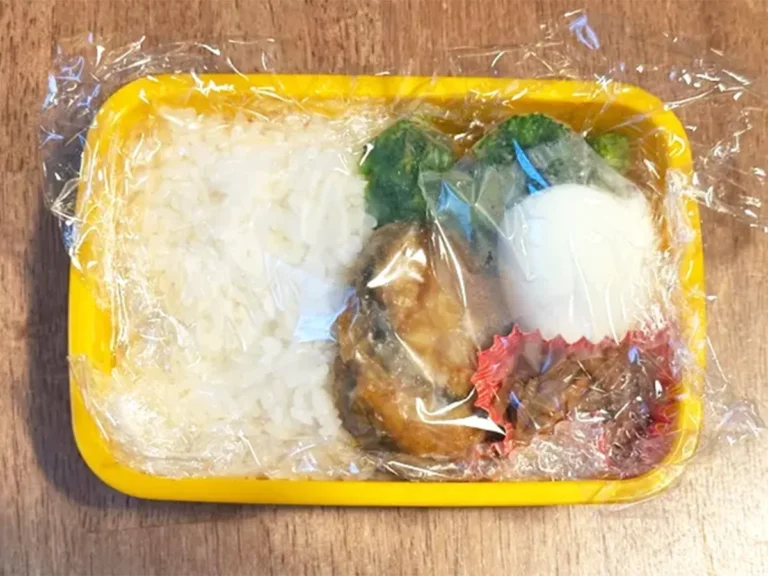
弁当にラップ1枚被せると? 思わぬ効果に「変わらない」「ビックリ」【弁当の裏技】忙しい朝に、せっかく時間をかけて作った弁当。昼に開けてみると、片側に寄ってしまっていることはありませんか。 いわゆる『寄り弁』に、日々職場や学校でがっかりしている人は多いでしょう。 そんな『寄り弁問題』を、ラップ1枚で解...
- 出典
- 農林水産省






通勤、通学時や、お出かけ時に持ち歩くことの多いお弁当。暑い季節に気になるのが食材の傷みによる食中毒です。
安全にお弁当を食べるにはどうすればいいのか、保管方法はどうしたらいいのか、心配になる人も多いでしょう。
農林水産省は食中毒予防の大原則として『付けない』『増やさない』『やっつける』を提唱しています。
安全にお弁当を楽しむために知っておきたいポイントを詳しく紹介します。
食中毒予防その1 お弁当を作る前に『付けない』
食中毒予防の1つめは、お弁当を作る前に菌を『付けない』ことです。
普段、当たり前に行っていることでも見落としていることがあるかもしれません。チェックも兼ねて確認してみましょう。
手をしっかり洗う
調理前はもちろん、調理中に生の肉や魚、卵を触った時、トイレに行った際にはしっかり手を洗いましょう。
手や指に傷がある場合は、調理用の手袋を使用して手を覆いましょう。
お弁当箱は清潔なものを使用する
洗う時はゴムパッキンを外し、泡スプレータイプの洗剤やスポンジを使用して隅々まで洗いましょう。
洗った後は十分に乾かすのがベストですが、洗った直後にお弁当箱を使用する場合は、清潔な布巾で水滴をしっかり拭き取りましょう。
調理用具は清潔なものを使用する
洗剤できれいに洗い、しっかり乾かしたもので調理しましょう。盛り付ける時には清潔な菜箸や使い捨ての手袋を使いましょう。
食材を洗う
野菜や果物、魚介類は流水でよく洗いましょう。ただし、肉は食中毒菌がシンクに飛び散るため、洗ってはいけません。
盛り付けるカップにも注意
シリコン製のカップはお弁当箱と同様に清潔にしましょう。梅雨時期と夏場は使い捨てのカップを使うようにしましょう。
食中毒予防その2 お弁当を作る時に『やっつける』
次に、菌を『やっつける』対策です。
農林水産省の公式サイトでは、おかずを作る際の注意点として以下のように説明しています。
卵焼きやゆで卵などは半熟ではなく完全に固まるまで加熱してください。
火を通さなくても食べられるハムやカマボコなども加熱してからお弁当に入れたほうがよいそうです。
さらに、公式サイトでは食中毒の原因となる微生物が死滅する時間と中心温度の目安を紹介しています。
菌が死滅する中心温度と時間の目安
・ノロウイルス…85〜90℃で90秒以上加熱
・腸管出血性大腸菌、カンピロバクター、サルモネラ族菌…75℃で60秒以上加熱
・リステリア…65℃で数分加熱
菌を死滅させる時間と温度の目安を覚えておくと、安心材料の1つになります。
食中毒予防その3 お弁当を詰める時に『増やさない』
最後は、菌を『増やさない』対策です。農林水産省の公式サイトでは、4つの方法が紹介されています。
水分が出ないようにする
水分が多いと、細菌が増えやすくなります。食品からの水漏れを防ぐため、仕切りや盛り付けカップを使用しましょう。
生野菜や果物はよく洗い、水気を切ってからお弁当に詰めましょう。揚げ物や焼き物など、もともと水分の少ないおかずを詰めるのも効果的です。
冷やしてから詰める
ご飯やおかずが温かいうちに詰めてしまうと、傷みの原因になってしまいます。しっかりと冷ましてから詰めましょう。
作り置きは再加熱する
お弁当の安全のためには当日調理が基本です。やむをえず前日に調理したものや昨晩の残りを詰める際は、必ず再加熱してください。
涼しいところで保存する
作ったお弁当を保存する場合は、冷蔵庫や涼しい場所がベストです。長時間持ち歩く場合は、保冷剤や保冷バッグを使用しましょう。
通勤通学時に限らず、ピクニックやレジャーなどお弁当を持って出かけることもあるでしょう。
そんな時は食中毒予防をしっかりとして、安全でおいしいお弁当を楽しみましょう。
[文・構成/grape編集部]