リンゴを罵倒してイジメ教育 ユニークな手法に「自分も習いたかった」と絶賛の声
公開: 更新:

出典:Facebook

「この発想はなかった!」 青森県で撮影された『鏡餅』に、7万人がザワつく北海道から青森に移り住んだ、Manato.N(@mn_05410)さん。青森で見た鏡餅に驚き、Twitterに公開したところ、多くの反響が寄せられました。

「好き嫌いは仕方ない。でも、みんなで嫌うは絶対にダメ」 だって、それがイジメだから「どうしても気が合わない」 そんな人がいるのはある意味で仕方がないのかもしれません。しかし、同じ嫌うにしても「他者に同意を求めてはいけない」という意見が称賛されています。


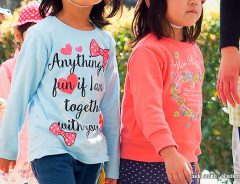



イギリスのバーミンガムにある「Relax Kids」というクラスの授業が大きな注目を集めています。
Relax Kids
感情のコントロールが不得手で、自分をうまく表現できない子どもたちに、リラックスした環境で穏やかに過ごしてもらうことを意図して設立された特殊学級。主に、繊細すぎる子どもや自閉症、鬱などの子ども。ストレスをためやすい子どもやイラつきやすい子どもなどが通うクラス。
「Relax Kids」はオンライン授業も行っており、高い人気を誇っています。
そんな「Relax Kids」でコーチをしているロージー・ダットンさんが行った「イジメが生き物に与える影響」という授業が絶賛されています。
身近なフルーツを使った斬新な授業
ダットンさんはイギリス人にも馴染みのあるリンゴを使って、説明することを思い立ちます。子どもたち、しかも精神面が安定していない子であれば、なおさら少し意外性のある授業が必要だと考えたからです。
リンゴを渡された子どもたちは、最初、困惑した表情を見せたと言います。
「なぜ、授業にリンゴがいるの? 分かんない」
元々、精神面があまり安定していない子どもたちです。中には苛立ちを露わにした子どももいたかもしれません。しかし、ダットンさんは続けます。
リンゴの2つのグループに分け、一方のリンゴにはこんな言葉を浴びせました。
「存在にも気付かなかったわ」
「臭いわね、あんた」
「虫でも湧いてるんじゃない?」
そして、他方のリンゴにはこう語り掛けました。
「素晴らしい色艶だわ」
「可愛らしいリンゴね」
「なんて美しいの!」
最後に、子どもたちにそれぞれのリンゴを真ん中からカットさせます。すると…
罵倒されたリンゴは、中が右のような状態になっていたのです。これには子どもたちも大きなショックを受けたようです。
タネも仕掛けもある授業
実はダットンさんは授業の前に罵倒する側のリンゴを、表面に傷がつかない程度に床に落とし、傷めておいたのです。しかし、表面だけを見ると、どちらのリンゴが傷んでいるのかは全く分かりません。
そして、この授業を行った意図を次のように説明しました。
この投稿は多くの共感を呼びました。
「こんなユニークな方法で教えてくれる先生に出会いたかった」
「発想が素晴らしいわ。こういった先生が増えれば教育が変わるはず」
「リンゴと人は違う。でも、間違いなく同じ部分もあるはずだ」
もしかしたら、ダットンさんの手法を快く思わない人もいるかもしれません。しかし、子どもにも直感的に分かりやすく、理解しやすい方法で伝えるというのは、本来は教育の基本。
ダットンさんのような教育者の教えが広まり、1人でも多くの子どもが「イジメは人の内面をボロボロにしてしまう恐ろしいものなんだ」という倫理観を身に付けることを願います。