牛乳の膜ができにくい温め方は? 企業の回答に「驚き」「次から入れてみる」
公開: 更新:

※写真はイメージ

麺をゆでる時に牛乳を入れると? 仕上がりに「全然くっ付かない」「感動した」麺をゆでた時に、数本の麺が鍋底にくっ付いてイライラしたことはありませんか。ゆでる前に『ある物を少し加える』だけで、麺がくっ付きにくくなります。簡単なアイディアなので、ぜひ試してみてください。

黄色の粉は『ターメリック』ではなく? 「この手があったか」「毎日食べたい!」冬に大活躍したコーンスープも、暖かい季節になるにつれて飲む機会が減っていませんか。そんな余りがちなコーンスープの活用方法を、ぱるん(parun_kurashi)さんが紹介していました。
- 出典
- 明治
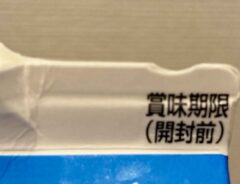





牛乳を温めて作るホットミルクは、身も心もほっこり癒してくれる飲み物です。しかし、牛乳を温めると表面に薄い膜ができることがあります。
この膜の正体は何なのか、そのまま口にしても問題はないのかと、不安を感じる人もいるかもしれません。
乳製品メーカーとしておなじみの株式会社明治(以下、明治)の公式サイトから、牛乳にできる膜について分かりやすく解説します。
膜の正体は牛乳に含まれる栄養成分
牛乳の表面にできる白く薄い膜について、明治では以下のように説明しています。
牛乳に含まれるタンパク質には、熱を加えると固まる性質があります。この固まってできたものが、膜です。
最初はほぼ目に見えないような薄い状態ですが、加熱時間が長くなり、温度が上昇すればするほど分厚くなっていきます。
加熱途中で膜を取り除く人もいますが、加熱を続ければまた新たな膜ができてしまいます。
何度も繰り返せば徐々に膜ができにくくなるものの、これは牛乳から栄養が失われている証拠です。
膜ができてしまった時はそのまま食べる、食感の悪さが気になる人は加熱段階で膜ができないよう気を配るとよいでしょう。
せっかくの栄養を無駄にしないよう注意してください。
膜ができにくい温め方とは?
牛乳の表面にできる膜は、温め方を工夫することでできにくくなります。
牛乳の膜は、40℃を超えたからといって、すぐにできるわけではありません。
先述したように、最初は目に見えないほどの薄い膜からスタートします。しっかりとかき混ぜながら温めていくと、固まりにくくなるでしょう。
また、牛乳に砂糖や重曹を加えて温めるのも効果的です。砂糖はタンパク質が固まる温度を上げる効果、重曹はタンパク質を固まりにくくする効果があります。
少量であれば、砂糖や重曹が牛乳の味や風味への影響もありません。
明治が紹介している『よく混ぜながら温める』や『電子レンジを使う』といった方法に組み合わせて使うと、表面の膜がよりできにくくなるでしょう。
牛乳の表面にできる薄い膜の正体は、タンパク質が固まったものです。膜を食べても健康に悪影響を及ぼすことはなく、むしろ牛乳の栄養を余すことなく摂取できます。
乳製品に関わる疑問や不安を解消し、より身近な存在として親しんでみてください。
[文・構成/grape編集部]