アルバイトとパートの違いとは?呼び方の由来や待遇面について解説
公開: 更新:

※写真はイメージ
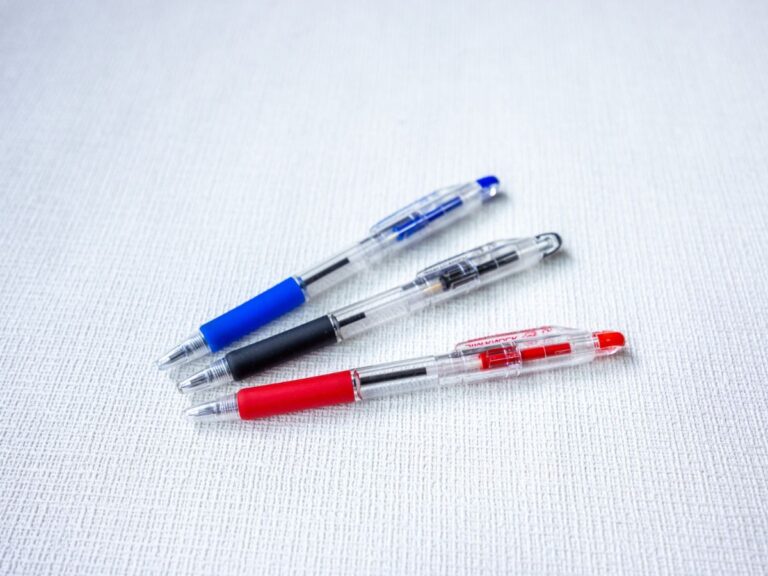
集中力を高めるなら「この色のペン」 専門家の助言に「知らなかった!」色にはそれぞれ効果があることを知っていますか。上手に使い分けることで、集中力を高められたる相手に好印象を与えられたりします。

『ワンオペ』の意味とは? 仕事・育児のワンオペについて解説仕事をしている人や、育児をしている主婦の人は『ワンオペ』という言葉を聞くことも多いのではないでしょうか。この記事では、ワンオペの意味や問題点が分からない人に向けて徹底解説していきます。いまいちワンオペについて分からないことが多い人や、ワンオペの仕事に興味がある人は参考にしてください。






「アルバイトとパートは何が違うの」
「働き方に違いはあるの」
アルバイトとパートの違いについて、上記のような疑問を持つ人もいるかもしれません。2つの働き方には、どのような違いがあるのでしょうか。
今回は、呼び方の由来や、待遇面でのアルバイトとパートの違いについて解説します。
それぞれの働き方に向いている人の特徴もまとめたので、参考にしてください。
アルバイトとパートの違いとは?
※写真はイメージ
アルバイトとパートには、法律上の違いはなく、どちらも『パートタイム労働者』に区分されます。
パートタイム労働者とは、正社員よりも、1週間の所定労働時間が短い労働者のことです。
短時間労働者を、企業独自のルールにより勤務時間帯や条件で区分して、『アルバイト』もしくは『パート』と呼びます。
パートタイム労働者は、2020年4月施行の『パートタイム・有期雇用労働法』により守られています。
「雇用が不安定な労働者の不安を解消し、短時間で働く人を守り、誰もが公平で正当な待遇を得られる環境を実現する」ために制定されたのです。
さらに事業主は労働者に対して、労働条件や正社員との待遇の差について説明する義務が強化されました。
「正社員と有期雇用労働者の間に、不合理な待遇の差を設けない」と定められています。
アルバイトとパートの呼び方の由来とは
※写真はイメージ
基本的に正社員は、所定労働時間内にフルタイム勤務することを前提に、契約期間を定めないで雇用されます。
一方アルバイトやパートは、短時間勤務で契約期間も定められています。
同じパートタイム労働者でも、アルバイトとパートで呼び方が異なるのはなぜでしょうか。
それぞれの由来について解説します。
アルバイトの由来はドイツ語の『arbeit』
アルバイトという呼び名の由来は、ドイツ語の『arbeit』です。
学生が、学業の合間に家庭教師などを行い、収入を得ることを『アルバイト』と呼んだのが始まりといわれています。
アルバイトは、土日祝日や夕方から深夜早朝の勤務、体力重視の仕事、繁忙期の単発雇用といった条件で募集されるケースが一般的。
アルバイトは主に、人手不足の解消を目的に募集されます。
パートの由来は英語『part timer』
パートの由来は、英語の『part timer(パートタイマー)』で、『full-time(フルタイム)』の対義語です。
家事や子育てなどで時間に制約がある主婦や主夫が、その合間に短時間で働くことを指します。
パートは、主に平日昼間の固定シフトが多く、長期的な雇用を前提に募集される傾向にあるようです。
主婦や主夫向けのパート求人は、これまでの経験を生かせる業務や正社員に近い仕事内容としている職場もあります。
アルバイトとパートの働き方にそれぞれ向いている人
※写真はイメージ
アルバイトとパート、それぞれの働き方に向いている人の特徴について解説します。
アルバイトに向いている人
アルバイト勤務は比較的自由度が高いため、学業やほかの仕事と両立したい人に向いています。週2~3日の勤務や、長期休暇中の短期雇用が多いようです。
・社会経験によりマナーや作法が身に付く。
・人との出会いが増える。
・アルバイトのみで生計を立てている場合は、社会的に不安定な立場に見られる。
パートに向いている人
パート勤務は、家庭と仕事を両立できるため、安定的な働き方と長期雇用を求める人に向いています。
週4~5日、1日4~6時間程度の勤務が多いようです。
・長期間の継続雇用が多い。
・幅広い年齢層が採用されている。
・スキルが少なくとも勤勉性を評価されやすい。
・固定シフトが多く自由度が少ない。
・昇級や昇進の機会が少ない。
・正社員に比べて収入が安定しない。
アルバイトとパートの待遇の違い
※写真はイメージ
アルバイトとパートの待遇の違いは、会社や勤務条件によります。
法律で定められている『社会保険』や『有給休暇』は、雇用形態に関わらず、条件を満たすことで適用されます。
ただし、企業独自の福利厚生は雇用形態によって適用条件が違うため、まずは会社に確認しましょう。
ここでは福利厚生、社会保険、各種制度が、アルバイトやパートの場合どのように適用されるのかを解説します。
福利厚生
交通費の支給や社割など、会社独自の福利厚生は企業ごとに異なるため、直接確認することが大切です。
交通費や通勤手当の支給については法律上の定めがなく、企業の就業規則に委ねられます。
支給条件が『自宅から2km圏内』など、一定距離以上を対象とする企業もあるため、面接時や入社前に労働条件を確認しましょう。
社会保険
アルバイトやパートでも要件を満たした場合は、社会保険への加入が必須です。
2024年10月より適用範囲が拡大し、従業員数が『51~100人』の企業で働くパートやアルバイトも、社会保険の対象となりました。
この場合の従業員数とは、フルタイムで働く従業員かつ、1週間や1か月の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の人が対象です。
厚生労働省のウェブサイトに記載されている、社会保険の加入要件は、以下の通りです。
【社会保険の加入要件】
一方雇用保険は、事業所規模に関係なく適用要件を満たしていれば、原則加入となります。
ただし学生は、雇用保険の加入対象にならない場合もあるため確認が必要です。
【雇用保険加入の適用要件】
雇用保険への加入手続きは、事業主が行います。また、現在は未加入でも、遡って加入できる場合があります。
事業主が加入手続をしていない場合は、労働者自らハローワークで雇用保険の確認が可能です。
各種制度
残業代、有給休暇、産休、育休などは雇用形態に関わらず原則付与されます。
ただしパートやアルバイトの残業は、採用時に『労働条件通知書』に雇用条件として明示されていないと行えません。
労働条件通知書とは、業務内容や賃金、就業時間、所定時間外労働の有無など、基本的な労働条件を示すもののこと。
有給休暇も労働基準法に基づき、就業規則で定める条件に該当する場合は適用されます。
パート、アルバイトともに入社から半年経てば、労働契約書で定めた勤務日の8割以上を出勤することで、有給休暇の取得が可能です。
産前産後休業(通称:産休)、育児休業(通称:育休)は、法律で定める条件に該当していれば、アルバイトやパートでも取得できます。
産休の取得には、入社時期やシフトの日数、有期雇用の制約はありません。
アルバイトとパートの違いに関する『よくある質問』
※写真はイメージ
アルバイトとパートの違いに関する『よくある質問』をまとめました。
パートとアルバイトの違いは年齢ですか?
パートとアルバイトの違いは、年齢ではありません。
ただし、一般的に『アルバイト』は10〜20代の学生で『パート』は主婦または主夫を指すことが多いようです。
学生やフリーター向けの『アルバイト募集』は短期間勤務、主婦または主夫を対象にした『パート募集』は長期間勤務の仕事が多い傾向にあります。
ただし、法律上はパートとアルバイトに違いはありません。
求人の条件を満たせば、主婦や主夫がアルバイトに、学生やフリーターがパートに応募しても差し支えないでしょう。
パートとアルバイトでは時給が違うのですか?
パートとアルバイトで、時給に違いがあるわけではないようです。
ただし、法律で定められているわけではないため、企業によってはパートとアルバイトで時給が違う場合もあるでしょう。
また、パートとアルバイトの給与面での違いとしては、支払い方法が挙げられます。パートの場合は、雇用条件によって給与の支払い方法が異なるケースもあるでしょう。
例としては、アルバイトは時給制で給与が支払われるのに対し、パートは時給制のほか、日給制や月給制もあるなどのケースです。
アルバイトとパートは企業によって定義が異なる
アルバイトとパートは法律上での違いはなく、企業によって定義が異なり、呼び方として使い分けられています。
社会保険加入要件の拡大により、パートやアルバイトでも、厚生年金保険や健康保険に加入できる対象者が増えました。
スキマ時間を活用できるパート、アルバイトの雇用環境も、以前より整っています。
勤務先を決める際は仕事内容だけではなく、雇用条件を確認してから選ぶとよいでしょう。
『アルバイト』や『パート』という呼び方の違いやイメージにこだわらず、募集要項を確認して自分に合った働き方を探すことが大切です。
※この記事は、一部厚生労働省のウェブサイトを参照にしています。公開から時間が経っている場合は、一部情報が変更されている可能性があります。ご了承ください。
[文・構成/grape編集部]