団子と餅の違いは?材料の違いや使い分けのコツを解説
公開: 更新:

※写真はイメージ

スイーツ好きなら挑戦! 読めたらスゴい『洋菓子の漢字』【3選クイズ】知っているようで知らない、洋菓子の難読漢字に挑戦しませんか?「加須底羅」「猪口令糖」「可麗餅」など、日本人に人気のスイーツに当てられた意外な漢字表記をクイズ形式でご紹介します。あなたの好きなスイーツの名前は漢字で書ける?読めたらスゴい、食通も驚く雑学と、洋菓子の興味深い歴史を徹底解説!

大根を切ったら断面が青色だった! 「食べても大丈夫?」の問いに農水省が回答切ったら青色に変色していたダイコン。その真相に生産者からも「広まってほしい」の声!


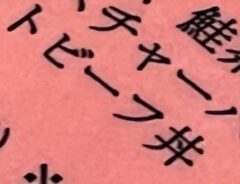



お正月やお花見など、日本のさまざまなイベントで目にする『団子』と『餅』ですが、それぞれの違いを説明できますか。
両者の主な違いは、言葉の意味やその作り方にあります。
本記事では『団子』と『餅』の違いや意味を解説。さらに『上新粉』や『白玉粉』との違いなどもまとめました。
『だんご粉』を餅や『もち粉』で代用する方法から、団子と餅の一般的な使い分け方まで解説しますので、ぜひ参考にしてください。
『団子』と『餅』の違いは何?
※写真はイメージ
『団子』と『餅』の作り方や意味の違いは、下記の通りです。
団子は、うるち米やもち米の粉に水や湯を加えてこねて丸め、蒸したりゆでたりして作ります。
一方、餅はもち米を蒸してから、臼と杵などでついて作られるのが一般的です。米粒をついてつぶすことで、もっちりとなめらかな粘り気の餅ができます。
『団子』と『餅』の言葉の意味の違い
※写真はイメージ
団子と餅は、言葉の意味も異なります。ここでは、その違いを見てみましょう。
『団子』の意味
団子は『米を丸めて蒸したもの』ですが、さらに『丸めたもの』『ひとかたまりになっているもの』という広い意味を持つようです。
例えば『肉団子』のように、原料が米だけに限定されていない場合にも使われます。
団子は、縄文時代に木の実をつぶして丸めたことが、始まりになっているようです。
『餅』の意味
餅は『もち米を蒸してついたもの』ですが、広い意味ではもち米以外の穀物で作るものも含まれます。
例えば、うるち米を蒸した後につぶして作る『五平餅』もその1つでしょう。
語源は諸説ありますが、円形の餅を『望月』すなわち『満月』に例えたことが由来のようです。
このように特定の原料以外でも、団子と餅は料理名に広く使用されています。
『上新粉』『もち粉』『白玉粉』『だんご粉』の違い
※写真はイメージ
団子や和菓子に使われる代表的な米粉には、主に以下の4種類があるといわれています。それぞれの特徴を知って、使い分けを楽しみましょう。
米粉の原料と形状をはじめ、団子の食感や風味、用途の違いを表にまとめました。
歯ごたえがある。
粘りが少ない。
ちまき
柏餅
弾力がある。
もち米の風味。
求肥
やわらかい。
よく伸びる。
大福
フルーツポンチ
うるち米
コシがある。
もちもちしている。
さらに、このほかにも違いがあります。
上新粉は、うるち米を砕いた粉を指しており、団子作りではポピュラーな材料といえるでしょう。
米粉の多くは、水を注いで混ぜますが、上新粉は熱湯を入れて練るようです。粘りが少ないため、加熱後にこねて粘りを出すこともあるのだとか。
白玉団子は冷たくなっても硬くなりにくいことが、ほかの米粉との違いです。フルーツポンチなどにも向いているでしょう。
ほかの米粉とは製法に違いがあるため、顆粒になっています。
『団子』と『餅』のカロリーの違い
※写真はイメージ
団子と餅の原料3種類のカロリーをまとめると、100gあたり下記の通りです。
どれも100gに対して約340kcalほどと、カロリーに大きな違いはないといえるでしょう。
『だんご粉』を代用する方法
※写真はイメージ
『だんご粉』が必要なレシピにも関わらず家にない場合、『もち粉』などの米粉があれば、代用できるようです。
また『切り餅』で代用できるケースもあるようなので、レシピと方法をご紹介します。
『上新粉』と『もち粉(白玉粉)』を合わせる
だんご粉は、うるち米を粉末にした『上新粉』と、もち米を粉末にした『もち粉』を混ぜて作れます。
もしだんご粉がない場合、この2つを混ぜることで代用が可能です。一般的な割合は5:5ですが、食感の好みで6:4や4:6のように調整することもできます。
ちなみに、もち粉がない場合は白玉粉で代用もできるようです。
また、フードプロセッサーでもち米を砕いて使うこともできますが、市販の粉ほど細かくはならず、少し粒感が残る場合があるので、注意しましょう。
『切り餅』を使う
だんご粉を使わなくても、切り餅があれば団子を作れるかもしれません。ここでは、みたらし団子のレシピをご紹介しましょう。
切り餅1個に対するみたらし団子の材料は、下記の通りです。
【材料】
作り方は、鍋にみたらし団子のたれの材料である醤油、砂糖、水、片栗粉を入れて火にかけます。とろみが付いて透明感が出るまでかき混ぜましょう。
切り餅に水をかけてから耐熱皿に入れてレンジにかけ、餅が膨らむまで温めましょう。
目安は600wで1分~1分半ですが、一度で柔らかくならない場合は柔らかくなるまで、様子を見ながら少しずつ加熱するのがポイントです。確認する際はやけどに注意しながら行いましょう。
餅が柔らかくなったら、スプーンなどでこねます。
こねた餅に片栗粉を付けながら、一つひとつ丸めた後、みたらし団子のたれをからめて皿に盛り付けて完成です。
団子と餅を入れて相性がよいのは『しるこ』と『雑煮』のどっち?
※写真はイメージ
団子と餅を『しるこ』と『雑煮』に入れる場合、どちらのほうが相性がよいのでしょうか。
『しるこ』には、団子がよく合うといわれています。小豆の優しい甘さと、もちもちしながらも歯切れのよい団子の食感は相性抜群です。白玉団子を使えば、つるんとしたのどごしも楽しめますね。
雑煮のレシピでも団子を入れるものはありますが、そのように紹介されているレシピはごくわずか。一般的には雑煮に団子を入れるケースは少ない傾向にあるようです。
一方、餅の場合は『しるこ』と『雑煮』の両方ともレシピが多く存在することから、どちらにも合うといえるでしょう。
実は、しるこのレシピ数は団子を入れるものよりも、餅を入れるほうが多いようですが、おいしさとは別の理由が考えられます。
日本では、昔から正月に餅を食べるという習慣があるためです。正月に残った餅を消費するために、しるこに入れる人が多くいるのではないでしょうか。
『団子』と『餅』の違いは作り方と言葉の意味、食感や用途が挙げられる
『団子』と『餅』は、どちらも言葉に広い意味を持っており、作り方にも違いがあると分かりました。
ただし、肉団子や五平餅があるように、団子や餅の名称が付いていても原料が同じとは限りません。米粉は団子の材料ですが、餅と同じくもち米が原料に使われていることもあるためです。
団子と餅、そしてさまざまな米粉の違いが分かると、料理がもっと楽しくなるでしょう。それぞれの食感や風味を生かして、おやつ作りやお料理にぜひ役立ててみてください。
[文・構成/grape編集部]