白菜が『苦い』原因とは?苦味を取る3つの調理法や見分け方のコツをご紹介
公開: 更新:

※写真はイメージ

【簡単レシピ】ニンジン1本をピーラーで削ったら… できたものに「箸が止まらなくなる!」ニンジンを丸ごと使った『リボンサラダ』を2種類の味つけで、実際に作ってみました!

ゴボウは使わない!新感覚の『きんぴら』に「ご飯のお供にぴったり」【作り置きレシピ】煮物や汁物などに使うことの多い、大根。 旬の時期は特に甘味が増しておいしいですが、やわらかくなるまでの煮込み時間が長かったり、味がうまく染みなかったりして、苦労することはありませんか。 そこで、短時間でおいしく作れる大根...

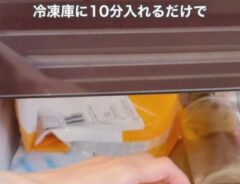




『白菜』は、さまざまなレシピに活用できる、冬の食卓に欠かせない野菜の1つです。
しかし、いざ食べてみると「苦い」と感じることもありますよね。そんな時「苦味の原因はなんなのか」「食べても身体に害はないのか」と気になる人もいるでしょう。
そこで本記事では、白菜が苦くなる原因や苦味を取る調理法、苦味の少ない白菜を見分けるポイントについて分かりやすくご紹介します。
「おいしい白菜をいつでも楽しみたい」と言う人は、ぜひ参考にしてください。
苦い白菜は食べても大丈夫?
※写真はイメージ
一般的に、苦い白菜を食べても健康に害はないとされています。その理由は後述しますが、おもに『含まれる成分』『栽培時期』『保存状態』が影響するようです。
苦いからといって腐敗しているわけではないため、苦味にそこまでの不安を感じる必要はありません。
ただし、『長く保存している』『保存状態が悪い』などの理由で、腐敗してしまう可能性もあります。
苦味ではなく、異臭やカビ、ぬめりといった腐敗のサインが見られる場合は、食べずに廃棄するとよいでしょう。
白菜が苦くなる原因とは?
本章では、白菜が苦くなる原因を4つご紹介します。苦味の理由や特徴を理解し、白菜をよりおいしく楽しむためのヒントにしてください。
イソチオシアネート
※写真はイメージ
白菜を苦いと感じる原因の1つに、アブラナ科の野菜に含まれる『イソチオシアネート』が挙げられます。
イソチオシアネートは、白菜などアブラナ科が本来持つ辛み成分であり、空気に触れて酸化することで苦味を感じる原因となるようです。
普段口にする白菜は、品種改良によって苦味が抑えられているようですが、まれに『先祖返り』により昔の味に戻ってしまい、苦味を感じる個体ができてしまうのだとか。
なお、イソチオシアネートには抗酸化作用があるとされ、免疫力や健康維持のサポートに役立つと言われています。
健康に害を与えるものではないため、安心して食べられますよ。
ゴマ症
※写真はイメージ
白菜の表面に『ゴマ症』と呼ばれる、黒いゴマのような斑点を見たことはありませんか。黒い斑点の正体は『ポリフェノール』で、苦味成分の一種と言われているそうです。
ゴマ症は、肥料の与えすぎや気温の変化といった、生育環境のストレスによって発生する生理現象とされています。
ポリフェノールも人体に害はないとされ、抗酸化作用があるため健康維持のサポートにも役立つのだとか。「黒い点が気になるから」と削ぎ落とすには、もったいないと言えるでしょう。
ただし、黒い斑点が多いほど白菜がストレスを受けていることになります。斑点がないものに比べて味は落ちるとも言われているため、早めに食べるようにしましょう。
また、ゴマ症による斑点はこすったり加熱したりしても消えないそうです。黒い斑点をこすってみて、消えたりずれたりするようであれば、汚れやカビの可能性があることも覚えておくとよいでしょう。
白菜のゴマ症については次の記事でより詳しく解説しているため、あわせて参考にしてください。
白菜の黒い点は食べられる?カビとの見分け方を解説
「白菜に黒い点ができた。カビなのか食べられるのか、見分ける方法を知りたい」と、悩んでいませんか。白菜の黒い点は『ゴマ症』のケースがあり、その場合は食べてもよいそうです。本記事では、白菜の黒い点が何かを見分ける方法を解説します。
栽培時期
※写真はイメージ
白菜の苦味は、栽培される時期によっても変わると言われています。本来、白菜は寒さに強い冬野菜であり、気温が低いほど甘みが増す性質を持っているのだとか。
特に、甘みのあるおいしい白菜は、11~2月頃に収穫されたものと言われているようです。
ただし、白菜は1年中スーパーなどで見かける野菜であり「夏に売られている白菜は苦いのでは」と感じる人もいるかもしれません。
実際には、品種や作型、産地を工夫することで『春白菜』『夏白菜』『秋冬白菜』と分けて栽培されており、通年出回るように工夫がされているそうです。そうした春白菜や夏白菜には、むしろ甘いものも見られます。
旬は冬ですが、春や夏の高温期に出回る白菜がかならずしも苦いわけではありません。安心して料理に使ってみてくださいね。
保存状態
※写真はイメージ
前述でもご紹介したイソチオシアネートは、酸化することで苦味が出やすくなるため、保存状態が悪いと苦味を感じやすくなるようです。
特に、カットした白菜は断面が空気に触れやすく、注意が必要といえるでしょう。
白菜をおいしい状態で長期保存したい人には、『冷凍保存』がおすすめされています。
当ウェブサイトでは、白菜の適切な保存方法について解説した記事もあるため、気になる人は下記の記事を参考にしてくださいね。
白菜はどう保存するのが正解? ニチレイが教える技に「やってみます!」
白菜の保存方法が、冷凍食品などを販売する、株式会社ニチレイフーズ(以下、ニチレイ)のウェブサイトにて公開されています。ニチレイによると、白菜は冷凍保存ができるのだそうです!
白菜を冷凍するコツ 芯の部分を… 「これで火がよく通る!」
温かい鍋やスープが恋しくなる、冬。 白菜は、鍋に入れる野菜の定番として、この時期重宝されますよね。 白菜の保存方法は? 冬に大活躍の白菜ですが、ひと玉を一度に使い切れず、困ってしまうこともあるでしょう。 そこで、2024...
白菜の苦味を取る3つの調理方法
続いては、白菜の苦味を取る3つの調理方法をご紹介します。「苦味がどうしても気になる」と言う人は、ぜひ試してみてくださいね。
1.下ゆでする
※写真はイメージ
鍋や煮物の具材など、白菜を加熱調理する際は、下ゆでをして苦味を抑えるとよいでしょう。イソチオシアネートと言う苦味成分は、加熱によって苦味が減るとされているためです。
下ゆでの方法はとても簡単で、鍋やフライパンで湯を沸かし、カットした白菜を入れてサッとゆでるだけ。
なお「下ゆでせずにそのまま鍋に入れれば楽でよいのでは」と考える人もいるかもしれませんが、苦味を取る目的であれば下ゆでしたほうがよいとされています。その理由は、煮汁に苦味成分が溶け出してしまうためなのだとか。
鍋や煮物などに使用する際は下処理をし、下ゆでに使用した煮汁は利用せず、捨てるようにしてくださいね。
2.塩もみをする
※写真はイメージ
白菜の漬物やサラダなどを作る場合は、苦味を和らげる方法として塩もみが効果的とされています。塩もみの手順は、次の通りです。
1.白菜を洗い、水気を切る。
2.食べやすい大きさにカットした白菜をビニール袋やボウルに入れる。
3.小さじ2分の1〜1杯ほどの塩をふりかけ、全体が馴染むようにもみ込む。
4.数分おき、水分が出てきたらしっかりと絞る。
塩もみをすることで、塩の浸透圧によって白菜から水分が出て、苦味成分も一緒に抜けるのだとか。
下ゆでと比べてシャキシャキとした食感が残り、食べやすく仕上がりますよ。
3.味つけを濃くする
※写真はイメージ
苦味のある白菜は、濃い味つけの料理に使い、苦味を気にならなくするのも1つの方法といえます。
加熱調理であれば麻婆豆腐やカレーに、生のサラダであればドレッシングやマヨネーズなどと合わせることで、苦味が気にならなくなる可能性があるでしょう。
濃い味つけで苦味を打ち消しているだけですが、「下ゆでや塩もみの手間を省いて、すぐに料理に使いたい」と言う場合には有効な手段といえますよ。
苦味の少ない白菜の見分け方
※写真はイメージ
「苦い白菜も食べられることは分かったけど、できれば苦味の少ないおいしい白菜を食べたい」と考える人もいるでしょう。
そこで本章では、苦味の少ない白菜の見分け方を2つご紹介します。白菜を購入する際の参考にしてくださいね。
ただし、見た目に変化がなくても苦味を感じる場合もあるようです。購入後に苦味があると分かった時は、前述の調理方法で苦味を和らげるとよいでしょう。
1.黒い斑点がないもの
前述した通り、黒い斑点は苦味成分の一種で、黒い斑点が多いほど苦味が強くなり、味が落ちてしまうようです。
白菜を購入する際は表面をよく確認し、黒い斑点がないものを選ぶと、苦味の少ない白菜を見つけられる可能性が高まるでしょう。
2.葉が変色していないもの
白菜の葉が変色している場合、鮮度が落ちており、苦味を感じやすくなっている可能性があります。
白菜に含まれるポリフェノールは、空気に触れることで酸化し、赤色から茶色、黒色へと変化していくそうです。
同じく、白菜に含まれるイソチオシアネートも酸化によって苦味が増すと言われていることから、変色が進んでいるほど苦い白菜に可能性は高いといえるでしょう。
特に、カットして販売されている白菜は切り口が空気に触れがちで、変色しやすいため注意が必要なのだとか。
鮮度の高い白菜は、外側が濃い緑色、内側が黄色であると言われています。購入時の目安として参考にしてくださいね。
なお、酸化によって変色した白菜は、腐敗しているわけではないため、食べても問題はないようです。
ただし、苦味を感じる可能性はあるため、気になる人は、下ゆでや塩もみなどで苦味を取ってから調理に使うとよいでしょう。
白菜が苦くなる原因や対処法を理解しておいしく食べよう
白菜が苦くなる原因はいくつかありますが、いずれの場合も身体に害を与える可能性は低いようです。苦味がどうしても気になる人は、下ゆでや塩もみ、濃い味つけの料理に使うなどの方法で、苦味を取る工夫をしてみましょう。
また、完璧ではないものの、苦い白菜かどうかを見分けるポイントもあるため、購入時の参考にしてくださいね。
[文・構成/grape編集部]