保冷剤の中身は何?捨て方や再利用の方法を徹底解説
公開: 更新:

※写真はイメージ

カダイフの代用食材5選!自宅でできるドバイチョコレートレシピも紹介カダイフの代用食材として、春巻きの皮やそうめん、皿うどん、ビーフン、ココナッツロングなどがあります。本記事では、春巻きの皮で作るドバイチョコレートのレシピも紹介。家にあるものでカダイフを代用したい人は参考にしてください。

セルクルの代用品9選!代わりになる身近なアイテムを紹介この記事では、お菓子や料理で使うセルクルの代用品を紹介します。牛乳パックやペットボトル、厚紙など身近なアイテムを代用品として使う方法や、それを使う際の注意点などを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
- 取材協力
- ここに取材協力先


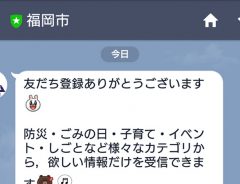


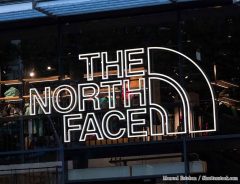
「保冷剤の中身はなんだろう」
「保冷剤を再利用できる方法が知りたい」
そんな疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
生鮮食品を保存するために買い物時にもらう保冷剤は、基本有害ではないといわれています。
そこで今回は、保冷剤の主成分について触れつつ、服についた際の対処法や捨て方を解説します。さらに、中身を再利用する方法についてもご紹介。
家に保冷剤がたくさんあり、再利用したいとお考えの方はぜひ参考にしてください。
保冷剤の中身は何?危険なの?
※写真はイメージ
保冷剤には大きく分けて2種類あります。『ソフトタイプ』と呼ばれるビニールに包まれたものと、『ハードタイプ』と呼ばれる硬いプラスチックの容器に入ったものです。
どちらも中身は同じで、98〜99%は水分であることが一般的。残りの1~2%が『高吸水性ポリマー』と呼ばれる物質が使われています。
高吸水性ポリマーは紙オムツなどの中に使われているものと同じで食用ではありませんが、触っても有害ではないといわれています。
また古い保冷剤には『エチレングリコール』と呼ばれる、体内で有害化する物質が含まれている可能性があるため、不安な場合は表示されている成分の確認をするとよいでしょう。
保冷剤のタイプで使い方や寿命は違う?
保冷剤は、主にソフトタイプとハードタイプで分けられますが、それぞれ使い方や寿命が異なるようです。順番にご紹介しましょう。
ソフトタイプ
※写真はイメージ
ソフトタイプは、形状が自由に変形するため食品や身体の部位に密着しやすく、保冷効果が高いのが特徴です。食品の保冷やケガの応急処置、お弁当の保冷に適しているでしょう。
ソフトタイプの寿命は一般的に約2~3年で、液漏れしたり、膨らんだりした時が寿命のサインと考えられています。
ハードタイプ
※写真はイメージ
ハードタイプは形状が固定されているため、積み重ねやすく、輸送時の安定性に優れているでしょう。
ただし、形状が固定されているため、細かい部分への密着性はソフトタイプに劣ります。そのため、宅配便や医療品の輸送、大型食品の保冷に使用するのがおすすめ。
ハードタイプの一般的な寿命は約3~5年と、ソフトタイプと比べて長持ちするようです。ヒビ割れや変形が寿命のサインと考えられています。
保冷剤の中身の捨て方
※写真はイメージ
使わなくなった保冷剤の中身をどのように捨てればいいのか困っている人もいるでしょう。保冷剤の中身を捨てる際には、基本的にお住まいの自治体の指示に従ってください。
一般的には紙オムツと同じように、可燃ゴミとして処分することが多いようです。
高吸水性ポリマーは非常に吸水性が高く詰まりやすいため、間違っても中身をトイレや排水口など、水に流すことは避けましょう。
保冷剤の中身を再利用する方法7選
※写真はイメージ
お買い物の際にもらう保冷剤をすぐに捨ててしまうのはもったいないと感じ、冷凍庫に保管している人も多いのではないでしょうか。
保冷剤は、暮らしの中で再利用が可能です。ここでは簡単に保冷剤の中身を再利用できる方法を7つご紹介します。
1.植木の保水剤
保冷剤の中身は、植木の保水剤として再利用できます。使い方はとても簡単で、保冷剤の中身を土の上に広げておくだけです。
保冷剤の中身の原料である高吸水性ポリマーが水分を含んでいるため、直接土の上に広げておくことで適度な湿り気を与えてくれます。水分が抜けてしまった後の保冷剤は、ゴミとして自治体が定めた方法で処分してください。
旅行などで数日間、植木に水をあげられない場合、この方法を活用すると安心してお出かけできるでしょう。また植木だけではなく、切り花の保水やフラワーアレンジメントのオアシスとしても有効活用できます。
ただし保冷剤の成分によっては、植物に影響を与えるおそれがありますので、確認してから使用しましょう。
2.消臭剤
保冷剤の中身の成分である高吸水性ポリマーには、ニオイを吸着する性質があります。この性質を利用して、消臭剤として再利用するとよいでしょう。お気に入りの空き瓶などに入れれば、中身を出しておくだけで簡単に作成できます。
使い方は、ニオイが気になる玄関やトイレなどに置いておくだけです。食紅や絵の具などで色をつけたり、ビー玉や貝殻、ビーズなどを入れたりすれば、インテリアとしても活用できます。子供との工作としても楽しめるでしょう。
ゲル状の中身が乾燥して白っぽく乾燥してきたら消臭効果が失われるため、ゴミとして処分してください。
3.虫除け
保冷剤の中身を取り出して空き瓶に入れたものに、虫の苦手な香りを含ませれば虫除けとして再利用できるようです。
レモングラスやペパーミント、シトロネラ、ユーカリ、ゼラニウムなどは、蚊やハエ、ダニなどの害虫が苦手な香りとされています。一方で人にはよい香りとしてリラックスをもたらすため、一石二鳥の効果が得られるでしょう。
また、クローブとペパーミントはゴキブリの苦手な香りといわれています。保冷剤の中身が入った瓶にアロマオイルを垂らして、キッチンの気になる場所に置いておくとよいでしょう。
なお、これらの香りは虫が苦手な香りとして知られてはいますが、殺虫効果はありません。
4.芳香剤
※写真はイメージ
保冷剤の中身を取り出して空き瓶に入れるだけで、消臭剤が完成するとご紹介しましたが、ここにアロマオイルを垂らせば芳香剤としても活用できます。
好きな香りを楽しみながら嫌なニオイを消臭できるでしょう。香りが消えたら、継ぎ足しながら使うとよいそうです。
使用するアロマオイルですが、トイレならユーカリやレモングラス、ティーツリーなどのハーブや樹木系がおすすめ。
ほかには、玄関や下駄箱ならオレンジやレモンなどのシトラス系、リビングなどにはラベンダーやベルガモットなどの落ち着く香りを選ぶとよいでしょう。
5.熱中症や発熱時のケア
※写真はイメージ
冷凍庫の中で凍ったままになっている保冷剤は、熱中症や発熱時のケアに非常に役立ちます。高熱が出たら、首の付け根や脇の下、太ももの付け根などを保冷剤で冷やすとよいでしょう。
そのまま使うと冷たいため、タオルやガーゼで包むことをおすすめします。少し大きいサイズの保冷剤なら、暑くて寝苦しい夜の氷枕の代わりとしても便利です。また熱中症のケアにも活用できます。
ほかにも打撲の際のアイシングとしても活用が期待できます。保冷剤を凍らせておくことで発熱時や熱中症などの際、身体を冷やすケアに再利用できるでしょう。
6.保冷バッグに入れる
お買い物でもらった保冷剤は、そのまま凍らせて次のお買い物に再利用できます。お買い物に使う保冷バッグの中に入れておけば、生ものを購入した会計の後に、わざわざ保冷剤や氷をもらいに行く必要がありません。
お買い物だけではなく、アウトドアの際にクーラーボックスに入れておけば、飲み物を冷やしておくことも可能です。このように凍った保冷剤は、食品や飲み物を冷やして保管したり持ち運んだりする時に大変役に立ちます。
7.暑い時期のお弁当に使用
※写真はイメージ
凍ったままの保冷剤は、夏の暑い時期のお弁当づくりにも大活躍します。
作りたてのお弁当をそのまま保冷剤の上に載せておけば、粗熱を取り、容器を持ちやすくしてくれるでしょう。お弁当と一緒にお弁当バッグの中に入れておけば、暑い時期でも安心してお弁当が食べられます。
このように、保冷剤は一度使ったらおしまいではなく、多くのシーンでの再利用が期待できます。
保冷剤の中身が漏れて服についた際の対処法
※写真はイメージ
保冷剤が破れて中身が服についてしまうこともあるでしょう。少量なら水やぬるま湯で洗い流せますが、大量についた場合は、そのまま排水口に流すことはあまりおすすめしません。
また、高吸水性ポリマーには水分を吸収する性質があるため、排水口が詰まる原因になる可能性があります。保冷剤の中身が大量についた場合は、排水口には流さず一度拭き取ってゴミに捨ててから、洗い流すとよいでしょう。
保冷剤の中身は触っても大丈夫!賢く再利用しよう
保冷剤の中身の成分は、大部分が水分で残りは高吸水性ポリマーという、紙オムツと同じ物質が使われています。
保冷剤の中身が破れて服についた際には、少量なら洗い流してもよいですが、大量の保冷剤は排水口を詰まらせる原因になるため、一度拭き取ってから洗うようにしましょう。ゴミとして捨てる際には、自治体の指示に従ってください。
冷凍庫に溜まった保冷剤は、植物の保水剤や消臭剤など、多くのシーンで再利用できます。
本記事を参考に、ただ捨てるだけではもったいない保冷剤を賢く再利用して、暮らしの中で役立ててください。
[文・構成/grape編集部]