本当に使える!簡単ライフハック15選|掃除・料理の片づけ・冬の寒さ対策にも!
公開: 更新:

※写真はイメージ
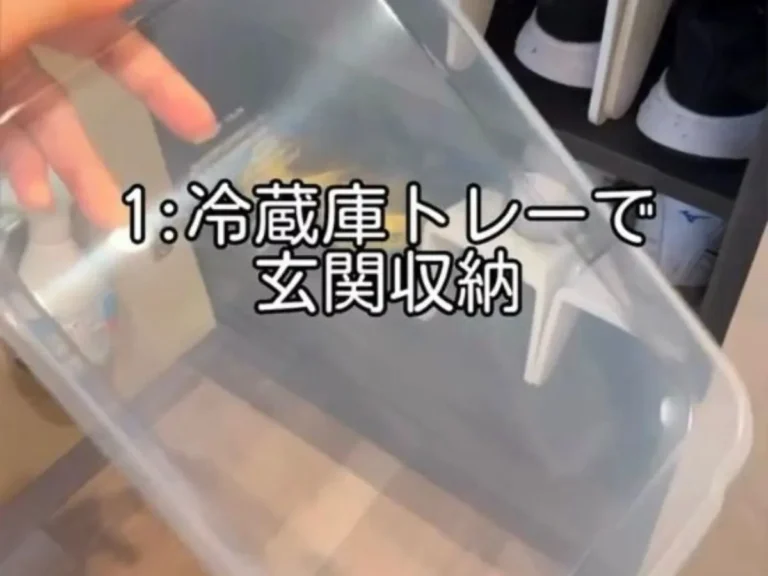
整理のプロがやってる玄関収納とは? 内容に「助かる」「真似したい」靴箱は汚れや臭いが気になるものです。しかし、いちいち靴をどかして掃除するのが面倒で、清潔さを保つのはなかなか難しいですよね。本記事では、誰でも手軽に取り入れられる玄関収納の工夫を3つ紹介します。

ウタマロクリーナーで排水口を洗うと? 仕上がりに「驚き」「リピ決定」【排水口掃除術4選】水回りの排水掃除は、なかなか大変です。そこで、キッチンや洗濯機の排水ホースの掃除術を4つ集めました。






忙しい毎日、できるだけ家事の負担は減らしたいですよね。
水回りの掃除や料理の後片付けは、気付けば手間がかかってしまうもの。
ちょっとした工夫で楽になる方法があれば、ぜひ試してみたいところです。
この記事では、掃除の手間や洗い物を減らすアイディア、寒い季節を快適に過ごすコツを紹介します。
水回りの掃除の手間を減らすライフハック6選
※写真はイメージ
キッチンや浴室など、水回りの掃除は面倒に感じがち。こまめに掃除できなくて、気付けば時間がかかってしまうことも多いですよね。
しかし、少しの工夫で掃除の手間を減らせば、日々の負担を軽くすることができるのです。
水回りの掃除の時間を短縮できるアイディアを6つ紹介します。
排水口のゴミ受けに『アルミホイル』を入れる
排水口のヌメリや嫌な臭い、気付いた時にはひどくなっていて、掃除が面倒に感じることはないでしょうか。
そんな悩みを手軽に解決できるのが『アルミホイル』を使った方法です。
手順はとても簡単で、アルミホイルを軽く丸めたボールを数個作り、排水口のゴミ受けに入れるだけ。
設置したアルミホイルのボールが水に触れると金属イオンが発生して、ヌメリや臭いを抑えてくれる効果があります。
特別な道具を用意する必要もなく、ちょっとした工夫で清潔をキープできると助かりますよね!
新しいアルミホイルを使うのがもったいないという人は、使用済みのものを再利用しましょう。
アルミホイルのボールは月に一回程度交換すればいいので、とてもお手軽な方法ではないでしょうか。
詳しい方法はこちらの記事でも紹介しています。今日から早速チャレンジしてみてください!
シンクには「アルミホイルが効果的」 活用テクに「心がける」「これは助かる」
アルミホイルを使ったライフハックは、ほかにもあります。
こちらの記事でも紹介しているので、お歳暮でアルミホイルをたくさんもらった時などに知っておきたいですね。
排水口にアルミホイルを詰めると? 企業が試した結果が「すごい」
三角コーナー不要!『ポリ袋』を生ゴミ受けにする
三角コーナーの掃除はヌメリが不快で、つい後回しにしてしまうことはありませんか。
そんな悩みを解決できるのが、ポリ袋を生ゴミ受けとして活用する方法です。
三角コーナーを置かないことでシンクの掃除が楽になるだけでなく、使い終わったら袋ごと捨てるだけなので、手間いらず。
スーパーで買い物した後の余ったポリ袋など、生ゴミ受けとして再利用すれば、わざわざ袋を購入しなくて済むので節約にもなるでしょう。
また、シンクの端にポリ袋をセットするだけでもいいですが、自立する水切りネットやスタンドに使えるアイテムがあれば、さらに快適かもしれません。
こちらの記事でも紹介しているので、気になる人はチェックしてみてください。
三角コーナーはもう不要!? 立てる水切りネットで衛生的なシンクをキープ
ダイソーで買った『スタンド』 意外な使い道に「三角コーナーいらず」
100均のアイテムも賢く使って、掃除の手間を省いていきましょう!
入浴剤代わりに『重曹』で湯船の汚れ防止
湯船の汚れをできるだけ防ぎたくても、毎日しっかり掃除するのは大変ですよね。
そんな時に役立つのが、入浴剤代わりに『重曹』を使って皮脂汚れを付きにくくする方法です。
手順は以下の通りです。
重曹の種類には、医療用、食品用、工業用(掃除用)の3つがあり、『医療用>食品用>工業用(掃除用)』の順番で純度の割合が高いです。
入浴剤代わりに使う重曹としては、食べる前提でつくられている食品用の重曹がよいでしょう。
食品用の重曹であれば、万が一口に入ってしまっても安心です。
重曹風呂の頻度としては、必要以上に肌の油分を落とさないように、週に一回もしくは二回にしておきましょう。
人によっては肌への刺激が強くなってしまう場合もあるため、自分の肌に合うかどうか、まずは大さじ1杯などの少量から試してみることをおすすめします。
また、浴槽に重曹を入れた際の注意点は、『追い焚きはしない』ことです。
重曹には銅を痛める作用があり、風呂釜や配管を傷付けてしまう恐れがあるため、追い焚きを終えた後に投入したほうがよいでしょう。
重曹を入浴剤代わりに使う場合の注意点は、こちらの記事でも紹介しています。
重曹風呂を試す前には、ぜひチェックしてみてくださいね。
『重曹湯』はメリットだらけ! 企業の解説に「驚き」「入浴剤要らず」
お風呂後は壁や床全体に『温水』をかける
お風呂場のカビや水垢はできるだけ防ぎたいもの。
かといって、防カビ専用の掃除アイテムを使ったり、毎日水切り用のスクイージーで浴室全体の水気を取ったりするのは、手間もお金もかかりますよね。
実は、特別な洗剤や道具を使わずに、もっと手軽に対策できる方法があるのです。
それがお風呂の後に壁や床全体に『温水』をかけるというシンプルな方法です。
お風呂から出る前には、「壁や床にシャワーをかけるようにしている」という人も多いのではないでしょうか。
この時、冷水派と温水派で分かれるかと思いますが、カビや雑菌の繁殖を防ぐなら、温水のほうが効果的だといわれています。
45℃以上のお湯をかけることで、カビが発生しづらくなるそうです。
また、浴室の湿度を下げるために換気扇を回すことで、さらにカビが発生しにくい環境にできるとのこと。
毎日のちょっとした習慣できれいが続くのは嬉しいですよね。
お風呂場をきれいに保ちたい人は、こちらの記事でほかの方法も紹介しているので要チェックです!
お風呂のピンク汚れをシャットアウト! 簡単にできる4つの予防法
夜寝る前に『重曹』を便器の水たまり部分に入れる
トイレの黒ずみ汚れ、気付いた時には落としにくくなっていて、困ることはありませんか。
この黒ずみ汚れを、寝る前のひと手間で手軽に掃除できる方法を紹介します。
必要なアイテムは、重曹のみ。重曹は弱アルカリ性の性質を持っていて、トイレにできやすい黒ずみなどの酸性の汚れを中和するのに役立ちます。
黒ずみ対策としては、寝る前に重曹を便器の水たまり部分に振りかけておくだけで準備完了です。
翌朝、ブラシなどで軽くこすって流すことで汚れが付きにくくなり、消臭・抗菌効果も期待できます。簡単なので、忙しい日々の中でも続けやすいでしょう。
ただし、根深いカビの場合は、重曹だけでは除去しきれない可能性もあるので、市販のトイレ用洗剤やクエン酸と組み合わせる必要があるかもしれません。
また、重曹を流しきれないとアルカリ成分が固まってしまい、新たな汚れの原因になる可能性もあるそうなので、放置のしすぎには注意してくださいね。
『トイレマットを撤去』して床掃除を楽に!
トイレは意外とホコリの溜まりやすい場所。きれいなトイレを保つためには、こまめな床掃除やトイレマットの洗濯も必要ですよね。
トイレマットは尿はねが床に付着するのを防いでくれますが、不衛生に感じ「洗濯機で洗うことに抵抗があり、手洗いしている」という人も多いのではないでしょうか。
そんな人に試してほしいのが、思い切って『トイレマットをなくしてみる』ということです。
トイレマットを置かないことで、床が汚れてもサッと拭き掃除ができ、トイレの床掃除の負担が減って気持ちよく過ごせるのではないでしょうか。
こちらの方法はトイレマットを置く派、置かない派で好みが分かれそうですが、一度試してみるといいかもしれません!
料理の洗い物を減らすライフハック3選
※写真はイメージ
料理の後片付けはできるだけ楽にしたいもの。洗い物がたまると、キッチンに立つのもおっくうになりませんか。
使う道具や少しの工夫で、洗い物を極力増やさずに調理できるアイディアを3つ紹介します。
フライパンを『キッチンペーパー』で拭いてから洗う
調理後のフライパンは、すぐに洗うとギトギトな油汚れで、手もスポンジもベタベタになって不快ですよね。
汚れたスポンジでそのままほかの食器を洗ってしまうと、油汚れが移って洗い直しということにもなりかねません。
そんな時は、先にキッチンペーパーでフライパンの油汚れを軽く拭き取っておけば、必要以上に手やスポンジが汚れずに済みます。
手やスポンジを洗い直す必要なく次の洗い物に移れることで、手間もストレスも減るでしょう。
スポンジが汚れにくくなるほかにも、使う洗剤の量も少なく済むので経済的かもしれません。
『クッキングシート』をまな板に敷く
調理中、「先に野菜を切っておきたかったのに、お肉を先に切ってしまった」なんて経験はありませんか。
そんな時は、クッキングシートを敷いてから食材をカットすることで、まな板を途中で洗う手間が省けるのでおすすめです。
生肉や魚を切った後は、衛生面を考えてハイターで除菌する人も多いと思いますが、クッキングシートを敷いておけば、捨てるだけなので片付けも簡単でしょう。
クッキングシートがない場合は、ラップなどでも代用できますが、クッキングシートよりも破れやすいので注意が必要です。
また、クッキングシートより丈夫で破れにくいという点では、『まな板シート』もおすすめ。
ホームセンターの『カインズ』や100円ショップの『ダイソー』などさまざまな店舗で販売されています。
クッキングシートと『まな板シート』は使い心地の好みや費用、使用頻度によって使い分けるとよさそうです。
実際に使ってみた体験記事もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
「買って損なし」「手間減った」 何度もまな板を洗うのが面倒なら…?
SNSで話題のダイソー『まな板シート』は丈夫で便利! 使い心地を試してみた
包丁・まな板を使わず『キッチンばさみ』でカット
包丁とまな板を使うと、洗い物が増えてしまいます。さらに、野菜とお肉など、切る食材によっては何度も洗う必要が出てくるでしょう。
洗い物が面倒な時は、キッチンばさみの出番です。直接フライパンやそのままお肉トレーの上でカットができて、洗い物も減らせます。
包丁もまな板も使わずに料理ができるとお手軽ですよね。
キッチンばさみは取り外しができて、簡単に洗えるタイプも人気です。
こちらの体験記事でも紹介しているので、気になる人は実際に使ってみた感想をチェックしてみましょう。
「ここまでとは…」「早く買えばよかった!」 貝印の『キッチンばさみ』を1週間使ってみた
寝る時にできる寒さ対策ハック3選
※写真はイメージ
冷え込む季節は「布団に入ってもなかなか温まらない」と寝る時の寒さに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
ちょっとした工夫で、寝る時の冷えを防げるとありがたいですよね。
快適に眠るための寒さ対策として、今日から試せる簡単な方法を3つ紹介します。
『靴下を2枚重ね履き』する
寝る時に布団に入っても、足先だけはひんやり冷たくて、なかなか温まらないことってありますよね。
足先が冷えると、眠りを妨げる原因にもなってしまうそうです。
足先の冷えが気になる時には、『靴下を重ね履き』する方法が取り入れやすいでしょう。
重ね履きをする際は、まず1枚目に吸湿性のいいシルク素材のような汗をよく吸う素材のものを履き、その上から綿やウール素材の厚手のソックスを履くのがおすすめ。
また、足が窮屈にならないよう、2枚目に重ね履きする靴下は少し余裕のあるサイズのものにしましょう。
ただし、素材によっては重ね履きをすることで汗の逃げ道がなくなり、冷えてしまう可能性もあるので注意が必要です。
靴下の重ね履きについては、警視庁が推奨するアルミホイルを使った方法もあります。
簡単に説明すると、1枚目を履いた後、靴下の上からアルミホイルを足に巻き、さらにその上に2枚目の靴下を履く、という方法です。
輻射(ふくしゃ)熱という熱の伝わり方により、足先が温まるという仕組みなのだとか。
災害などの非常時にも役立つアイディアなので、こちらもぜひ覚えてくださいね。
単に重ね履きをするよりも? 警視庁が推奨したやり方に「これはいい!」
『布団と毛布を重ねる順番』が重要
寝る時に布団に入ってしばらくしても、なかなか温まらず、寒さで眠れないことってありませんか。
そんな時に試してみてほしいのが、布団と毛布の重ね方を見直すことです。
実は、羽毛布団とそれ以外の布団では、毛布を重ねる順番にコツがあります。羽毛布団の場合、毛布を『羽毛布団の上』にかけるほうが暖かいそうです。
毛布を羽毛布団の下にすると熱が逃げやすく、逆に寒くなってしまいます。外側から温もりを閉じ込めて、しっかり保温しましょう。
一方で、羽毛以外の布団は毛布を『布団の下』にかけるほうが暖かいのだとか。
重ねる順番が重要だったとは、意外ですよね。もし「逆にしていた」という人は、今夜から早速試してみるのはいかがでしょうか。
『布団の端を折り込む』ことで冷気をシャットアウト
寝ている時に布団や毛布の隙間からひんやり寒さを感じることってありますよね。
そんな時に試してみてほしいのが、布団や毛布の端を内側に折り込む方法です。
4面を内側に折り込むことで、ぬくもりが逃げにくくなります。
寝袋のように身体を包み込むイメージです。特に道具もいらないので、簡単に試すことができるでしょう。
ちょっとした工夫でぐっすり眠れるようになるかもしれません。
外出時にできる寒さ対策ハック3選
※写真はイメージ
外に出るたびに冷たい風が身にしみる季節。防寒しているつもりでも、手足や身体が冷えることはありませんか。
寒い日の外出は、できるだけ暖かく過ごしたいですよね。
ちょっとした工夫で身体を温める方法やアイテムを紹介します。
出かける前に『軽くストレッチ』する
寒い季節、しっかり防寒していても寒さを感じることは多いですよね。それはもしかしたら、身体自体が温まっていないからかもしれません。
そこでおすすめなのが、外出前に軽いストレッチで身体を温めることです。
ここでは、肩回りのストレッチ方法を紹介します。やり方は以下の通りです。
背中の肩甲骨周りには、脂肪を燃焼し熱を生み出す働きを担う褐色(かっしょく)脂肪細胞があり、肩、肩甲骨周りを動かすことで、身体がポカポカしてきますよ。
肩こり改善が期待できるほかにも、褐色脂肪細胞を活性化させることでダイエット効果も期待できるでしょう。
このほかにも、ラジオ体操も肩周りを大きく動かすストレッチなのでおすすめです。
寒い日のお出かけ前に試してみてはいかがでしょうか。
カイロを『腰』『お腹』『背中』に貼る
寒い季節に大活躍するのがカイロですが、貼る位置によって効果やメリットが違うと聞けば、知っておきたいものですよね。
カイロを貼る部位としては、『腰』『お腹』『背中』がおすすめです。
ここでは、それぞれの部位を温めるメリットを紹介します。
身体の中心部を温めることで、全身がポカポカして冷えにくくなるので、ぜひ覚えてくださいね。
腰を温めるメリット
腰が冷えるというイメージはあまりないかもしれませんが、実は血流が滞りやすい部位の1つだそうです。
腰を温めることで、下半身全体の血流がよくなり、足の冷えやむくみを軽減する効果が期待できるので、特にデスクワークの人は腰にカイロを貼るのがおすすめです。
カイロを貼る場所としては、背中側でおへその真裏にあたる部分を中心に、カイロを横向きして貼るのがいいでしょう。
おへその真裏(背中側)には、『命門(めいもん)』といわれる、その名の通り生命の門とされる重要なツボがあります。
さらに、そこから左右両方の指2本分の位置には、『腎兪(じんゆ)』というツボがあり、このあたりにカイロを貼ると腰全体を温めることができます。
また、腰が冷えることで筋肉が硬直し、腰痛やぎっくり腰のリスクが高まるのだとか。
カイロで温めることで血流がよくなり、筋肉のこわばりを和らげ、腰痛の軽減が期待できます。
お腹を温めるメリット
お腹を冷やすのはよくないと聞いたことがあり、なんとなく気を付けているという人も多いのではないでしょうか。
冷えるとよくないといわれる理由としては、『お腹の冷えが腸の動きに影響するから』というのが大きいようです。
冷えによって胃腸の働きが低下すると、消化不良や便秘、下痢の原因にもなるとのこと。寒い季節はお腹も冷えやすくなるため、より一層意識してお腹を温めるようにしましょう。
そこでおすすめしたいのが、カイロをお腹に貼ってあたためるという方法です。
お腹を温めることで腸の動きが活発になり、便秘改善にも役立つほかにも、身体が温まると自律神経が整うため、ストレス軽減も期待できます。
また、お腹を温めることで、子宮周りの血流が良くなり、生理痛の軽減も期待できるのだとか。
便通や生理痛で悩んでいる人は、一度お腹を温めるという方法を試してみるといいかもしれませんね。
背中を温めるメリット
寒い時期、知らず知らずのうちに肩に力が入ってしまい、肩が凝ることがありますよね。
意識していても、なかなか力を抜くというのは難しいものです。
そんな時には、肩甲骨の間にカイロを貼るという方法を試してみるのはいかがでしょうか。
首から肩・背中にかけては、僧帽筋(そうぼうきん)と呼ばれる大きな筋肉があり、 この筋肉を温めることで全身の血行促進が期待できます。
また、この僧帽筋を温めることで凝りやこわばりをほぐす効果が期待でき、肩こりの解消にも効果的だそうです。
寒さ対策だけでなく肩こりの改善にもつながるかもしれないと聞くと、試してみたくなりますね。
カイロを貼るおすすめ部位については、こちらの記事でも紹介しています。
ほかにどんなところに貼るとよいのか気になる人はチェックしてみてくださいね。
寒い季節でも全身ポカポカ! 使い捨てカイロを貼るおすすめ部位をアイリスオーヤマが解説
『首・手首・足首』をしっかり防寒する
寒い時には『首』がつく部分を温めると、身体全体が冷えにくくなると聞いたことはありませんか。
皮膚が薄く、太い血管が通っている『3つの首』を温めれば、効率よく全身の血液を温めることができるというのが理由のようです。
そこで、ここでは『首・手首・足首』を温めるために効果的な外出時に使えるアイテムを紹介します。
寒い時期はマフラーや手袋などをしっかり着けて、外出の際は防寒対策を万全にして出かけましょう。
首の防寒対策
寒い日にハイネックのインナーやセーターを着ている人も多いでしょうが、暖房のよく効いている部屋では逆に熱くなってしまうなど、調節が難しいところが難点でもあります。
その点では、着脱のしやすいマフラーのほうが取り入れやすいでしょう。
ただ、マフラーをうまく巻けていないと、隙間から風が入ってきて寒いですよね。
実感している人も多いかもしれませんが、マフラーの巻き方によっても暖かさが違ってくるのです。
一番身体が暖まりやすいマフラーの巻き方を調査したので、どの巻き方がもっともよかったかを、こちらの記事でチェックしてみてください。
一番身体が暖まりやすいマフラーの巻き方に「冷気を感じない」「しかも簡単!」
手首の防寒対策
外出時に手首を温めるには手袋が効果的です。
しかし、手袋をしたままだとスマホ画面が反応してくれず、手袋を外して操作している人も多いのではないでしょうか。
そんな人におすすめしたいのが、スマホ対応の手袋です。
寒い屋外や電車の待ち時間に、手袋を付けたままスマホを操作できると便利ですよね!
こちらの記事ではおすすめのスマホ対応手袋を紹介しているので、気になる人はチェックしてみてください。
スマホ対応のレディース手袋のおすすめ5選 「デザインもめっちゃおしゃれ」
足首の防寒対策
足首・足元を温めるにはレッグウォーマーがおすすめです。
オシャレなものだと室内でも外出先でも使えて、ファッションの一部にもなりそうです。
こちらの記事では、『まるでこたつ』というネーミングのレッグウェアを実際に履いてみた感想を紹介しています。
足元の冷えが気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
「足が冷えるのはヤダ!」 レッグウェア『まるでこたつ』シリーズの実力は?
ライフハックで毎日をもっと快適に!
※写真はイメージ
今回は少ないアイテムで簡単に試せるライフハックや寒い時期を乗り越えるためのアイディアなどを紹介しましたが、いかがでしたか。
ちょっとした工夫が、毎日の暮らしをもっと楽にしてくれるかもしれません。
まずは取り組みやすい身近なものから毎日の習慣に取り入れて、快適な生活を楽しみましょう!
grapeでは、ほかにも役に立つライフハックをいろいろと紹介しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
ライフハック記事一覧
[文・構成/grape編集部]